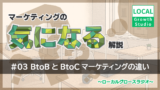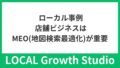ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
この記事は、「マーケティング施策の全体像 〜BtoBとBtoCの違いを理解する〜」について記載しています。
この記事はポッドキャストでも音声解説を行っております。各種サイトで無料で聞くことができます。
マーケティング施策を理解するための基本フレーム
マーケティング施策を設計する際、混乱を避けるためにまず押さえておきたい3つの軸があります。これらを理解することで、自社に最適な施策を選択できるようになるのです。
1. 顧客のフェーズ
顧客の状態によって、適切なアプローチは大きく変わります。ここでは3つのフェーズに分けて考えてみましょう。
潜在層(認知〜初期接触)
まだ課題を認識していない層です。商品やサービスの存在自体を知らない段階にあります。このフェーズでは、課題の認識を促し、自社ソリューションの存在を知ってもらうことがゴールになります。
準潜在層(興味・関心)
課題を認識し始めた層です。解決策を探し始めている段階で、情報収集を行っています。このフェーズでは、自社ソリューションの概要理解と、さらなる情報収集意欲を高めることがゴールです。
顕在層(比較検討)
具体的な解決策を探している層です。競合比較や価格検討をしている段階にあります。このフェーズでは、自社が最適な選択肢であることを示し、購入・契約の決断を促すことがゴールとなります。
これらのフェーズごとに適切な施策を設計することで、効率的なマーケティングが可能になります。例えば、顕在層に対して「課題認識を促す」コンテンツを提供しても効果は限定的です。逆に、潜在層に対して「今すぐ購入」を促すのも効果的ではありません。
2. 施策のカテゴリ
マーケティング施策は、大きく5つのカテゴリに分類できます。それぞれ特徴が異なるため、バランスよく組み合わせることが重要です。
オーガニック施策
検索エンジンやSNSからの自然流入を促す施策です。SEO対策やコンテンツマーケティングがこれに当たります。初期コストはかかりますが、長期的な資産となり、継続的な効果が期待できます。
ペイド施策
広告などの有料施策です。リスティング広告、SNS広告、ディスプレイ広告などが含まれます。即効性はありますが、配信を停止すると効果もすぐに消えるため、継続的なコストが発生します。
ナーチャリング
見込み顧客の育成施策です。メールマーケティングやコンテンツ配信などを通じて、顧客との信頼関係を構築していきます。時間はかかりますが、コンバージョン率の向上につながります。
BDR(Business Development Representative)
営業活動的な施策です。テレアポ、フォーム営業、外部パートナー連携などが含まれます。人的リソースは必要ですが、直接的な成果に結びつきやすいという特徴があります。
アライアンス
提携による施策です。共催セミナーやクロスプロモーションなどがこれに当たります。他社のリソースやブランドを活用できるため、効率的な展開が可能です。
3. コスト特性
投資対効果を考える上で重要な視点です。大きく2つに分けることができます。
ストック型
SEOやコンテンツマーケティングなど、効果が蓄積される施策です。初期投資は大きいですが、時間とともに効果が持続・拡大する特徴があります。長期的な視点では費用対効果が高くなります。
フロー型
広告など、都度コストが発生する施策です。効果は即時的に現れますが、投資を止めると効果も消失します。短期的な成果を求める場合に有効です。
この3軸を踏まえた上で、BtoBとBtoCそれぞれの特徴的な施策を見ていきましょう。
BtoBマーケティングの特徴と主要施策
BtoBビジネスでは、案件単価が高く、購買意思決定に関わる人数も多いため、信頼構築と専門性のアピールが重要になります。主要な施策を見ていきましょう。
1. オーガニック施策
オウンドメディア(SEO重視)
専門性の高い情報発信による見込み客獲得です。業界の課題や解決策に関する情報を提供することで、信頼性を構築します。
コンテンツ例としては:
- 業界トレンド解説
- 課題解決ノウハウ
- 事例紹介
重要ポイントとしては:
- 定期的な更新(検索エンジンでの評価向上)
- 専門性の担保(信頼性の構築)
- 読者ニーズの把握(関連キーワード分析)
私が作成したBtoBのWEBサイト制作では、業界特有の課題に焦点を当てたコンテンツ発信により、以前のオーガニック流入から20倍以上の成長につながりました。
共催セミナー
パートナー企業との共同開催による相互送客です。単独開催に比べてコスト分散、集客力の向上、信頼性の向上といったメリットがあります。
展開方法としては:
- オフラインセミナー(対面での深い関係構築)
- ウェビナー(地理的制約の解消、録画の資産化)
- ハイブリッド型(双方のメリットを活かす)
特に補完関係にある企業との共催は、参加者にとっても価値が高く、双方にとって効果的な施策となります。
プレスリリース
業界メディアでの露出獲得です。新サービス発表、事業展開告知、業績報告などの際に活用します。直接的な集客効果は限定的ですが、信頼性向上や認知拡大に効果があります。また、SEO的にも価値のある被リンクを獲得できるケースもあります。
2. BtoB ペイド施策
SNS/ディスプレイ広告
ビジネス層向けのターゲティング配信です。特定の業種、職種、企業規模などで絞り込んだ配信が可能です。
運用方法としては:
- Google、Facebook、Instagram、LINE、SmartNewsの自社運用
- 広告代理店への発注
BtoBの場合、純粋なコンバージョン獲得だけでなく、認知度向上やブランディングの観点も重視する必要があります。
展示会/カンファレンス
リアルな商談機会の創出です。特に対面での信頼構築が重要な商材の場合、効果的な施策となります。
実施内容としては:
- ブース出展(来場者との接点作り)
- スポンサーセッション(自社の知見をアピール)
- ネットワーキング(業界内でのつながり構築)
単なる製品紹介ではなく、業界課題への解決策として自社ソリューションを位置づけることが重要です。また、展示会後のフォローアップ体制も成果を左右します。
3. BtoB ナーチャリング施策
MA(マーケティングオートメーション)活用
顧客行動の分析と自動的なアプローチ設計です。見込み客の行動履歴に基づき、最適なタイミングでの接触を自動化します。
主な機能としては:
- リード獲得からスコアリング(見込み度の数値化)
- メール配信の自動化(行動トリガーに基づく)
- 顧客行動の可視化(サイト閲覧履歴など)
活用ポイントとしては:
- スコアに基づく優先順位付け(営業リソースの最適配分)
- コンテンツの段階的提供(顧客フェーズに合わせた情報提供)
- 営業部門との連携(リードの引き渡しタイミングの最適化)
クローズドイベント
選別された見込み顧客との関係構築です。少人数での濃密なコミュニケーションにより、信頼関係を深めます。
実施形態としては:
- ユーザー会(既存顧客中心)
- 勉強会(業界知識の共有)
- 交流会(ネットワーキング中心)
重要事項としては:
- 参加者の選定(質の高いリードの招待)
- コンテンツの質の担保(参加者にとっての価値提供)
- フォローアップの設計(イベント後の関係性発展)
4. BtoB BDR施策
フォーム営業/テレアポ
ポイントとしては:
- ターゲットの選定(顧客ニーズがあう企業を選ぶ)
- ターゲットのインサイト・ニーズにあわせた文面やスクリプト
- 事前情報収集による顧客にあわせた会話内容
外部パートナー連携
顧問サービスなどとの連携による見込み客紹介です。信頼性の移転、効率的な見込み客獲得、専門知識の補完といったメリットがあります。
例えば、税理士事務所と会計ソフトベンダーの連携、システム開発会社とクラウドサービスの連携など、互いの顧客基盤を活かした関係構築が効果的です。
BtoCマーケティングの特徴と主要施策
BtoCビジネスでは、大量の顧客獲得が必要となるケースが多く、効率的な集客と顧客育成が重要になります。主要な施策を見ていきましょう。
1. オーガニック施策
サービスサイト(SEO対策)
基本となるWebサイトで、検索エンジンからの自然流入を最大化することが目的です。長期的な集客基盤として必須の施策と言えます。構築コストはかかりますが、効果は蓄積されていくため、中長期的には高いROIが期待できます。
実施のポイントとしては以下が挙げられます:
- 重要キーワードでの上位表示を目指す
- ユーザビリティとSEOのバランスを取る
- コンバージョン導線の最適化
サブSEOサイト
特定のキーワードや用途に特化したサイトです。メインサイトでは取りこぼす可能性のあるニッチな需要の取り込みが可能になります。メインサイトとの相乗効果も期待できます。
活用例としては:
- 商品カテゴリ別のミニサイト
- 使い方専門サイト
- 比較・レビューサイト
例えば、家電メーカーが「掃除機の選び方ガイド」というサブサイトを運営し、自社製品の認知拡大につなげるといった方法があります。
SNS発信
各プラットフォームの特性を活かした情報発信です。ユーザーとの関係構築や、ブランドイメージの醸成に効果的です。
プラットフォーム別の特徴としては:
- X:リアルタイム情報、カスタマーサポート
- Instagram:ビジュアル訴求、ライフスタイル提案
- YouTube:詳細な商品説明、使い方動画
- TikTok:若年層向け、トレンド発信
- note:深い情報発信、ブランドストーリー
これらのプラットフォームは、それぞれ特性が異なるため、自社のターゲット層や提供価値に合わせて選択することが重要です。すべてのプラットフォームで発信するのではなく、重点領域を決めて集中的に取り組むのが効果的です。
2. BtoC ペイド施策
SNS広告
各SNSプラットフォームの広告配信システムを活用した施策です。詳細なターゲティングが可能で、クリエイティブの差し替えも容易なため、テストマーケティングに適しています。また、予算調整の自由度も高いという特徴があります。
主な配信面としては:
- Facebook/Instagram:フィード、ストーリーズ、リール
- X:タイムライン、検索連動
- LINE:トーク画面下部、タイムライン
- YouTube:動画前後、バナー表示
特に初期段階では、小規模な予算でA/Bテストを繰り返し、効果の高いクリエイティブやターゲットセグメントを見つけ出すことが重要です。
アプリ広告
GoogleやAppleの広告プラットフォームでのアプリ訴求です。アプリビジネスの場合、インストール数を増やすための重要な手段となります。
活用方法としては:
- ストア内での露出増加
- 競合アプリユーザーへの配信
- リエンゲージメント施策(一度インストールしたが使っていないユーザーへの再訴求)
アプリのLTVに基づいた適切な獲得単価設定が重要です。また、インストール後の継続率を高めるための施策と組み合わせることで、効果を最大化できます。
リスティング広告
検索意図が明確なユーザーへのアプローチです。能動的な検索へのアプローチとなるため、即効性が高く、効果測定も容易という特徴があります。
重要な設定項目としては:
- キーワードの選定(競合度、検索ボリューム、意図の明確さを考慮)
- 入札価格の調整(ROIを見ながら適宜調整)
- 広告文の最適化(CTRを高めるための工夫)
特に、「購入」「比較」「レビュー」など、顕在ニーズを示すキーワードに対しては積極的に出稿することで、効率的な顧客獲得が可能になります。
3. BtoC ナーチャリング施策
メール配信
顧客データベースを活用した段階的なアプローチです。既存顧客のリピート促進や、見込み客の育成に効果的です。
ポイントとしては:
- セグメント別の配信設計(購買履歴、閲覧行動などに基づく)
- A/Bテストの実施(件名、内容、送信時間などの最適化)
- 開封率・クリック率の改善(継続的な分析と改善)
適切なセグメンテーションを行うことで、同じメール施策でも反応率が2〜3倍変わることも珍しくありません。
プッシュ通知
アプリユーザーへの即時的なメッセージ配信です。タイムリーな情報提供や、特定のアクションの促進に効果的です。
活用シーンとしては:
- セール情報の告知
- 放置ユーザーの呼び戻し
- 新機能のお知らせ
ただし、過度な配信はユーザーの離脱につながるため、配信頻度や内容の最適化が重要です。理想的には、ユーザーの行動に基づいたパーソナライズされた通知が効果的です。
BtoCとBtoBの重要な違いと共通点
1. 初期顧客獲得の特徴
最大の違い:営業活動の可能性
BtoBの大きな特徴は、アウトバウンドやリファラルといった変動費コストの低い営業施策が実施可能な点です。例えば、月額10万円のSaaSサービスであれば、テレアポや訪問営業などの人的コストをかけても採算が取れます。
対して、客単価が低いBtoCサービスでは、人的営業コストを回収することが難しく、広告やSEOといった非人的な施策が中心となります。
そのため、BtoBビジネスの方が初期の顧客獲得の予測が立てやすく、立ち上げフェーズでの事業計画が描きやすいという特徴があります。初期投資を抑えたローリスクでのスタートが可能なのです。
2. 顧客インサイトの重要性
BtoCでもBtoBでも、認知からリード獲得までを実現するには、ユーザーのインサイト(本質的なニーズ)を深く理解する必要があります。
インサイト理解のポイント
- 現状の課題は何か
- 現在どのような解決策を採用しているか
- 理想的な解決策はどのようなものか
- なぜその解決策に至っていないのか
3. 投資対効果の考え方
LTVとCPAの関係
LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を正確に把握し、それに基づいて適切なCPA(顧客獲得コスト)を設定することが重要です。
一般的に、LTV > CPA×3を目安とすることが多いです。この考え方をユニットエコノミクスといいます。つまり、顧客から得られる利益の3分の1までなら、獲得コストとして投資できるという考え方です。この比率は業界や成長フェーズによって変動しますが、サステナブルな事業運営のための一つの指標となります。
広告予算はLTVから逆算して設定するのが理想的です。
例:法人向けSaaSの場合
- 月額課金:10万円
- 平均契約期間:24ヶ月
- LTV = 240万円
- 適正CPA = 80万円以下
このように、BtoBではCPAの許容額が大きいため、人的コストを含めた多様な獲得策が実行可能となります。
4. 長期的な視点の重要性
変動費のかかるフロー施策(広告など)は、短期的な効果は期待できますが、持続的な成長には以下の要素も重要です:
ストック施策の例
- SEO対策
- コンテンツマーケティング
- ソーシャルメディア運用
- メディア構築
これらは初期投資が必要ですが、効果が蓄積されていくため、長期的なROI(投資対効果)は高くなります。特に地方企業においては、広告費用の制約がある場合も多いため、これらのストック施策の重要性は高いと言えるでしょう。
PR/ブランディングの重要性
- 認知度向上
- 信頼性の構築
- 業界でのポジショニング確立
- 採用への好影響
特にBtoB領域では、ブランド力が直接的な営業活動の効率にも影響します。「知っている会社」の営業担当からの連絡は、未知の企業からの連絡に比べて、対応されやすい傾向にあります。
実践のためのステップ
ここまでの内容を踏まえ、実践のためのステップをご紹介します。
1. 現状分析
まずは現状を正確に把握することが重要です。
- 顧客インサイトの深堀り(インタビューや行動分析を通じて)
- 競合状況の把握(差別化ポイントの明確化)
- 自社リソースの確認(予算、人員、スキルなど)
特に重要なのは、「なぜ顧客が自社を選ぶのか」という点です。これが明確になっていないと、効果的なマーケティングメッセージを構築できません。
2. KGI/KPIの設定
数値目標を明確に設定することで、施策の効果測定が可能になります。
- LTVの算出(平均客単価×購入頻度×継続期間)
- 適正CPAの設定(一般的にはLTVの3分の1以下)
- 必要顧客数の算出(売上目標÷客単価)
これらの数値を基に、各施策の予算配分や優先順位を決定していきます。
3. 施策の優先順位付け
限られたリソースを効果的に活用するため、施策に優先順位をつけます。
- 即効性の高い施策(短期的な成果が必要な場合)
- 中長期的に効果の出る施策(持続的な成長のため)
- リソース配分の検討(予算、人員、時間の最適配分)
初期段階では、小規模な投資でテスト可能な施策から始め、効果が確認できたものを拡大していくアプローチが効果的です。
4. 実行とPDCA
計画を実行し、結果を分析して改善するサイクルを回します。
- 小規模での検証(リスクを最小化)
- データに基づく改善(感覚ではなく数値で判断)
- 成功施策の横展開(効果が確認できた施策の拡大)
特に重要なのは、失敗を恐れずに小さく始め、データを収集しながら改善していく姿勢です。完璧な計画を立てようとするよりも、実行と改善のサイクルを回すことが成功への近道となります。
まとめ
マーケティング施策の選択は、事業フェーズや目標、リソースによって大きく異なります。重要なのは、自社の状況に合わせて適切な施策を選択し、顧客インサイトに基づいた展開を行うことです。
特に初期段階では、BtoBならアウトバウンドやリファラル、BtoCなら小規模な広告テストなど、検証可能な範囲から始めることをお勧めします。
その上で、中長期的な成長を見据えたストック施策やブランディングにも、早い段階から着手することが重要です。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。