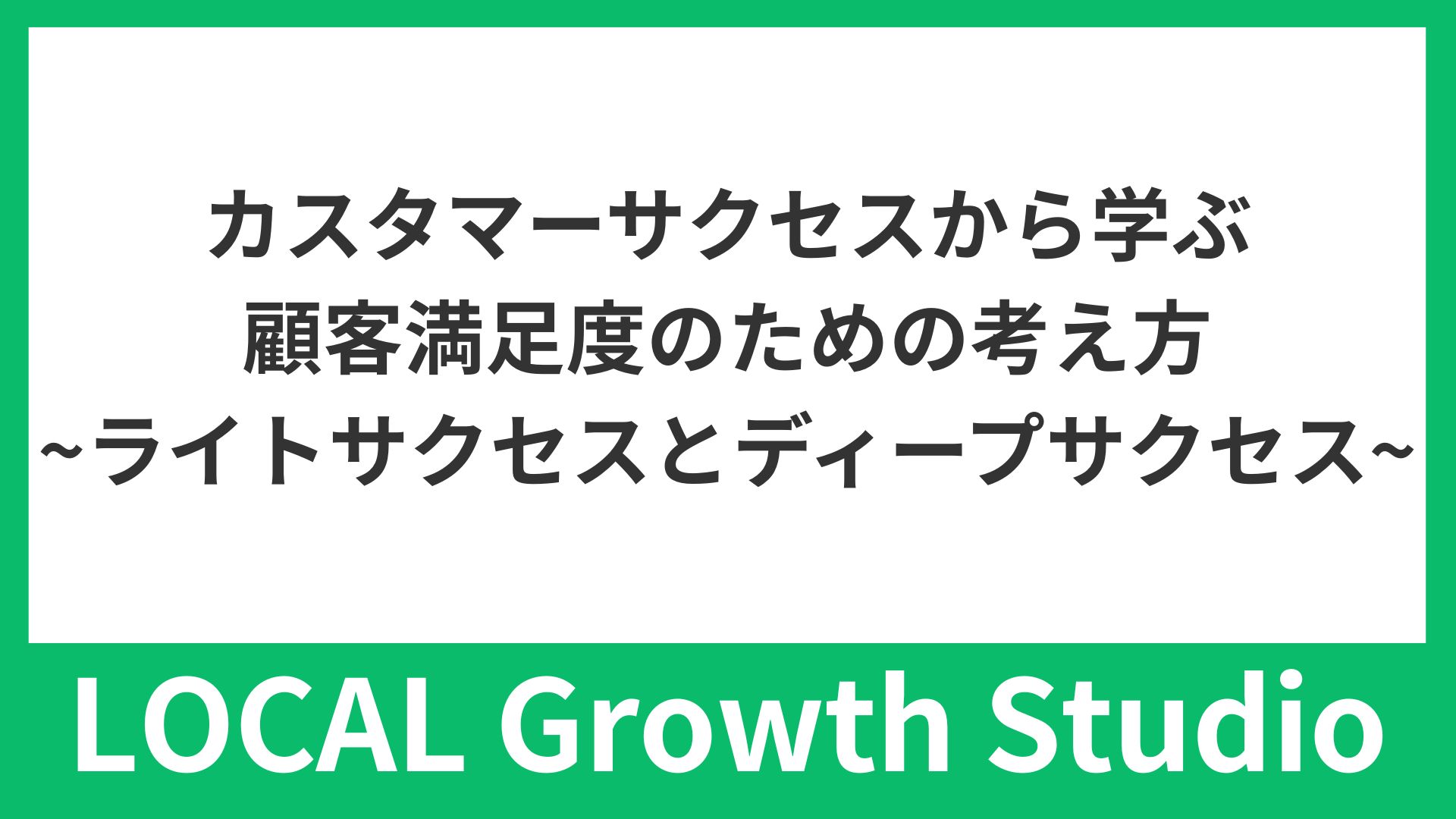ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
この記事は、「カスタマーサクセスから学ぶ顧客満足度のための考え方:ライトサクセスとディープサクセス」について記載しています。
カスタマーサクセスという職種の誕生
近年、BtoB企業を中心に「カスタマーサクセス」という職種が急速に広がっています。この職種は、SaaS企業やザモデル(The Model)と呼ばれる営業組織の中で生まれた、比較的新しいポジションです。
ザモデルとは、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスという4つの機能に営業プロセスを分業化した組織モデルのことです。従来の営業担当者が一人で全てのプロセスを担当していたのに対し、各プロセスを専門化することで、効率的な顧客獲得と維持を実現しています。
この組織モデルの中で、カスタマーサクセスは「既存顧客の成功を支援し、長期的な関係を築く」という重要な役割を担っています。特にSaaSビジネスでは、初期の契約だけでなく、継続的な契約更新(リテンション)こそが事業の成長を左右するため、カスタマーサクセスの重要性が高まっているのです。
カスタマーサポートとの違い
カスタマーサクセスと聞いて、「カスタマーサポートと何が違うのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。同じ頭文字の「CS」を取る職種ですが、その役割には明確な違いがあります。
カスタマーサポートの役割
カスタマーサポートは、主にBtoC事業において、顧客からの問い合わせに対応する職種です。具体的には、以下のような業務を担当します。
- 商品の使い方に関する質問への回答
- トラブルや不具合が発生した際の対応
- 返品や交換の手続きサポート
- クレーム対応
カスタマーサポートの基本的な姿勢は「受け身」です。顧客から問い合わせが来たときに、迅速かつ丁寧に対応することが求められます。評価指標も、対応時間の短さ、解決率、顧客満足度(問い合わせ対応に対する評価)などが中心になります。
カスタマーサクセスの役割
一方、カスタマーサクセスは、より能動的なアプローチを取ります。主にBtoB企業で用いられることが多く、以下のような役割を担います。
- 既存顧客のサービス活用度合いの向上
- 契約更新(リテンション)の実現
- アップセル(上位プランへの移行提案)
- クロスセル(別商材の提案)
カスタマーサクセスは、顧客からの問い合わせを待つのではなく、自ら顧客に働きかけます。「顧客がサービスを通じて成功する」ことを目指し、そのために必要な支援を先回りして提供するのです。
例えば、顧客のサービス利用状況をモニタリングし、「最近ログイン頻度が下がっている」と気づいたら、自らコンタクトを取って課題をヒアリングし、活用方法を提案します。問題が顕在化する前に、能動的に介入することで、顧客の満足度を高め、契約継続につなげるのです。
カスタマーサクセスの役割と求められる能力
カスタマーサクセスは、カスタマーサポートと比べて、より高度なスキルが求められます。
求められる能力
営業力 新規契約を獲得する営業とは異なりますが、既存顧客に対してアップセルやクロスセルを提案する場面では、営業的なコミュニケーション能力が必要です。顧客の予算感や意思決定プロセスを理解し、適切なタイミングで提案を行う力が求められます。
課題理解力 顧客が抱えている課題を正確に把握し、その課題がどのようにビジネスに影響しているかを理解する必要があります。表面的な要望だけでなく、その背景にある本質的な課題を見抜く力が重要です。
コンサルティング能力 顧客の課題を理解した上で、サービスをどう活用すれば理想状態に導けるかを提案する力が求められます。単なる操作方法の説明ではなく、顧客のビジネス成果につながる活用方法を設計し、伴走する必要があります。
例えば、マーケティングオートメーションツール(MA)を提供している企業のカスタマーサクセスであれば、以下のような支援を行います。
- 顧客企業のマーケティング課題をヒアリング(リード獲得数が少ない、商談化率が低いなど)
- 課題解決のために、MAツールをどう活用すべきかの戦略を提案
- 具体的な設定やシナリオ設計をサポート
- 運用開始後の効果測定と改善提案
このように、ツールの使い方を教えるだけでなく、顧客のビジネス成果に責任を持つ姿勢が、カスタマーサクセスには求められるのです。
カスタマーサクセスの評価指標と先行指標
カスタマーサクセスの仕事は、担当顧客の契約更新をもって評価されることが多いです。しかし、契約更新のタイミングはSaaSでは1年後というケースも多く、活動の成果を見定める期間が長いプロジェクトになります。
そのため、契約更新という最終的な成果指標だけでなく、先行指標を設定してマネジメントを行うことが重要です。
プロダクト活用指標
サービスがしっかり活用されているかどうかを測る指標です。具体的には以下のような指標があります。
- ログイン頻度:期間中に顧客が何回ログインしたか
- 主要機能の利用回数:契約更新に影響する重要な機能を何回操作したか
- アクティブユーザー数:契約企業内で実際にサービスを使っている人数
- データ登録量:顧客がシステムに登録したデータの量(例:顧客情報、商品情報など)
これらの指標が高ければ、サービスが日常業務に組み込まれており、契約継続の可能性が高いと判断できます。逆に、これらの指標が低下してきたら、顧客が離れていくサイン(チャーンのシグナル)として捉え、早めに介入する必要があります。
オンボーディング期間の満足度
オンボーディングとは、サービス導入当初の期間(一般的には最初の3ヶ月程度)に、顧客がサービスを使いこなせるようになるまでの支援プロセスです。
この期間に研修プログラムを実施し、以下のような指標で満足度を測ります。
- 満足度スコア:10点満点で顧客に評価してもらう
- 理解度テスト:研修内容がどの程度理解できたかを確認する
- 初期目標の達成率:オンボーディング期間中に設定した小さな目標(例:初回キャンペーンの配信)が達成できたか
オンボーディング期間での満足度が高い顧客は、その後の契約継続率も高い傾向があります。最初の3ヶ月で「このサービスは使える」と実感してもらうことが、長期的な関係構築の鍵となるのです。
ライトサクセスとディープサクセス:2つの顧客満足度
カスタマーサクセスの活動の中でも、特に注目されるべき考え方が「ライトサクセス」と「ディープサクセス」です。この2つの概念を理解することで、より本質的な顧客満足を実現できます。
ライトサクセス:現場担当者の満足度
ライトサクセスとは、サービスを実際に利用する現場担当者(エンドユーザー)の満足度を指します。
現場担当者が重視するポイントは、以下のような点です。
- 使い方が理解できているか:操作が複雑すぎず、迷わず使えるか
- 業務のスピードが上がったか:以前よりも短時間で作業が完了するか
- 業務の質が向上したか:ミスが減った、より良いアウトプットが出せるようになったか
- 手間が減ったか:手作業が自動化され、負担が軽減されたか
例えば、経理業務効率化システムを導入した企業の経理担当者が、「以前は手作業で3時間かかっていた月次決算が、30分で終わるようになった」「計算ミスがなくなって安心して仕事ができる」と感じていれば、ライトサクセスは達成されています。
一般的なカスタマーサクセスの活動は、このライトサクセスで止まっているケースが多いです。現場担当者が満足していれば、サービスは継続的に使われ、契約も更新されるだろうと考えるからです。
ディープサクセス:経営者/決裁者の満足度
しかし、より発展的な企業では、ライトサクセスだけでなく「ディープサクセス」を目指しています。ディープサクセスとは、経営者や決裁者の満足度を指します。
仮に現場担当者の業務が楽になったり、スピードが上がったとしても、それが会社全体の売上やコストにどれだけ影響をもたらしているかが、経営者や決裁者の重視しているポイントです。
経営者や決裁者が判断する際の観点は、以下のようなものです。
- 投資対効果(ROI):サービス導入にかかるコストに対して、どれだけのリターンが得られているか
- 売上への貢献:サービスを活用することで、売上が増加したか
- コスト削減効果:人件費や外注費などのコストがどれだけ削減されたか
- 戦略的価値:単なる業務効率化だけでなく、競合優位性や新しいビジネス機会の創出につながっているか
例えば、先ほどの経理システムの例で考えてみましょう。
ライトサクセスの視点(経理担当者) 「月次決算が3時間から30分になって、すごく楽になった!」
ディープサクセスの視点(経営者) 「経理担当者の作業時間が削減され、年間で約240時間(月20時間×12ヶ月)の工数削減になった。時給2,000円とすると、年間48万円のコスト削減効果がある。システムの年間利用料が36万円なので、差し引き12万円のプラスになっている。さらに、月次決算が早く完了することで、経営判断のスピードが上がり、経営の質も向上した。」
このように、ディープサクセスでは、現場の満足だけでなく、経営視点での価値を定量的に示すことが重要です。
なぜディープサクセスが重要なのか
BtoBサービスの契約更新を決定するのは、多くの場合、経営者や決裁者です。現場担当者がどんなに満足していても、経営者が「費用対効果が見合わない」と判断すれば、契約は打ち切られてしまいます。
特に、以下のような状況では、ディープサクセスの重要性が高まります。
- 予算削減の局面で、優先順位の低いサービスから削られる
- より安価な競合サービスが登場し、乗り換えを検討される
- 経営者が交代し、既存契約の見直しが行われる
こうした状況でも契約を継続してもらうためには、経営者や決裁者に対して、サービスの価値を明確に示し、納得してもらう必要があります。それがディープサクセスの実現です。
ディープサクセスを実現するための実践
では、ディープサクセスを実現するためには、具体的にどのような活動を行えば良いのでしょうか。
経営者/決裁者とのコミュニケーション接点を設ける
ディープサクセスを目指すためには、現場担当者だけでなく、経営者や決裁者とも直接コミュニケーションを取ることが重要です。具体的には、以下のタイミングで経営者や決裁者への報告機会を設けます。
1. 導入時(キックオフミーティング) サービス導入の目的や期待する成果を、経営者や決裁者から直接ヒアリングします。このタイミングで、「何を実現すれば成功と言えるのか」を明確にすることが、その後の活動の指針になります。
例えば、以下のような質問を投げかけます。
- 「このサービスを導入することで、どのような経営課題を解決したいとお考えですか?」
- 「1年後、どのような成果が出ていれば、投資して良かったと感じていただけますか?」
2. オンボーディング終了時(3ヶ月後) 導入から3ヶ月が経過し、現場でのサービス活用が軌道に乗った段階で、初期の成果を報告します。
報告内容の例:
- 導入前と比較した業務時間の削減量
- サービス活用によって改善された指標(例:リード獲得数、商談化率など)
- 現場担当者からのフィードバック
- 今後さらに活用を進めるための提案
3. 契約中間折り返し地点(6ヶ月後) 契約期間の半分が経過した時点で、中間報告を行います。順調に成果が出ているかを確認し、必要に応じて軌道修正を行います。
報告内容の例:
- 半年間の累積効果(コスト削減額、売上貢献など)
- 投資対効果(ROI)の試算
- 後半6ヶ月で取り組むべき施策の提案
4. 契約更新前(2〜3ヶ月前) 契約更新の2〜3ヶ月前に、1年間の総括報告を行います。ここでは、定量的な成果を中心に、サービスがもたらした価値を明確に示します。
報告内容の例:
- 1年間の総合的な成果(売上への貢献、コスト削減効果など)
- 投資対効果(ROI)の実績
- 次年度に向けた提案(上位プランへのアップグレード、追加機能の活用など)
報告資料の作成とフォローアップ
理想的なのは、経営者や決裁者に直接ミーティングに参加していただき、対面で報告することです。しかし、多忙な経営者の時間を確保するのは容易ではありません。
もしミーティングへの参加が難しい場合でも、以下のような方法でディープサクセスを目指すことができます。
報告資料の作成と共有 成果をまとめた資料を作成し、現場担当者を通じて経営者や決裁者に共有してもらいます。資料には、以下の内容を盛り込みます。
- エグゼクティブサマリー(1ページで要点をまとめる)
- 定量的な成果(数値とグラフで視覚的に示す)
- 具体的な成功事例(どのような場面でサービスが役立ったか)
- 次のステップの提案
現場担当者へのフォローアップ 資料を共有した後、現場担当者に「経営者や決裁者からの感想や評価をお聞かせいただけますか?」とフォローアップします。これにより、経営層がどのように受け止めているかを把握し、次回の報告に活かすことができます。
恐怖心を乗り越える
経営者や決裁者に直接報告することは、カスタマーサクセス担当者にとって、時に恐怖心や負荷を感じる行為です。なぜなら、以下のようなリスクがあるからです。
- 期待していたほどの成果が出ていないと指摘される
- より高い要望や追加の要求を受ける
- 厳しい質問や批判を受ける可能性がある
しかし、本質的なサービスを通じた顧客の成功と、サービスの継続収益を実現させるためには、こうしたコミュニケーションから逃げてはいけません。
むしろ、定期的に経営者や決裁者とコミュニケーションを取ることで、以下のようなメリットがあります。
- 早期に不満や課題を発見し、対処できる
- 経営者の期待値を正しく理解し、活動の方向性を調整できる
- 信頼関係が構築され、契約更新時の交渉がスムーズになる
重要なのは、タイミングを決めて、計画的にコミュニケーションの機会を持つことです。契約更新の直前になって初めて報告するのではなく、定期的な接点を持つことで、経営者や決裁者との信頼関係を築いていくのです。
地方企業のBtoBサービスへの応用
ここまで、カスタマーサクセスの文脈でライトサクセスとディープサクセスについて解説してきました。しかし、この考え方は、SaaS企業やザモデルを採用している企業だけのものではありません。地方企業のBtoBサービスにおいても、非常に有効な考え方です。
地方企業のBtoBサービスの現状
地方企業がBtoBサービスを提供する際、多くの場合、現場担当者とのやり取りが中心になります。例えば、以下のようなケースです。
- Webサイト制作会社が、クライアント企業のWeb担当者とやり取りする
- 研修事業者が、クライアント企業の人事担当者と研修内容を詰める
- システム開発会社が、クライアント企業の情報システム部門と要件定義を行う
これらのやり取りの中で、現場担当者が満足していれば、次回も発注してもらえると考えがちです。しかし、実際には以下のような理由で契約が打ち切られるケースがあります。
- 予算削減のため、外注費を見直すことになった
- 経営者が「費用対効果が見えない」と判断した
- より安価な競合に乗り換えることになった
このような事態を避けるためには、現場担当者の満足(ライトサクセス)だけでなく、経営者や決裁者の満足(ディープサクセス)を意識したサービス提供が必要です。
具体的な実践例
地方企業がディープサクセスを目指すための具体的な実践例を紹介します。
例1:Webマーケティング支援会社のケース
従来のアプローチ(ライトサクセス志向):
- クライアント企業のWeb担当者に、月次で広告運用レポートを提出
- クリック数、表示回数、コンバージョン数などの指標を報告
- Web担当者から「数字が改善して良かった」という評価を得る
ディープサクセスを目指すアプローチ:
- 四半期ごとに、経営者向けの報告資料を作成
- 広告経由で獲得したリードが、最終的にどれだけの売上に貢献したかを試算
- 広告費に対する売上のROIを明示(例:広告費100万円に対して、売上300万円を創出)
- 経営者に対して、次四半期の戦略提案を行う
例2:人材育成・研修事業者のケース
従来のアプローチ(ライトサクセス志向):
- 研修実施後、受講者アンケートで満足度を測定
- 人事担当者に「満足度90%でした」と報告
- 人事担当者から「良い研修でした」という評価を得る
ディープサクセスを目指すアプローチ:
- 研修実施3ヶ月後に、受講者の行動変容を測定(例:営業担当者の商談数や受注率の変化)
- 研修による生産性向上や売上増加を定量化
- 経営者に対して、「研修投資額〇〇万円に対して、年間△△万円の売上増加効果がありました」と報告
- 次年度の研修計画を経営者に直接プレゼンテーション
例3:業務システム開発会社のケース
従来のアプローチ(ライトサクセス志向):
- システム納品後、現場担当者に使い方をレクチャー
- 「使いやすいシステムを作ってもらった」という評価を得る
- 保守契約を継続してもらう
ディープサクセスを目指すアプローチ:
- システム稼働後、業務時間の削減効果を測定
- 人件費削減額や、削減された時間で取り組めるようになった新規業務の価値を試算
- 経営者に対して、「システム投資額〇〇万円に対して、年間△△万円のコスト削減効果があります」と報告
- システムの追加機能開発や、他部門への展開を経営者に提案
地方企業がディープサクセスを目指すためのポイント
地方企業がディープサクセスを実現するためには、以下のポイントを意識することが重要です。
1. 経営者とのコミュニケーション機会を積極的に設ける 現場担当者だけでなく、経営者にも定期的に報告の機会を持つことを提案しましょう。「四半期に一度、経営者様にも成果をご報告させていただきたいのですが」と、こちらから働きかけることが大切です。
2. 定量的な成果を示す 「満足度が高かった」「好評だった」といった定性的な評価だけでなく、売上への貢献やコスト削減効果を数値で示すことが重要です。完璧な数値でなくても、試算や推定値を示すことで、経営者は判断しやすくなります。
3. 投資対効果(ROI)を意識する 経営者が最も気にするのは、「投資に見合うリターンがあるか」です。サービス提供にかかるコストと、それによって得られる効果を比較し、投資対効果を明示しましょう。
4. 継続的な価値提案を行う 一度の報告で終わらせるのではなく、継続的に新しい価値提案を行うことが重要です。「次はこんな取り組みをすれば、さらに成果が上がります」という提案を続けることで、長期的な関係を築くことができます。
まとめ:真の顧客満足とは何か
カスタマーサクセスの世界で生まれた「ライトサクセス」と「ディープサクセス」という考え方は、BtoB事業において非常に重要な示唆を与えてくれます。
**ライトサクセス(現場担当者の満足度)**は、サービスが日常的に使われ、現場に受け入れられるための第一歩です。現場担当者が満足していなければ、サービスは活用されず、成果も出ません。
しかし、それだけでは不十分です。**ディープサクセス(経営者/決裁者の満足度)**を実現して初めて、サービスの継続的な契約や、さらなる投資の拡大につながります。
特に地方企業のBtoBサービスにおいては、現場担当者の満足だけに安心せず、経営者や決裁者に対して、サービスの価値を定量的に示し、納得してもらうプロセスが重要です。
そのためには、以下の実践が必要です。
- 導入時、オンボーディング終了時、契約中間地点、契約更新前など、定期的なタイミングで経営者や決裁者への報告機会を設ける
- 報告内容は、定量的な成果(売上貢献、コスト削減)を中心に、投資対効果を明示する
- ミーティングへの参加が難しい場合でも、資料を通じて情報を共有し、フィードバックを得る
- 経営者や決裁者とのコミュニケーションを恐れず、タイミングを決めて計画的に実施する
真の顧客満足とは、現場担当者と経営者や決裁者の両方が満足している状態です。ライトサクセスとディープサクセスの両方を実現することで、長期的な顧客関係を築き、事業の成長につなげることができます。
地方企業の皆さんも、この考え方を自社のBtoBサービスに取り入れ、より深い顧客満足を目指してみてください。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。