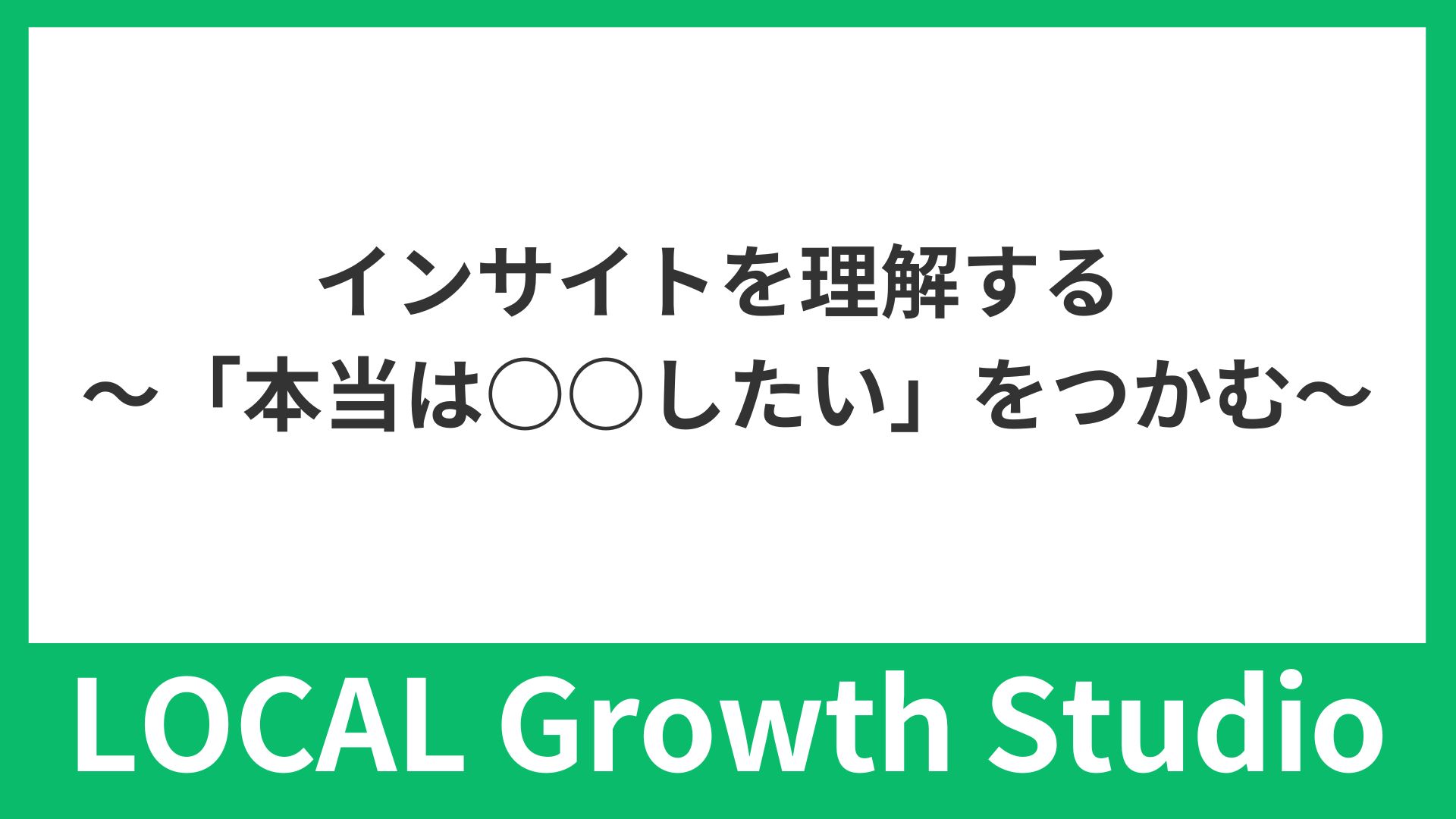ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
この記事は、「インサイトを理解する ~「本当は○○したい」をつかむ〜」について記載しています。
なぜインサイトが重要なのか
インサイトとは、心の中でユーザーが考えていることを指します。表面的な「何がほしい」というニーズではなく、「本当は○○したいけど、良い選択肢がないから△△で妥協している」という、深層的な願望のことです。
例えば、「安い商品が欲しい」という声の背後には、「品質を犠牲にせず、賢く買い物をしている自分でありたい」という本音があるかもしれません。あるいは「使いやすい製品が欲しい」という声の裏には、「実は新しい技術を使いこなせる自分に自信がない」という不安が隠れているかもしれないのです。
このインサイトを理解できているかどうかが、商品開発やマーケティングの成否を分けるのです。
インサイトを理解するための基本構文
インサイトを理解するために、私たちは以下の構文を使います:
「ユーザーは〇〇という課題を今は△で解決しているが、本当は××の方がいい」
この構文は、シンプルながらも非常に強力なツールです。顧客の本音を構造化して理解するための枠組みを提供してくれます。
この構文の3つの要素を詳しく見ていきましょう:
1. 〇〇(課題)
- 具体的な困りごと
- 日常的な不便
- 解決したい問題
- 達成したい目標
これは顧客が「何をしたいのか」という目的や課題です。例えば「子どもの食育」「デザインの外注」「効率的な経理処理」といった具体的な課題です。ここでのポイントは、具体的であることと、顧客自身が認識している課題であることです。
2. △(現状の解決方法)
- 今の対処法
- 妥協している部分
- 我慢している点
- 不満を感じている方法
現在、その課題をどのように解決しているかという点です。これは現状のマーケットの状態を表しています。例えば「栄養素を考えた手作り」「フリーランスのデザイナーに依頼」「毎週金曜に残業して処理」といった具体的な現状の対処法です。
3. ××(理想の解決方法)
- こうなったら嬉しい状態
- 本当はこうしたい方法
- より良い解決策
- 満足できる状態
これが本当の「インサイト」の部分です。現状の解決法に対して、「本当はこうありたい」という理想の状態を指します。例えば「栄養バランスを気にせず子どもが喜ぶ食事を提供したい」「デザインの質を確保しつつ迅速に納品してほしい」「面倒な入力作業から解放されたい」といった本音の部分です。
この3つの要素を明確にすることで、顧客の深層心理を構造化して理解することができるのです。
成功サービスに見るインサイトの実例
この構文を使って、実際の成功サービスを分析してみましょう。有名なサービスが、どのようなインサイトを捉えて成功したのかを見ることで、インサイト理解の重要性がより明確になります。
1. タイミー(短時間バイトアプリ)
「ユーザーは【すぐにお金を稼ぎたい】という課題を今は【面倒な面接や固定シフトのバイト】で解決しているが、本当は【都合の良い時間だけ自由に働ける】方がいい」
タイミーは、この深い理解に基づいて、面接なしですぐに働けるという画期的なサービスを生み出したのです。従来のバイト探しでは、応募から採用、研修までのプロセスが1〜2週間かかるのが当たり前でした。しかし「今週中に現金が必要」という切実なニーズに応えたのがタイミーの成功要因の一つといえるでしょう。
2. Uber Eats
注文する側: 「ユーザーは【食事の準備】という課題を今は【自分で買いに行くか、限られた店の出前】で解決しているが、本当は【どんな店のものでも手間なく届けてもらえる】方がいい」
配達する側: 「ユーザーは【収入を得たい】という課題を今は【固定的な仕事】で解決しているが、本当は【誰にも管理されず好きな時間に働ける】方がいい」
Uber Eatsの革新性は、消費者と配達パートナーの双方のインサイトを同時に捉えたプラットフォームモデルにあります。特に配達する側のインサイトは、「副業したいけど時間的な縛りがネック」という働き方に関する本質的な願望を捉えていました。
3. スターバックス
「ユーザーは【くつろげる場所がほしい】という課題を今は【騒がしいお店で時間を潰す】で解決しているが、本当は【自分の居場所として使える空間】方がいい」
スターバックスが提供したのは、単なるコーヒーショップではなく、「サードプレイス」という新しい価値でした。人々は実はコーヒーそのものではなく、家庭でも職場でもない「第三の場所」を求めていたのです。このインサイト理解があったからこそ、店内の雰囲気づくりやゆったりとした滞在を許容するサービス設計が生まれました。
4. iPod・ウォークマン
「ユーザーは【音楽を楽しみたい】という課題を今は【家の中でしか聴けない/大きなCDプレーヤーでしか聴けない】で解決しているが、本当は【どこでも自分だけの音楽空間を持てる】方がいい」
ウォークマンやiPodの革新性は、音楽を「場所」から解放したことにあります。特にiPodは「1000曲をポケットに」というキャッチフレーズで、この深いインサイトを端的に表現していました。
5. ネット証券
「ユーザーは【株式投資をしたい】という課題を今は【証券会社の営業マンと付き合う】で解決しているが、本当は【自分で情報を集めて判断して取引したい】」
ネット証券の登場は、「本当は自分で判断したいのに、証券会社の勧める商品に合わせなければならない」というストレスを解消しました。このインサイト理解が、低コストで自由度の高いサービス設計につながったのです。
インサイトを見つけるための実践的アプローチ
では、実際にどうやってインサイトを見つけていけばよいのでしょうか。理論的な理解だけでなく、現場で活用できる具体的な方法をご紹介します。
1. 顧客との深い対話
単なるアンケートやヒアリングではなく、より深い対話が必要です。
- 「なぜ」を5回繰り返す 最初の回答に対して「なぜですか?」と掘り下げ、さらにその回答に対しても「なぜ?」と問い続けることで、表層的な答えから本質的な動機まで到達する手法です。例えば、「なぜこの商品を選びましたか?」→「使いやすそうだったから」→「なぜ使いやすさを重視するのですか?」→「失敗したくないから」→「なぜ失敗が気になるのですか?」というように掘り下げていきます。
- 具体的なエピソードを聞く 「この商品をどんな場面で使いましたか?」「最初に使った時のことを教えてください」など、具体的な体験談を聞くことで、本人も気づいていない本質的なニーズが見えてくることがあります。
- 不満や困りごとの本質を探る 「この商品・サービスのどんな点を改善してほしいですか?」という直接的な質問だけでなく、「使っていて不便だと感じた瞬間はありますか?」「こうだったらもっと良かったのにと思ったことは?」など、日常の小さなフラストレーションから本質を探ります。
- 理想の状態を具体的に描いてもらう 「もし魔法が使えて、この課題を完璧に解決できるとしたら、どんな状態になっていますか?」といった質問で、現実的な制約を取り払った理想の状態を描いてもらいます。
2. データの深掘り
対話だけでなく、既存のデータからもインサイトの手がかりを得ることができます。
- よく売れる商品・サービスの共通点 ベストセラー商品や高リピート率のサービスには、何らかの共通点があるはずです。それは価格帯かもしれませんし、デザインの特徴かもしれません。あるいは購入プロセスの簡便さかもしれません。これらの共通点から、顧客が本当に価値を感じている要素が見えてきます。
- クレームや問い合わせの裏にある本質 クレームは貴重な情報源です。「配送が遅い」というクレームの裏には、「特定の日までに確実に届けたい」という切実なニーズがあるかもしれません。問い合わせ内容を分類し、頻出するテーマから本質的な課題を探ります。
- 予想外の使われ方や活用方法 想定していなかった使い方をしている顧客がいれば、そこにはニーズのギャップがあります。例えば、食品保存容器が化粧品入れとして使われているとしたら、化粧品収納に関する未充足のニーズがあるかもしれません。
- リピーターの特徴分析 一度きりの顧客と定期的に購入する顧客の違いは何か?属性の違いだけでなく、利用シーンや購入動機の違いを分析することで、より深いインサイトが見えてきます。
3. 競合との比較
市場におけるポジショニングからもインサイトの手がかりを得られます。
- なぜ自社を選んでくれたのか 「他社ではなく、なぜ当社を選びましたか?」という質問は、自社の強みだけでなく、競合が満たせていないニーズを明らかにする重要な問いです。
- 競合のどこに不満を感じているのか 競合サービスからの乗り換え顧客に、「以前使っていたサービスのどんな点に不満がありましたか?」と聞くことで、業界全体の盲点が見えてくることがあります。
- 業界全体で見落としている点はないか 業界の常識や当たり前を疑うことも重要です。「なぜこの業界ではこのやり方が当たり前なのか?」「顧客はこの慣習に本当に満足しているのか?」という視点で見直すことで、革新的なアイデアが生まれることがあります。
地方企業での実践方法
インサイト発見のアプローチをご紹介します。都市部の企業に比べてリソースが限られていることが多い地方企業ですが、その分、顧客との距離の近さという大きな強みがあります。
1. 顧客との距離の近さを活かす
- 日常的な会話の中での気づきを記録 地方企業の強みは、顧客と日常的に接する機会が多いことです。雑談の中から出てくる何気ない不満や要望を見逃さず、記録する習慣をつけましょう。例えば、店頭での何気ない会話や、納品時のちょっとした意見などが貴重な情報源になります。
- 従業員からの情報収集 現場で顧客と接している従業員は、多くの生の声を聞いています。週に一度、「お客様から聞いた声」を共有する時間を設けるなど、組織的に情報を集める仕組みを作りましょう。
- お客様の生の声を集める仕組み作り 小規模な「お客様座談会」や「ユーザーミーティング」を開催することで、より深い対話の機会を作ることができます。少人数で和やかな雰囲気の中での対話は、アンケートでは得られない本音を引き出すことができます。
2. 地域特性の理解
- 地域特有の課題の把握 都市部とは異なる地域固有の課題があるはずです。例えば、公共交通機関の利便性、気候条件、地域産業の特性など、地域ならではの背景を理解することで、より深いインサイトにつながります。
- 都市部とは異なるニーズの発見 「都市部で流行っているから」という理由だけでサービスを展開するのではなく、地域特有のニーズに目を向けることが重要です。例えば、同じECサービスでも、地方では配送時間や対応可能エリアに関する不安が大きいかもしれません。
- 地域文化や習慣との関連性 地域の行事や習慣、価値観は、購買行動に大きな影響を与えます。例えば、特定の季節行事に関連した需要や、地域コミュニティでの評判の重要性など、地域文化を理解することでより効果的なアプローチが可能になります。
3. 段階的な実践
- まずは売上TOP3商品から分析 すべての商品・サービスを一度に分析するのではなく、まずは売上や利益に貢献している主力商品から分析を始めましょう。成功している理由を深く理解することで、他の商品にも応用できるインサイトが得られます。
- 優良顧客5社へのヒアリング すべての顧客にヒアリングするのは現実的ではありません。まずは特に関係性の深い優良顧客5社程度を選び、深いヒアリングを行いましょう。顧客も自社の成長を応援してくれるパートナーと考えれば、協力してくれるはずです。
- 短期的な改善と中長期的な開発 インサイトから得られた気づきを、すぐに実行できる「短期的な改善策」と、時間をかけて取り組む「中長期的な開発テーマ」に分けることで、着実に成果につなげることができます。
よくある失敗とその対策
インサイト発見のプロセスでは、いくつかの落とし穴があります。よくある失敗パターンとその対策を見ていきましょう。
1. 表面的なニーズだけを聞いてしまう
- 失敗例:「何が欲しいですか?」といった直接的な質問だけを行い、その回答をそのまま受け止めてしまう。
- 対策:「なぜそれが必要なのですか?」「それによって何を実現したいですか?」と、さらに掘り下げる質問を重ねる。
例えば、「使いやすいアプリが欲しい」という声に対して、単に操作性の改善だけを考えるのではなく、「なぜ使いやすさが重要なのですか?」と掘り下げることで、「実は新しい技術に対する不安がある」という本質的な課題が見えてくることがあります。
2. 自社の常識に縛られる
- 失敗例:「それは業界の常識的に無理です」「そんなやり方は前例がない」と、自社の枠組みの中でしか考えられない。
- 対策:「どうすれば実現できるか」という発想で、制約条件を一度取り払って考えてみる。
例えば、「即日納品してほしい」という要望に対して、「物理的に無理です」と断るのではなく、「在庫管理方法の見直し」「緊急時の特別配送ルートの確保」など、実現方法を模索する姿勢が重要です。
3. 性急な結論を出す
- 失敗例:一人の意見や、特定の現象だけで判断し、すぐに結論づけてしまう。
- 対策:複数の視点での検証を行い、パターンを見つけることを意識する。
例えば、「一人のお客様から『価格が高い』という意見があった」からといって、すぐに値下げを検討するのではなく、「どんな状況で高いと感じたのか」「他の顧客も同じように感じているのか」「価格以外の価値をどう感じているのか」といった多角的な検証が必要です。
4. インサイトと解決策を混同する
- 失敗例:「スマホアプリが欲しい」というのはインサイトではなく、解決策の一例に過ぎない。
- 対策:「なぜスマホアプリが必要なのか」という本質的なニーズに立ち返る。
スマホアプリという解決策の裏には、「いつでもどこでも情報にアクセスしたい」「手軽に操作したい」といった本質的なニーズがあります。このインサイトを理解すれば、アプリ以外の解決策も検討できるようになります。
まとめ:実践のためのステップ
ここまで見てきたインサイト理解の方法を、具体的なステップとしてまとめます。
1. まずは基本構文を使って整理
- 既存の成功商品について分析 まずは自社の成功している商品・サービスを基本構文(「ユーザーは〇〇という課題を今は△で解決しているが、本当は××の方がいい」)で整理してみましょう。なぜ選ばれているのかの本質が見えてきます。
- 顧客の声を構文に当てはめる 日々寄せられる顧客の声や要望を、この構文に当てはめて整理する習慣をつけましょう。単なる「要望リスト」ではなく、「インサイトベースの課題リスト」に変わります。
- チーム内で共有と議論 インサイト理解は、一人の担当者だけのものではなく、組織全体で共有されるべきものです。定期的にインサイトについて議論する場を設け、多様な視点からの解釈を促進しましょう。
2. 継続的な情報収集
- 定期的な顧客ヒアリング 一度きりではなく、定期的に顧客の声を聞く機会を設けましょう。顧客のニーズは時間とともに変化するため、継続的な対話が重要です。四半期に一度など、定期的なサイクルを設定するとよいでしょう。
- データの分析と活用 購買データ、利用データ、問い合わせ内容など、日々蓄積されるデータを定期的に分析し、パターンやトレンドを把握しましょう。定量データと定性データの両面からインサイトを探ります。
- 競合動向のチェック 競合の動きからも多くのヒントが得られます。競合が力を入れている分野は、何らかのインサイトに基づいているはずです。その背景にある顧客ニーズを考察してみましょう。
3. 施策への反映
- 商品開発への活用 発見したインサイトを、新商品開発や既存商品の改良に活かしましょう。「本当は××の方がいい」という部分に応える商品設計が、差別化につながります。
- マーケティング施策の立案 広告コピーやセールストークにも、インサイト理解を反映させましょう。「〇〇という課題を持つあなたに」というターゲティングと、「××を実現します」という本質的な価値提案が、効果的なメッセージとなります。
- サービス改善の方向性 顧客サービスやサポート体制も、インサイトに基づいて改善していきましょう。表面的な要望に応えるだけでなく、本質的なニーズを満たすサービス設計が差別化につながります。
インサイトの発見は、一朝一夕にはいきません。しかし、この基本構文を意識しながら、日々の顧客との対話を重ねることで、必ず新しい気づきが得られるはずです。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。