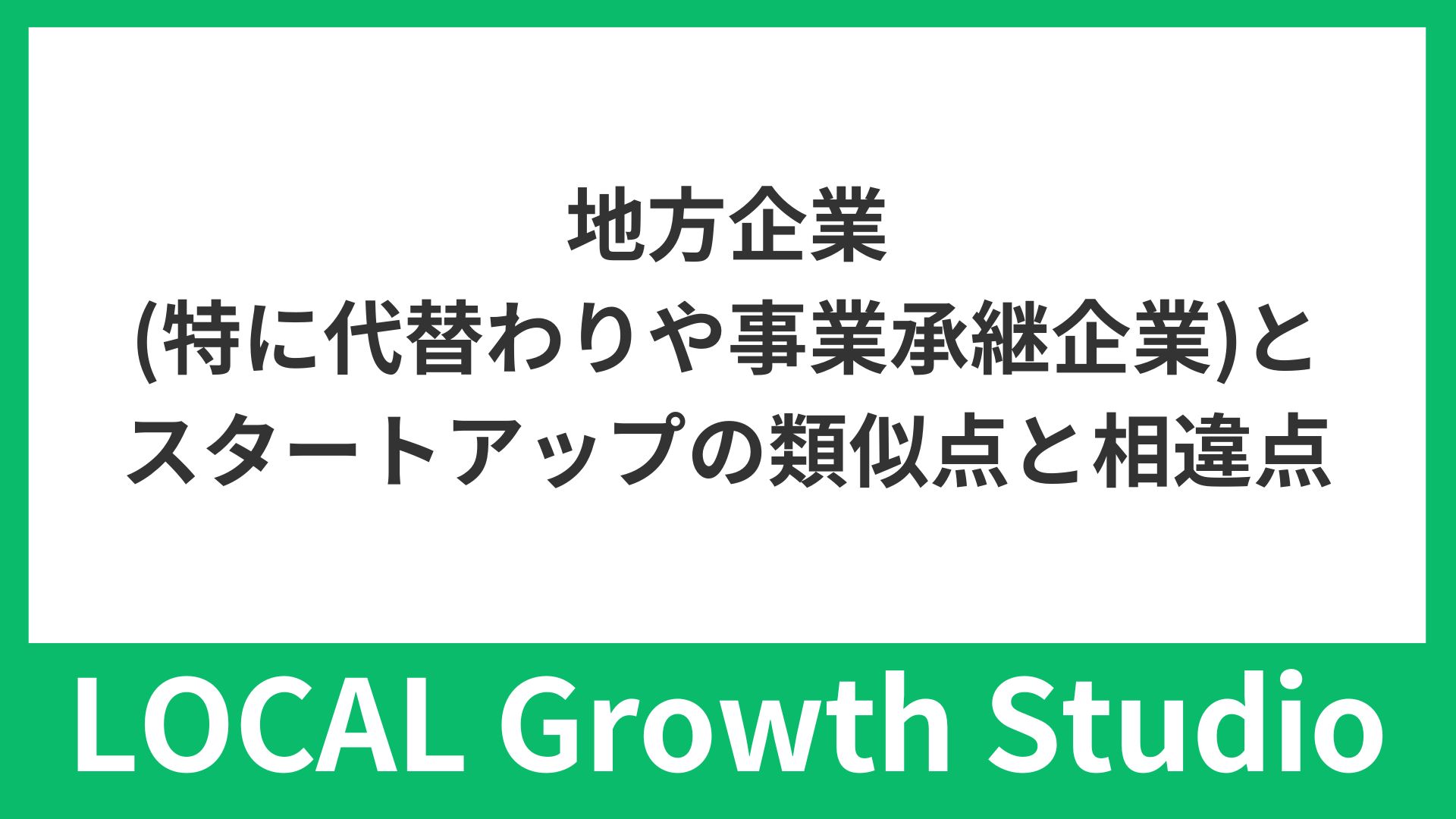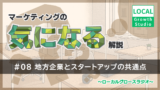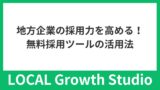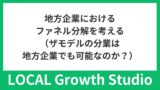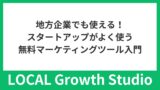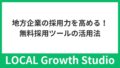ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
この記事は、「地方企業(特に代替わりや事業承継企業)と、スタートアップの類似点と相違点」について記載しています。
この記事はポッドキャストでも音声解説を行っております。各種サイトで無料で聞くことができます。
はじめに:変革期にある地方企業とスタートアップ
日本の経済環境が大きく変化する中、地方企業の多くは代替わりや事業変革の時期を迎えています。特に創業者から二代目、三代目への経営交代や、デジタル化の波による事業モデルの見直しなど、変革を迫られている企業は少なくありません。一方で、革新的なビジネスモデルを掲げて急成長を目指すスタートアップも、日本各地で増加傾向にあります。
一見すると異なる道を歩んでいるように見える「変革期の地方企業」と「スタートアップ」ですが、実は多くの類似点と相違点を持っています。この記事では、両者を比較しながら、特に地方企業がスタートアップから学べる実践的な要素について考えていきます。
私自身、リクルートでの法人営業経験と地方での起業経験の両方を持ち、さらに複数のスタートアップでの勤務経験があります。これらの経験から感じたのは、地方企業とスタートアップには共通の課題がある一方で、その対応アプローチには大きな違いがあるということです。
地方企業とスタートアップの類似点
リソースの制約
地方企業とスタートアップの最も明確な共通点が「リソースの制約」です。ここでいうリソースとは、資金、人材、時間、情報など、事業を展開する上で必要なあらゆる資源を指します。
地方企業は大都市の大企業に比べて資金調達や人材確保に苦労し、スタートアップも創業初期は極めて限られたリソースの中で事業を立ち上げます。両者とも、「選択と集中」「外部リソースの活用」「創意工夫によるコスト削減」など、限られたリソースで最大の効果を得るための工夫が求められます。
地方企業の場合、特に専門性の高い人材確保が難しく、スタートアップも少人数のチームで多様な役割をこなさなければなりません。このリソース制約は、両者にとって創意工夫の源泉でもあります。
ブランド構築の課題
地方企業もスタートアップも、市場での認知度やブランド力の構築に苦労するという共通点があります。
地方企業は地元では知名度があっても、地域を超えた広い市場では認知されにくく、スタートアップはゼロからブランドを構築する必要があります。特に代替わり期の地方企業では、「昔ながらの〇〇屋さん」というイメージから脱却しつつ、信頼関係を維持するという難しい課題に直面します。
この課題に対して、両者は「ストーリーテリング」「ニッチ市場での強み構築」「デジタルマーケティングの活用」などの共通のアプローチを取ることが多いです。
成長志向
変革を目指す地方企業とスタートアップは、「現状維持ではなく成長を目指している」という点で共通しています。
特に代替わりや事業転換期にある地方企業は、従来のビジネスモデルに限界を感じ、新たな経営陣のもとで「次の成長」を模索しています。スタートアップも本質的に「急成長」を前提としたビジネスモデルを持っています。
成長に対する時間軸や規模感はスタートアップの方が急進的ですが、「今よりも大きく成長したい」という基本的な志向性は両者に共通しています。このために「新規市場の開拓」「イノベーションへの投資」「人材育成と採用」「デジタル化の推進」などの取り組みを行います。
地域との関わり
地方企業とスタートアップの両者にとって、「地域」との関わりは重要な要素です。特に、地方で事業を展開するビジョンを持つスタートアップと、地域に根ざした地方企業には、この点で大きな共通点があります。
地方企業は長年その地域で事業を営み、地域社会との深いつながりを持っています。地域の雇用を支え、地域経済に貢献し、時には地域のコミュニティの中心的役割を担います。
一方、地方創生やローカルイノベーションを掲げるスタートアップは、地域特有の課題解決や資源活用を事業の中心に据えています。両者とも、地域資源の活用、地域課題の解決、地域人材の育成と活用などを通じて、地域との関係を重視しています。
地方企業とスタートアップの相違点
時間軸と出口戦略の違い
地方企業とスタートアップでは、事業の時間軸と最終的なゴール(出口戦略)に大きな違いがあります。
地方企業、特に老舗企業や家族経営の企業では、「何世代にもわたって事業を継続していく」という長期的な時間軸で経営を考えることが一般的です。出口戦略という概念自体があまり馴染まず、むしろ「いかに持続可能な形で事業を継続するか」「いかに地域に根差した企業として存続するか」という永続性が重視されます。
対照的に、スタートアップは比較的短い時間軸で事業展開を考えます。特に外部からの投資を受けるスタートアップは、投資家のリターン期待に応えるため、通常5〜10年程度の間に「出口戦略」を実現することが求められます。これはベンチャーキャピタルのファンド償還期限(8〜10年)に合わせたものです。
こうした時間軸の違いは、投資判断、リスク許容度、人材戦略など、経営の様々な側面に影響を与えます。
収益モデルと投資の考え方
地方企業とスタートアップでは、収益モデルや事業投資に対する考え方に大きな相違点があります。
地方企業では、「堅実な収益を継続的に確保する」というビジネスモデルが一般的です。新規事業への投資も慎重に行われ、投資回収の確実性や既存事業とのシナジーが重視されます。「赤字を出しながら急成長する」よりも「確実に黒字を維持しながら段階的に成長する」という保守的なアプローチが多いです。
一方、スタートアップ、特にVC(ベンチャーキャピタル)の投資を受けるスタートアップでは、初期段階での赤字は当然のこととして受け入れられています。「先行投資によって急速に市場シェアを獲得し、その後収益化する」という戦略が一般的で、短期的な黒字よりも成長率や将来の収益ポテンシャルが重視されます。
これらの違いは、資金調達の方法(銀行融資 vs エクイティ調達)、成長の速度、収益化のタイミングなどに顕著に表れます。
リスクへの姿勢
地方企業とスタートアップでは、リスクに対する基本的な姿勢が大きく異なります。
地方企業、特に長い歴史を持つ企業では、「リスク回避」「リスク管理」を重視する傾向があります。これは企業の永続性を確保し、地域における信頼関係を維持するためでもあります。新しい取り組みのリスクは慎重に評価され、一つの大きな賭けよりも、複数の小さな試みを通じてリスクを分散させる傾向があります。
対照的に、スタートアップはその性質上、高いリスクを取ることを前提としています。「10の挑戦のうち9つが失敗しても、1つの大成功で全体をカバーする」というリスク・リターンの考え方が基本にあります。特にVCの投資を受けるスタートアップでは、「失敗を恐れずに大きな挑戦をする」という文化が奨励されます。
このリスクへの姿勢の違いは、意思決定のスピード、事業ポートフォリオの組み方、失敗への対応、イノベーションのアプローチなどに大きな影響を与えます。
組織文化と意思決定スピード
地方企業とスタートアップでは、組織文化や意思決定のあり方に特徴的な違いがあります。
地方企業、特に長い歴史を持つ企業では、階層的な組織構造や確立された意思決定プロセスが一般的です。「和を重んじる」「前例を重視する」といった伝統的な日本的組織文化が根づいていることも多く、新たな施策の実行までに時間を要することがあります。
一方、スタートアップでは、フラットな組織構造や柔軟な役割分担が特徴的です。「スピード重視」「結果主義」「挑戦を奨励する」といった価値観が組織文化の基盤となり、意思決定も迅速に行われる傾向があります。少人数のチームで多様な業務をこなすため、一人が複数の役割を担う「マルチプレイヤー」的な働き方も一般的です。
この違いは、変化への適応力、イノベーションの創出プロセス、人材の育成と活用方法、コミュニケーションのスタイルなど、さまざまな面に表れます。
地方企業がスタートアップから学べる要素
限られたリソースの中で効果的に成長するために、地方企業がスタートアップから学べる要素は数多くあります。特に代替わり期や変革期にある地方企業にとって、以下の要素は実践的な価値があるでしょう。
1. リソース効率を最大化する「戦わない戦略」
スタートアップは、大企業と真正面から競争せず、未開拓の市場や特定のニッチ市場に焦点を当てる「ブルーオーシャン戦略」をとることが多いです。地方企業も地域性や独自の強みを活かして、大手企業と直接競合しない独自の市場ポジションを確立することが重要です。
例えば、「地域特有のニーズに特化したサービス」「大手が対応しきれない少量多品種の製品」「地域資源を活かした独自性の高い商品」など、差別化された価値提案を行うことで、限られたリソースでも存在感を示すことができます。
地方企業やスタートアップに共通する「低リソース・ブランド無しの戦わない戦略」は、以下のような施策で実現できます:
- 競合との直接対決を避ける
- 地域ならではの強みを活かす
- 協業によって新たな価値を創造する
地域の伝統や文化、独自の資源を活用することで、大手企業には真似できない価値を提供できる点が、地方企業の大きな強みとなります。
2. 顧客インサイトに基づく価値創造
スタートアップは、顧客の表面的なニーズだけでなく、潜在的な「インサイト(本当の望み)」を理解することに注力します。地方企業も長年の地域での活動で培った顧客との近い関係性を活かし、対話を通じて顧客の本当の望みを掘り下げることができます。
インサイト理解のための基本構文「ユーザーは〇〇という課題を今は△で解決しているが、本当は××の方がいい」を使って、顧客の深層心理を構造化して理解することが有効です。例えば、「安い商品が欲しい」という声の背後には、「品質を犠牲にせず、賢く買い物をしている自分でありたい」という本音があるかもしれません。
また、ターゲットと便益を5〜10パターンに整理する手法も取り入れられます。サービスは単一の属性のターゲットに対応しているのではなく、複数の異なる属性に対して異なる価値を提供する、という考え方です。「Who(どんな属性の人に)」「What(どんな提供価値を)」「独自性(他社と比べてもより良い形で)」の3つの要素で整理することで、より幅広い顧客層にアプローチできるようになります。
地方企業は顧客との距離が近いという強みを活かして、大企業では捉えきれない細かなインサイトを把握し、それに基づいた独自の価値提案ができます。
3. 効率的なマーケティング手法の活用
スタートアップは限られた予算で最大の効果を得るために、様々な効率的なマーケティング手法を駆使しています。地方企業もこれらの手法を学び、限られたリソースで効果的なマーケティングを実現できます。
「ブレンデッドCPA(総合的な顧客獲得コスト)」の考え方は特に重要です。これは、すべての流入経路を合わせた平均的な顧客獲得コストを指します。例えば、広告経由、紹介経由、オーガニック流入などを組み合わせることで、全体の顧客獲得コストを最適化できます。
また、「ストック>フロー」という考え方も重要です。広告は出稿をやめれば効果もすぐに消えてしまう「フロー型」の施策ですが、SEOやコンテンツマーケティングなどは一度構築すれば継続的に効果を発揮する「ストック型」の施策です。地方企業は特に、この「ストック型」の施策に注力することで、持続可能な顧客獲得の仕組みを作ることができます。
具体的には以下のようなアプローチが有効です:
- コンテンツの積み上げが相乗効果になっていくSEO対策
- 地域に特化した情報や専門知識を体系的に発信するコンテンツマーケティング
- プレスリリースや地域メディアとの関係構築による露出拡大や被リンク施策
- 無料/低コストのマーケティングツール(Google Analytics、Canvaなど)の活用
こうした施策により、限られた予算でも継続的に顧客を獲得できる基盤を整えることができます。
4. 無料ツールを活用した採用チャネルの整備
スタートアップは人材確保のためにさまざまな採用チャネルを活用しています。地方企業も無料ツールから始める段階的な採用チャネルの整備を行うことで、採用力を高めることができます。
まずは無料のATS(採用管理システム)を導入し、複数の求人媒体に一括掲載することから始めます。求人タイトルの工夫、魅力的な求人文の作成、写真や画像の活用など、基本的な改善だけでも応募数は大きく変わります。
また、自社の採用基盤として、自社HPでの求人ページの作成、Googleマイビジネスでの求人情報の掲載、社員インタビューなどのコンテンツ追加も効果的です。これらは一度作れば継続的に効果を発揮する「ストック型」の施策となります。
人材確保が難しい地方企業こそ、複数の採用チャネルを整備し、企業の魅力を効果的に伝える工夫が必要です。特に地方企業の強みである「地域での存在意義」「ワークライフバランス」「長期的な関係性と安定」などの価値を明確に打ち出すことが重要です。
5. 少人数組織でも機能する業務分担モデル
スタートアップは少人数でも効率的に業務を遂行するための工夫を凝らしています。地方企業も同様に、限られた人数で最大の効果を出すための業務分担モデルを取り入れることができます。
完全な分業制ではなく、以下のような「ハイブリッド型」のアプローチが現実的です:
- 核となる役割での分業(新規開拓に強い担当者と既存顧客管理に強い担当者の役割分担)
- チーム制による相互補完(個々の営業担当者が得意・不得意を補い合うペア制)
- 時間配分による機能分担(週や月の中で、新規開拓活動と既存顧客フォローの時間を明確に分ける)
また、マーケティングや顧客管理のプロセスを「ファネル」として可視化し、各段階での転換率を数値で把握することで、ボトルネックの特定と重点的な改善が可能になります。
地方企業の少人数組織の強みは、一つひとつの案件について深く議論できることです。特に「どのような顧客」に「どのような提案」が有効かという傾向の分析や、成功事例をテンプレート化することで、個人の勘や経験に依存しない組織的な営業力を構築できます。
6. デジタルツールの効果的な活用
スタートアップは限られたリソースを補うために、様々なデジタルツールを効果的に活用しています。地方企業でも無料または低コストのツールを組み合わせることで、業務効率化やマーケティング強化が可能です。
例えば、以下のようなツールが活用できます:
- Google アナリティクス、サーチコンソール、タグマネージャー:ウェブサイトの訪問者分析、検索分析
- Google ビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス):MEO(地図検索)の最適化
- HubSpot(無料版):問い合わせ管理とCRM機能
- AhrefsなどのSEOツール:競合分析やキーワード戦略立案
これらのツールは、専門的な知識がなくても基本的な機能から段階的に活用していくことで、大きな効果を生み出すことができます。特に地方企業においては、デジタルツールの活用によって地理的制約を超えた市場へのアプローチが可能になります。
まとめ:それぞれの強みを活かした成長の形
地方企業とスタートアップには、リソースの制約やブランド構築の課題、成長志向、地域との関わりといった共通点がある一方、時間軸や出口戦略、収益モデルとリスクへの姿勢、組織文化と意思決定スピードなどの面で大きな違いがあることがわかりました。
地方企業がスタートアップから学べる要素としては、「戦わない戦略」の実践、顧客インサイトに基づく価値創造、効率的なマーケティング手法、採用チャネルの整備、柔軟な業務分担モデル、デジタルツールの活用などが挙げられます。
変革期の地方企業にとって重要なのは、自社の強みである「地域との深いつながり」「長期的な信頼関係」「安定性」などを活かしながら、スタートアップの「スピード感」「顧客中心」「効率的なリソース活用」といった特性を取り入れていくバランス感覚です。
具体的には、以下のようなバランスを意識することが重要です:
- 伝統と革新のバランス: 長年にわたって築いてきた伝統や価値を尊重しながらも、新しい時代の流れに合わせた革新を取り入れる
- リスクと安定のバランス: 企業の安定性を維持しながらも、適切な範囲でリスクを取り新しい挑戦をする
- 地域性とより広い市場へのアプローチのバランス: 地域に根差した特性を大切にしながらも、より広い市場や世界の動向に目を向ける
- 人間関係重視とデジタル化のバランス: 対面での信頼関係を大切にしながらも、デジタル技術の利点を取り入れる
スタートアップの側も、短期的な成長や出口戦略だけでなく、地方企業が培ってきた持続可能性や地域との共生の知恵から学び、より長期的な視点を持つことで、真に社会に価値を提供し続ける企業へと成長していくことができるでしょう。
変革期の地方企業にとって、スタートアップの手法や考え方は、新たな成長の道筋を示す貴重なヒントとなります。ただし、それらを盲目的に取り入れるのではなく、自社の状況や文化に合わせて取捨選択し、独自の成長モデルを構築していくことが成功の鍵となるでしょう。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。