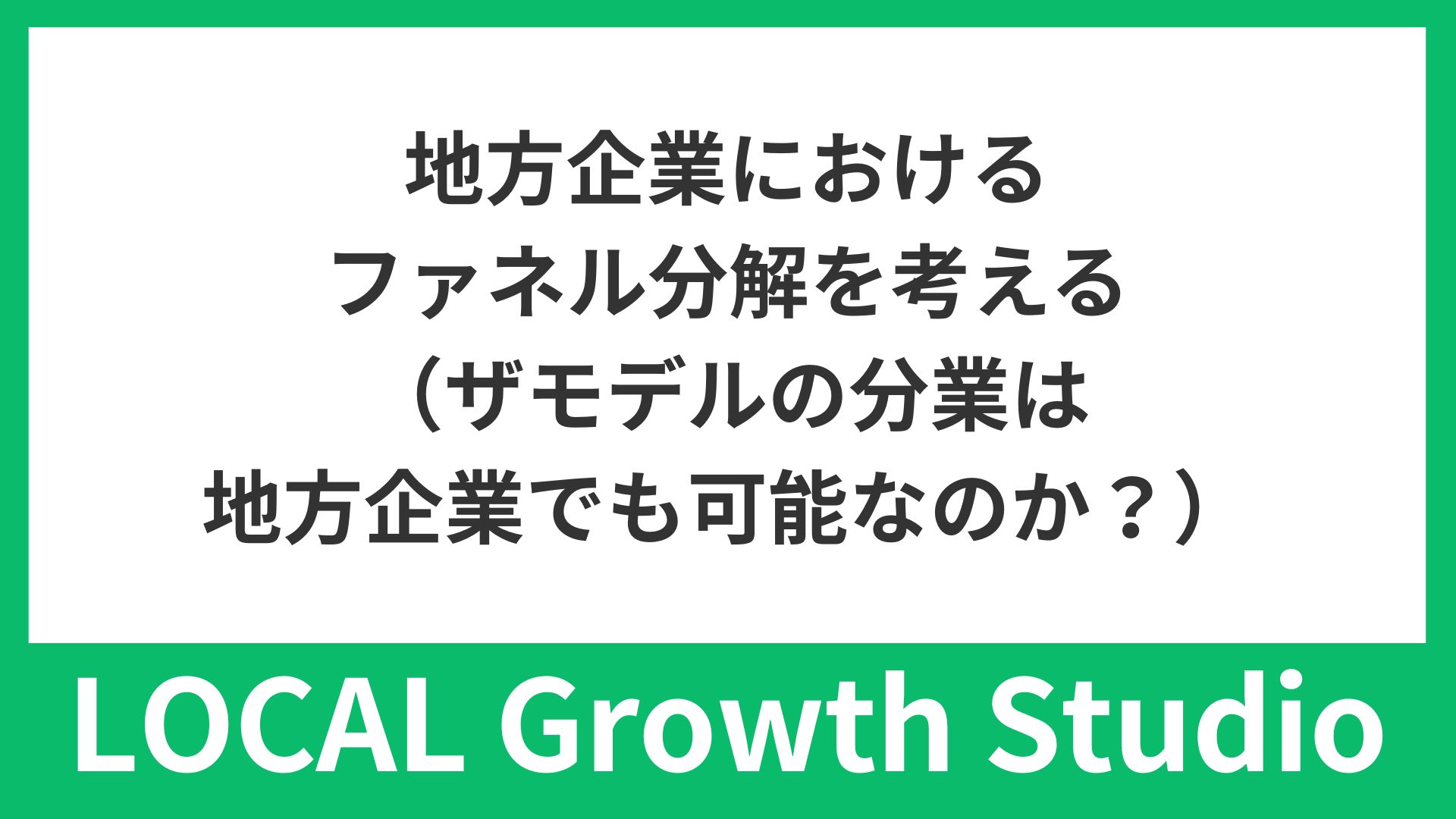ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
この記事は、「地方企業におけるファネル分解を考える(ザモデルの分業は地方企業でも可能なのか?)」について記載しています。
ファネルとザモデルの基本概念
「ファネル」とは見込み客が顧客になるまでの導線を指します。漏斗(ろうと)のような形をしていることから、この名前がついています。上から下に行くにつれて数が絞られていく様子を表現したものです。
典型的なBtoBのファネルでは、以下のような数値が一般的です:
- リード数1000件に対して
- アポイント獲得150件(転換率15%)
- 商談実施60件(転換率40%)
- 成約15件(転換率25%)
このように数値で可視化することで、どの段階で改善の余地があるのか、どこにボトルネックがあるのかが明確になります。これはまさに「測定できないものは管理できない」という経営の基本原則の実践そのものなのです。
「ザモデル」は、このファネルを組織的に運用するために確立された営業組織モデルです。主にSaaS企業で発展してきた手法ですが、その本質は業界を問わず応用可能です。具体的には:
- マーケティング:リード獲得を担当
- インサイドセールス:アポイント設定を担当
- フィールドセールス:商談と成約を担当
- カスタマーサクセス:継続利用支援を担当
という分業体制を特徴としています。この分業により、各工程の専門性と効率性を高めることができます。
Salesforceなどの先進的なSaaS企業では、この分業体制によって生産性が大きく向上するケースが多いと言われています。しかし重要なのは、この形態を単に真似るのではなく、その背景にある「営業プロセスを可視化し、科学的に改善する」という思想を理解することなのです。
地方企業における営業組織の課題
多くのBtoB企業では、従来から以下のような管理体制が一般的です:
- エリアや顧客リストによる担当振り分け
- 四半期や年間の売上目標による管理
- 担当者の経験と勘に依存した営業活動
この方式の数値的な特徴を見ると:
- Aさん年間売上高 ○%達成
- Bさん年間売上高 ○%達成
- Cさん年間売上高 ○%達成
このような体制の課題は、個々の営業担当者の裁量に依存しすぎているという点です。つまり:
- プロセスの可視化が難しい
- 改善ポイントの特定が困難
- ノウハウが属人化しやすい といった問題が生じやすくなります。
特に地方企業では、しばしば「優秀な営業マン頼み」の経営が行われがちです。この「スーパー営業マン」がなぜ成功しているのかが組織的に解明されないまま、「あの人だから出来る」と片付けられてしまうのです。しかし、このような状態は組織としての成長に大きな障壁となります。組織としての業績改善には「なぜ成約したのか」「なぜ失注したのか」というプロセスの理解が不可欠になります。
少人数組織に適したファネル分解の考え方
地方の少人数組織では、ザモデルのような完全な分業体制ではなく、営業プロセスを「分解」して可視化・最適化するアプローチが効果的です。では、具体的にどのようにファネルを分解し、少人数でも効率的に運用していくべきでしょうか。
少人数組織のためのファネル分解ステップ
ステップ1:現状の営業プロセスを可視化する
まずは現在の営業活動の流れを書き出すことから始めましょう。少人数組織では、以下のような簡易的なファネル分解が効果的です:
- リード獲得段階
- どのような経路で見込み客を獲得しているか
- 月間の獲得数とその質はどうか
- 初期接触・アポイント獲得段階
- 初期接触の方法(電話、メール、訪問など)
- アポイント獲得率とその要因
- 提案・見積り段階
- 商談から提案までの流れ
- 提案から見積りへの進捗率
- 成約段階
- 見積りから成約までの転換率
- 成約までの平均期間
ステップ2:少人数組織でも実践できる数値管理
少人数組織では、複雑なCRMツールよりも、まずはエクセルやスプレッドシートを活用した簡易的な数値管理から始めることをお勧めします。週次でチェックすべき重要指標は:
- 新規リード数:週間の新規見込み客数
- 商談数:週間の商談実施件数
- 提案数:週間の提案実施件数
- 成約数:週間の成約件数
これらの数値を、営業担当者全員が閲覧できる形で共有し、週に一度30分程度の振り返りミーティングを実施するだけでも、大きな変化が生まれます。
ステップ3:少人数ならではの深堀り分析
少人数組織の強みは、一つひとつの案件について深く議論できることです。成約した案件と失注した案件について、以下の点を分析しましょう:
- この案件はどのような経緯で発生したか
- 顧客のどのような課題やニーズに応えたか
- 成約/失注の決め手は何だったか
- 次回に活かせる学びは何か
この分析を通じて、「どのような顧客」に「どのような提案」が有効かという傾向が見えてきます。少人数組織ではリソースが限られているからこそ、「勝てる案件」への集中が重要なのです。
少人数組織のファネル運用の特徴
効率的なファネル分解では、以下の3点を特に意識すべきです:
- 質の高いリード獲得への集中
- 成約事例に似た特徴を持つ見込み客へのアプローチ
- 紹介や既存顧客からの紹介の仕組み化
- 地域ネットワークを活用した見込み客発掘
- 提案・商談の質の向上
- 顧客情報の事前収集と共有
- 成功事例を基にした提案テンプレートの活用
- 複数メンバーによる提案内容のブラッシュアップ
- 成約後のケアの仕組み化
- 定期的なフォローアップの予定化
- 追加提案のタイミングの標準化
- 紹介依頼のプロセス化
少人数組織だからこそ、個々の案件に対して丁寧に対応できる強みを活かしながら、プロセスの標準化と可視化を進めることで、個人の勘や経験に依存しない組織的な営業力を構築できるのです。
地方企業におけるカスタマーサクセスの役割
ザモデルの重要な構成要素の一つがカスタマーサクセスです。大規模SaaS企業ではこの役割を専門チームが担当していますが、地方の少人数組織ではどのように実践すべきでしょうか。
カスタマーサクセスの重要性
カスタマーサクセスについて、よくある誤解は「営業ではないサポート部隊」という認識です。しかし、これは大きな認識の誤りです。カスタマーサクセスは、れっきとした「既存顧客営業」としての専門性が求められる重要な役割なのです。特に地方の少人数組織においては、この機能が事業の安定性と成長性を支える柱となります。
地方企業向けのカスタマーサクセス実践法
地方の少人数組織では、専任のカスタマーサクセス担当者を置くことが難しい場合が多いでしょう。そこで、以下のような工夫が効果的です:
- 役割の明確化と時間配分
- 既存営業担当者の業務時間の20-30%をカスタマーサクセス活動に割り当て
- 週や月の特定の日をカスタマーサクセスデーとして設定
- 顧客ごとの定期フォローの予定を明示的にスケジュール化
- 最低限の定期接点の設計
- 新規契約後の1週間・1ヶ月・3ヶ月時点でのフォローアップ
- 四半期に一度の利用状況確認と満足度調査
- 契約更新の3ヶ月前からの計画的なアプローチ
- 顧客情報の一元管理
- 簡易的なCRMツールの活用(Hubspot無料版、Notion、Googleスプレッドシートなど)
- 顧客とのやり取りを全て記録し、誰でも確認できる状態に
- 顧客の重要イベント(決算期、繁忙期など)の把握と対応
地方企業ならではのカスタマーサクセスの強み
地方企業には以下のようなカスタマーサクセス上の強みがあります:
- 意思決定の速さ
- 顧客からの要望に対して迅速に対応可能
- 特別対応や例外処理の即断即決
- 問題発生時の責任者への素早いエスカレーション
- 深い人間関係の構築
- 経営者同士の直接的な関係性
- 地域コミュニティを通じた多面的な接点
- 長期的な信頼関係の醸成
- 地域特有の文化や商習慣への理解
- 地域内の業界動向に関する深い知識
- 地域特有の課題やニーズへの共感
- 地域内の人脈や紹介ネットワークの活用
単なるルーティン対応ではなく、顧客の事業課題に深く関与し、成果創出を支援する姿勢が重要です。顧客に対して「ただのサプライヤー」ではなく「ビジネスパートナー」としての関係を構築することを目指しましょう。
実践的な組織設計のステップ
これまでの内容を踏まえ、地方の少人数組織において具体的にどのようにファネル分解を取り入れるべきでしょうか。ここでは実践的なステップを見ていきましょう。
1. 事業計画の数値整理から始める
まずは、既存顧客と新規顧客の売上比率から計画を策定します:
- 既存顧客売上比率の目標値:75%
- 新規開拓の目標値:25%
- 顧客単価の維持/向上目標
この数値の設定が重要なのは、これによって必要な工数や時間配分が見えてくるためです。例えば、新規顧客からの売上を30%と設定しているにも関わらず、実際の新規開拓活動時間が10%しかないといった矛盾が生じていないか確認する必要があります。
2. 現状とのギャップ分析
計画と現状のギャップを分析する際の重要な観点:
- 既存顧客の継続率は適切か
- 新規獲得のコストは妥当か
- リソース(時間・人材)は適切に配分されているか
このギャップ分析では、単なる数値比較だけでなく、以下のような質的な側面も考慮すべきです:
- 営業活動のどのプロセスに最も時間がかかっているか
- 社内の情報共有はスムーズに行われているか
- 顧客情報の管理状況はどうか
3. KPIの設定と管理サイクル
効果的なKPI管理には、以下のような頻度での確認が有効です:
- 週次:リード獲得数、アポイント数
- 月次:商談実施数、成約数
- 四半期:顧客継続率、アップセル率
ただし、ここで重要なのは、これらの数値は「目的」ではなく「手段」だということです。数値を追うことが目的化してしまうと、かえって顧客価値を損なう可能性があります。
例えば、アポイント数だけを追うと、質の低いアポイントが増える可能性があります。常に「最終的な成果」と「プロセス指標」のバランスを取りながら管理することが重要です。
KPI管理で最も重要なのは「改善のための対話」です。単に数字を報告するだけでなく、「なぜこの数字になったのか」「どうすれば改善できるのか」を議論する場を設けることで、組織全体の成長につながります。
4. 小規模組織に適した実践ポイント
地方の少人数組織では、完全な分業体制よりも、以下のような実践方法が有効です:
- 時間ブロック制:週や日の中で、新規開拓と既存顧客フォローの時間を明確に分ける
- チームでの振り返り:週に一度、全案件の状況と課題を共有する時間を設ける
- 簡易的なツール活用:エクセルやスプレッドシートなど、導入コストの低いツールから始める
ザモデルの本質は「分業」ではなく「プロセスの可視化とKPI管理」にあります。この本質を理解し、自社の規模や状況に合わせて柔軟に取り入れることが成功の鍵となるのです。
地方企業が陥りやすい落とし穴と対策
地方企業が営業組織の強化において陥りやすい落とし穴と、その対策について考えてみましょう。
1. 営業ツールの過剰導入
都市部の最新トレンドに触発されて、高額なCRMシステムやSFAツールを導入したものの、活用しきれずに形骸化してしまうケースが少なくありません。
対策:
- 必要な機能を明確にした上での導入判断
- エクセルやスプレッドシートから始めるステップアップ方式
- 定期的な活用状況の確認と改善
最も重要なのは、ツール導入の「目的」を明確にすることです。「可視化して改善するため」という目的が共有されていれば、最初は簡易的なツールでも十分に効果を発揮できます。
2. 過剰な数値管理による営業の画一化
数値管理を導入することで、かえって営業活動が硬直化し、「数字合わせ」のための表面的な活動が増えてしまうケースがあります。
対策:
- 数値とストーリーの両面からの評価
- 定性的な成功要因の共有と分析
- 顧客価値を最優先する文化の醸成
数値管理の目的は「改善」であることを常に意識し、単なる評価ツールにしないことが重要です。特に地方企業では、顧客との信頼関係が競争優位の源泉になることが多いため、数値だけでは測れない価値も大切にする文化が必要です。
3. 過去の成功体験への固執
「これまでうまくいってきたのだから」という思考から、新しい営業手法や顧客接点の開拓を躊躇するケースが少なくありません。
対策:
- 小規模な実験を奨励する文化
- 外部の成功事例の積極的な学習
- 若手社員の視点を取り入れる仕組み
特に地方企業では、長年同じ顧客や地域を相手にしてきた結果、変化を起こしにくい環境になっていることがあります。しかし、顧客の購買行動や情報収集方法は急速に変化しており、過去の成功パターンだけでは対応できない時代になっています。小さな変化から始めて、徐々に新しい方向性を模索していくアプローチが効果的です。
まとめ:ザモデルの本質を地方企業に活かす
ここまで、ザモデルの考え方と地方企業での実践について見てきました。最後に、その本質と実践のポイントをまとめてみましょう。
ザモデルの本質とは
ザモデルの本質は、「分業体制」という形態ではなく、以下の点にあります:
- 営業プロセスの可視化
- 顧客獲得から育成までの全工程を明確に定義
- 各段階での転換率を数値で把握
- ボトルネックの特定と重点的な改善
- 科学的なKPI管理
- 結果指標(成約数、売上)と過程指標(リード数、商談数)のバランス
- 定期的なモニタリングと改善サイクル
- データに基づく意思決定
- 継続的な改善文化
- 成功・失敗からの学習と共有
- 顧客の声を取り入れた営業プロセスの改善
- 小さな実験と検証の繰り返し
これらの本質は、組織の規模や業種に関わらず、あらゆる企業に適用可能な普遍的な価値を持っています。
地方企業での実践ポイント
地方の少人数組織では、以下のポイントを押さえることで、ザモデルの本質を効果的に取り入れることができます:
- 現実的な目標設定
- 自社のリソースと市場規模に合った数値目標
- 段階的な改善を重視した計画
- 短期・中期・長期のバランスある目標設計
- シンプルな仕組みづくり
- 複雑なツールよりも運用しやすいシンプルな仕組み
- 全員が理解し参加できる振り返りの場
- 日常業務に無理なく組み込める数値管理
- 地域特性の活用
- 地域ネットワークを活かした質の高いリード獲得
- 地域内の信頼関係を基にした顧客育成
- 地域ならではの強みをアピールしたプロポジション
トヨタ自動車が世界に誇る「改善」の文化は、まさに「細分化されたプロセスの継続的な見直しと最適化」という点で、ザモデルの本質と共通しています。地方企業においても、この「改善」の考え方を取り入れることで、限られたリソースの中でも持続的な成長を実現することができるのです。
日本の地方には、長年培われた職人気質と誠実な顧客対応の文化があります。これに営業プロセスの可視化とKPI管理という科学的アプローチを加えることで、グローバル企業にも負けない競争力を身につけることができるでしょう。まずは小さな一歩から、自社に合った形でのファネル分解と改善サイクルの構築を始めてみてください。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。