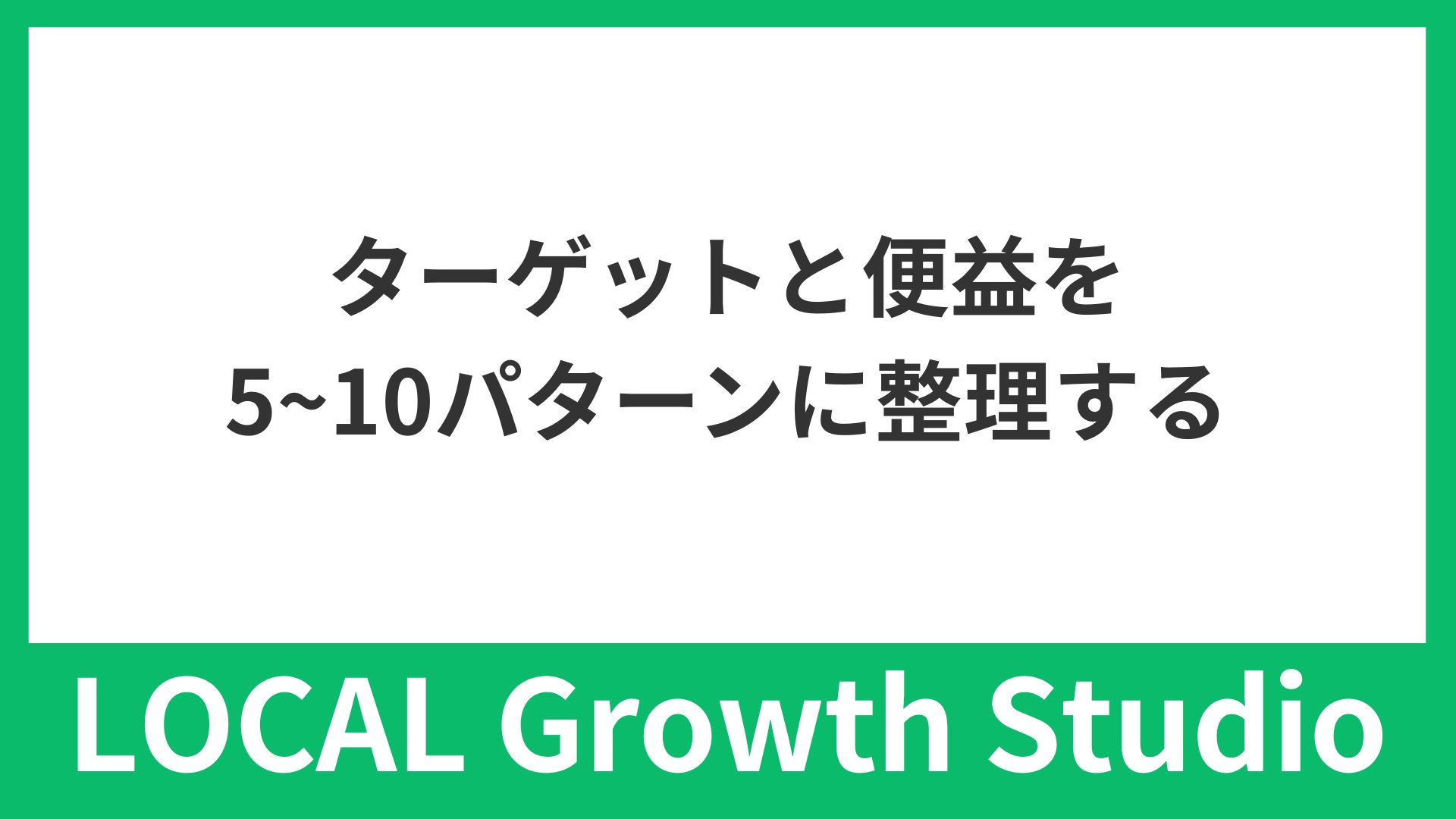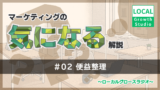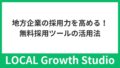ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
この記事は、「ターゲットと便益を5-10パターンに整理する」について記載しています。
この記事はポッドキャストでも音声解説を行っております。各種サイトで無料で聞くことができます。
便益整理の考え方について
顧客起点マーケティングの第一人者である西口一希さんのに、コンサルティングを受けながら事業運営していた経験のまとめになります。
私は以前、ユーザベースFORCAS事業に所属しており、当時の経営陣が西口さんのコンサルティングを受け事業方針に反映し、西口さんの書籍を読み学んでいました。その後、自身がスタートアップ役員になった際にこの考え方を実践し成果につなげていました。
西口さんが提唱する便益整理の考え方は、実にシンプルです。サービスは単一の属性のターゲットに対応しているのではなく、5〜10個の属性を内包している、という考え方なのです。つまり、「このサービスは○○な人向け」というより、「このサービスは○○な人にはこんな価値があり、△△な人にはまた別の価値がある」という捉え方をするのです。
便益は以下の3つの要素で整理します:
- Who:どんな属性の人に
- What:どんな提供価値を
- 独自性:他社と比べてもより良い形で
この3つを5-10パターンにまとめることで、より幅広い顧客層にアプローチできるようになります。また、マーケティングコミュニケーションの精度も高まるのです。
実践事例:ベンチャーデット事業での経験
ベンチャー向けの資金調達支援サービスで活用した実践事例です。
最初は「成長企業向けの資金調達支援」という漠然とした捉え方をしていたのですが、顧客との取引記録を整理していく中で、実に様々なパターンが見えてきました。
例えば:
- 急成長スタートアップ
- Who:シリーズA〜B手前の企業
- What:迅速な資金調達による成長機会の確保
- 独自性:審査から入金までのスピード感
- 在庫回転企業
- Who:EC事業者、小売業
- What:仕入れ資金の機動的な確保
- 独自性:精緻な将来予測から柔軟に融資判断
- ミドルステージスタートアップ
- Who:シリーズB~Cの企業
- What:株式希薄化しない資金調達
- 独自性:株式担保なしのベンチャーデット、最大数億が数週間で
このように整理していくと、それぞれの属性に応じてメッセージを出し分けることができるようになりました。例えば、急成長スタートアップには「2週間での資金調達で、成長機会を逃さない」というメッセージが響き、在庫回転企業には「将来の売上予測から柔軟に融資判断」といったメッセージが効果的だったのです。
また、この便益整理によって、製作コンテンツの内容や、マーケティング施策、さらには営業トークにも一貫性を持たせることができました。
実践事例:キャッシュレス事業での展開
キャッシュレス決済サービスでも同様の整理を行いました。
当初は「キャッシュレス化を進めたい店舗」という大きな括りでしか見ていなかったのですが、利用者の行動パターンを分析していく中で、以下のような分類が見えてきたのです:
- ポイント重視層
- Who:ポイ活に熱心なユーザー
- What:還元率の最大化
- 独自性:残高に対する2%のポイント還元
- 海外旅行好き層
- Who:年に数回の海外旅行者
- What:手数料の節約
- 独自性:海外事務手数料無料
- 節約好き
- Who:節約が好きなユーザー
- What:お金を余らせれば余らせるだけポイントがつく
- 独自性:残高に対する2%のポイント還元
この属性整理に基づいて、広告のクリエイティブを出し分けたり、アライアンス先を選定したり、コンテンツ記事のパターンを作り分けていきました。例えば、旅行代理店とのアライアンスでは「海外旅行好き層」向けのメッセージを強調し、ポイ活ユーザー向けでは大手ポイント発行事業者との連携などの施策を行いました。
結果として見えてきたのは、「同じサービスでも、顧客によって得られる価値が全く違う」という事実です。そして、それぞれの価値を適切に言語化し、訴求することで、成約率が大きく向上したのです。
ある顧客層に対しては、「還元率が業界トップクラス」という訴求が響き、別の層には「導入後のサポートが手厚い」という訴求が効果的でした。同じサービスでも、受け手によって価値の感じ方が異なるため、それを理解し適切にコミュニケーションすることが重要だったのです。
便益パターンを見つける手順
私の経験から、便益パターンを見つけるための具体的な手順をお伝えしたいと思います。
まずは自社の顧客群の分類から始めます:
- 売上/利益貢献度の高い順に顧客を並べる
- なぜこの顧客は自社のサービスを選んでくれたのかどんな価値を感じてくれているのか他社ではなく、なぜ自社なのか
- 新規問い合わせの分析
- どんな課題を持って問い合わせてくるのか初期接触時の関心事は何か成約に至る/至らない理由は何か
- 小口顧客の分析
- 発注は小さくても好意度が高い顧客は何を評価しているのかどんな使い方をしているのか潜在的な成長可能性はあるのか
- 仮説の検証
- このようなターゲットもいるのではないか
- 競合から見たときの自社の独自性は何か
- 市場全体から見た時の機会領域はどこか
この手順を通じて、最初は2-3パターンしか見えていなかった便益が、徐々に5-10パターンに広がっていきます。そして、それぞれのパターンに対して適切なアプローチを設計することで、マーケティングの精度が格段に向上するのです。
地方企業での実践方法
では、地方企業でこのような便益整理をどのように始めればよいのでしょうか。
私が地方で事業を展開してきた経験から、以下のようなステップを提案したいと思います:
- まずは現状の棚卸しから
- 直近1年の売上TOP20の顧客リストを作るそれぞれの顧客との会話を思い出す可能であれば、改めてヒアリングを行う
- パターンを見つける
- 業種や規模だけでなく、利用動機に注目「なぜ」を深掘りする似たような特徴を持つ顧客をグループ化
- 便益を言語化する
- Who/What/独自性の3つの要素で整理できるだけ具体的に書き出す5つ程度のパターンを目指す
- 施策に落とし込む
- パターンごとの訴求ポイントを決める
- 情報発信の方法を検討
- 新規開拓の方向性を定める
まとめ:まずは始めてみよう
便益パターンの整理は、一度やって終わりではありません。
顧客の声を聞くたびに、新しい気づきが生まれます。その気づきを蓄積し、定期的に見直していくことで、より精度の高い便益整理ができるようになっていくのです。
特に地方企業の場合、都市部と比べて情報量や事例が少ないと感じるかもしれません。しかし、だからこそ自社の顧客との対話を大切にし、その中から便益パターンを見つけていく作業が重要になります。
ときには「うちのサービスでこんな使い方をするんですね」と驚くような発見があるかもしれません。そうした顧客の声こそが、新たな便益パターンの発見、ひいては事業成長のヒントになるのです。
まずは、売上の大きな顧客から3社程度選んで、「なぜ自社のサービスを選んでくれているのか」をヒアリングしてみましょう。そこから見えてくるパターンが、便益整理の第一歩となるはずです。
まずは「便益パターン」を書き出してみる。そして顧客との会話の中で、その精度を高めていく。シンプルな取り組みですが、マーケティングの効果を大きく変える可能性を秘めています。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。