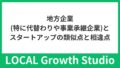ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
この記事は、「地方企業やスタートアップに共通する、低リソース・ブランド無しの戦わない戦略」について記載しています。
なぜ「戦わない戦略」が必要なのか
地方企業やスタートアップには、共通する課題があります。それは「リソースの限界」と「ブランド認知の低さ」です。大手企業と同じ土俵で戦えば、必然的に不利な戦いを強いられることになります。
大手企業との競争において、地方企業やスタートアップが直面する現実的な壁は以下のようなものです:
- 資金力の差:広告予算、人材投資、研究開発費など
- 知名度の差:求人や営業活動における信頼性の違い
- 規模の経済:仕入れコスト、製造コスト、配送コストの優位性
多くの地方企業の経営者から「大手と同じことをしても勝てない。でも、他に方法が分からない」という悩みを聞きます。これは、地方企業が抱える共通の課題なのです。
しかし、これらの課題は「戦わない戦略」によって解決できるのです。大手との直接対決を避け、自社の強みを活かせる市場や手法を選ぶことで、持続可能な成長が可能になります。
「戦わない」とは何か
孫子の兵法に「戦わずして勝つ」という言葉があります。戦略は、戦を略すと書き、やらないことを決めるとも言い換えられます。
「戦わない」戦略とは、以下の3つの要素で構成されます:
- 競合との直接対決を避ける:同じ市場、同じ方法ではなく、隙間市場や独自の手法を見つける
- 自社の強みを最大化する:大企業にはできない小回りの利く対応や地域密着型のサービス
- 協業によって新たな価値を創造する:競合ではなくパートナーとして関係を構築する
このアプローチは、「ブルーオーシャン戦略」と呼ばれる経営理論とも通じるものがあります。血みどろの競争(レッドオーシャン)ではなく、競争のない市場(ブルーオーシャン)を創造するという考え方です。
バリューチェーンから見る協業の可能性
ビジネスのバリューチェーンを深く理解することで、意外な協業の可能性が見えてきます。一見すると競合に見える企業であっても、バリューチェーンの異なる部分に強みを持っていることが多いのです。
実際に私が事業責任者を行っていた、決済アプリ事業では、ポイ活という市場で同じユーザーを取り合っているように見えていましたが、実際は「お金を貯めるときにポイントが貯まる」と「お金を使うときにポイントが貯まる」という違うタイミングで価値訴求ができていることを見つけ、積極的に他の高還元アプリやカードとの事業連携を検討することができました。
同じターゲット属性でもバリューチェーンを分解することで、一見競合に見えていた企業が、相互にメリットが生まれるパートナーになりうるのです。
バリューチェーン分析のポイントは以下の3つです:
- 自社の強みを正確に把握する:製造なのか、販売なのか、アフターサービスなのか
- 競合の強みを客観的に評価する:嫉妬や否定ではなく、尊重と学びの姿勢で
- 相互補完できるポイントを見つける:Win-Winの関係構築を目指す
地方企業にとって、限られたリソースを最大限に活かすためには、このような協業の視点が非常に重要です。単独では達成できないことも、適切なパートナーとの協業によって実現できることは数多くあります。
SEOにおける戦わないキーワード戦略
検索エンジン対策においても、「戦わない戦略」は非常に効果的です。大手企業が押さえている一般的なキーワードではなく、ニッチで競合の少ないキーワードを狙うことで、効率的に集客することができます。
SEOにおける「戦わないキーワード戦略」の基本的な考え方を詳しく見ていきましょう。
地方企業が直面するSEOの課題:
- 大手ポータルサイトとの検索順位競争の難しさ
- 一般的なキーワードでの広告費用の高騰
- 投資対効果の低さ
こうした課題を解決するため、「戦わないキーワード戦略」が有効です。この戦略は以下の3つの軸で構成されます:
戦わないキーワード選定の3つの軸:
- 商圏特化型
- 「中古マンション 東京」(×)→「子育て向けマンション ○○市」(○)
- 「新築物件 販売」(×)→「駅徒歩5分 新築 ○○町」(○)
- ニーズ特化型
- 「不動産 購入」(×)→「通学路安心物件」(○)
- 「マンション 売却」(×)→「相続対策 不動産 ○○市」(○)
- オリジナルコンセプト型
- 「中古住宅」(×)→「子育てファースト住宅」(○)
- 「マンション」(×)→「職住近接スマートライフ」(○)
SEOの専門家によると、こうした特化型キーワード戦略は特に中小企業や地方企業にとって効果的です。検索ボリュームは少なくても、コンバージョン率が高く、顧客獲得コストを大幅に抑えられるためです。
Ahrefs社やSEMrush社などのSEO分析ツールのデータによれば、一般的なキーワードと比較して、地域特化型キーワードは以下のような特徴があります:
- 検索競合度(Keyword Difficulty)が30-50%低い
- クリック率(CTR)が平均で15-25%高い
- コンバージョン率が最大で3倍になるケースもある
SEOにおける「戦わない戦略」の成功ポイントは以下の通りです:
- 競合分析の徹底:競合がどのキーワードに注力しているかを調査
- 地域特化の徹底:自社の商圏に特化したキーワード選定
- 独自コンセプトの確立:誰も使っていないオリジナルのキーワードの創出と育成
特に地方企業にとって、地域名と組み合わせたキーワード戦略は大きな効果を発揮します。大手企業は全国を対象にしているため、細かな地域名までカバーすることが難しいからです。
地域特化型マーケティングの実践
地方企業の大きな強みは、地域に根差した活動ができることです。この強みを活かした「地域特化型マーケティング」は、「戦わない戦略」の代表的な実践例と言えます。
地域特化型マーケティングの基本的な考え方と実践方法について詳しく見ていきましょう。
地方企業が直面するマーケティングの課題:
- 大手企業との広告力の差
- 限られたマーケティング予算
- 商品・サービスの差別化の難しさ
こうした課題を解決するために効果的なのが「地域特化型マーケティング」です。これは地域の特性や資源を活かしたマーケティング戦略で、以下のような具体的なアプローチがあります:
- 地元資源の徹底活用
- 地元特有の素材や技術の活用
- 地域の歴史や文化をストーリーとして発信
- 「地産地消」や「地域貢献」をテーマにしたブランディング
- 地域コミュニティとの関係構築
- 地元の祭りやマルシェへの積極参加
- 学校や公民館でのワークショップ開催
- 地域のスポーツチームや文化活動への協賛
- 地域メディアの戦略的活用
- 地元新聞や地方テレビへの定期的な情報提供
- コミュニティFMやケーブルテレビとの協力関係構築
- 地域性の高いSNSコミュニティでの情報発信
日本商工会議所の調査によると、地域に根差したマーケティング活動を行う中小企業は、そうでない企業と比較して以下のような傾向があります:
- 顧客ロイヤルティが平均で25%高い
- 口コミによる新規顧客獲得率が2倍以上
- 経済変動に対する事業の耐性が強い
特に観光や食品、小売業などの分野では、地域特化型のアプローチが大きな差別化要因となり得ます。中小企業庁の報告書でも、地域資源を活用した商品開発やマーケティングが、地方企業の持続的な競争優位性の源泉になることが指摘されています。
地域特化型マーケティングの重要ポイントは以下の3つです:
- 地域資源の発掘と活用:地元ならではの素材や文化を商品に活かす
- 地域コミュニティとの関係構築:単なる販売先ではなく、共に地域を盛り上げるパートナーとして
- 地域の誇りとなる商品開発:「この地域を代表する商品」という位置づけを目指す
大手企業は全国市場向けの商品開発やマーケティングに注力するため、細かな地域ニーズへの対応は苦手としています。ここに、地方企業が「戦わず」に成長できる大きなチャンスがあるのです。
具体的なアライアンス施策
戦わない戦略の具体的な実践方法として、アライアンス施策が効果的です。以下に、成功事例とともに紹介します:
1. 共同キャンペーンの開催
共同キャンペーンとは、「○○社×△△社コラボでサービスがお得に!」など、それぞれの顧客群に互いのサービスの認知や利用を高めるキャンペーン企画のことです。
- 複数企業の強みを組み合わせて相乗効果を生み出す
- リソースを集約することで個々の投資負担を軽減する
- 異なる顧客基盤へのクロスアクセスが可能になる
実施のポイント:
- 各店の顧客層の重なりと違いを分析
- 共通のテーマ設定
- 統一したビジュアルと訴求メッセージの作成
2. 共同イベント・セミナー・ウェビナー
共同イベント・セミナー・ウェビナーとは、それぞれのハウスリードや見込み顧客群に対して、サービスの認知や理解を高めるセミナーやイベントのことです。オフライン・オンラインともに効果があります。
実施のポイント:
- 相互の強みを活かしたコンテンツ設計
- 明確な役割分担と責任範囲の設定
- 顧客データの取り扱いルールの事前合意
3. プレスリリースの共同発出
プレスリリースの共同発出とは、複数の企業連名でプレスリリースを発出することにより、互いの認知度やブランドを活かした露出の強化と、メディア掲載率を高めるための施策です。
- 複数企業による共同プレスリリースは単独よりもメディア掲載率が高まる
- 業界を超えた連携による多様なメディアへの露出増加効果
- 地域貢献型プロジェクトの信頼性向上と長期的ブランド価値の強化
実施のポイント:
- 社会的意義のある共通テーマの設定
- 各社の強みや特徴を活かした役割設定
- プレスリリース後のフォローアップ体制の構築
アライアンス施策成功の鍵は、「Win-Win-Win」の関係構築です。つまり:
- 自社にとってのメリット
- パートナー企業にとってのメリット
- そして何より、顧客にとってのメリット
この3つがバランスよく設計されていることが重要です。特に、顧客メリットを最優先に考えることで、単なる企業間の取引ではなく、真に価値のあるアライアンスが実現します。
実践的なアクションプラン
これらの戦略を実践するための具体的なステップをご紹介します:
Step1:現状分析
- 自社の強みの棚卸し
- 製品・サービスの独自性は何か
- 地域との関係性の強さはどうか
- 顧客からの評価が高いポイントは何か
- 競合との差異の可視化
- 競合マップの作成(価格帯×品質、等)
- 競合が対応していない顧客ニーズの特定
- 競合の強みと弱みの客観的分析
- 潜在的なパートナーのリストアップ
- 補完関係にある企業の洗い出し
- 顧客層が重なる非競合企業の特定
- 地域内の信頼できる企業のリスト化
Step2:戦略立案
- 非競合領域の特定
- ニッチ市場の発見
- 地域特化型のサービス設計
- オリジナルコンセプトの開発
- Win-Winとなる協業ポイントの設定
- 相互の強みを活かせる接点の特定
- リソースの相互補完可能性の検討
- 共同で取り組める社会課題の設定
- 具体的な施策の検討
- 協業の形態選定(共同商品開発、販促連携など)
- 数値目標の設定(売上増加率、認知度向上など)
- 実施スケジュールと役割分担の決定
Step3:アプローチと実行
- パートナー候補への段階的なアプローチ
- まずは情報交換や意見交換からスタート
- 小規模な協力から始め、信頼関係を構築
- 正式な協業提案と条件交渉
- 小規模な協業からスタート
- 短期的かつ成果が見えやすいプロジェクトから
- 投資コストを抑えた試験的な取り組み
- 定期的な進捗確認と課題共有の場の設置
- 効果測定と改善
- 数値目標に対する達成度の評価
- 顧客からのフィードバック収集
- 次のステップに向けた改善点の整理
このように段階的に進めることで、リスクを抑えながら「戦わない戦略」を実践することができます。特に重要なのは、一度に大きな投資や変更を行わず、小さな成功体験を積み重ねていくアプローチです。
まとめ
「戦わない戦略」は、単に競争を避けるだけではなく、自社ならではの独自の価値を創造するための積極的なアプローチです。地方企業やスタートアップこそ、この戦略を取り入れることで、持続可能な成長を実現できるのです。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。