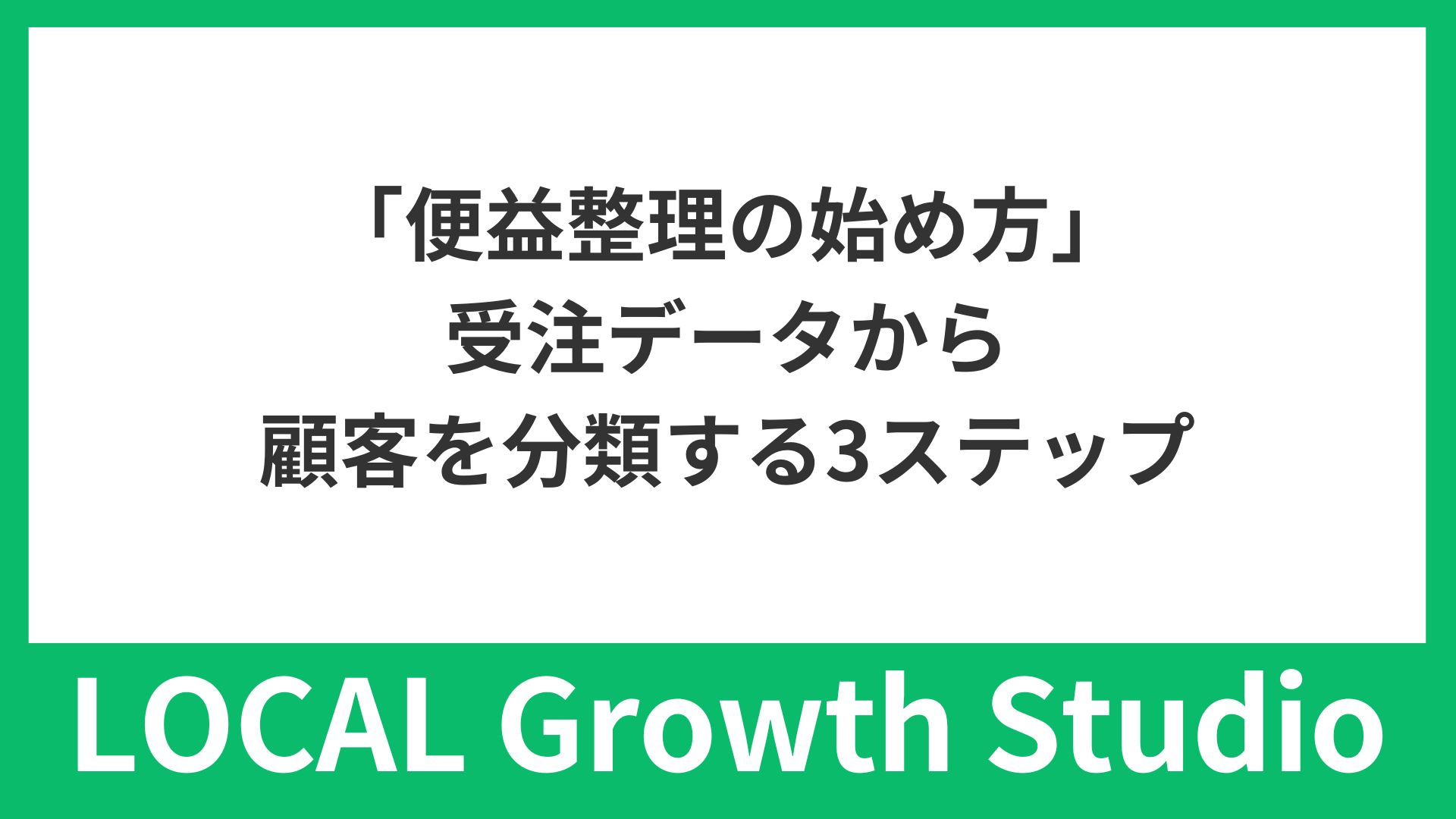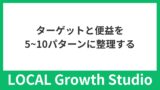ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
この記事は、「便益整理の始め方|受注データから顧客を分類する3ステップ」について記載しています。
便益整理とは何か
便益整理とは、自社のサービスの提供価値を、ターゲット群別に2〜10個程度に分類することです。
もう少し具体的に言うと、以下の情報を整理していく作業です。
企業属性(Who)
- 業種(製造業、小売業、サービス業など)
- 従業員数(10名以下、30名以下、100名以下など)
- 売上高(年商1億円未満、3億円未満、10億円未満など)
- 地域(関東、関西、地方都市など)
担当者属性(Who)
- 部署(営業部、マーケティング部、人事部など)
- 担当業務(新規開拓、既存顧客フォロー、採用など)
- 決裁レイヤー(経営者、部長、担当者など)
課題と解決したいこと(What)
- どんな課題を感じているのか
- 何を解決したいのか
- どんな成果を求めているのか
これらを整理することで、「自社のサービスは、誰に、どんな価値を提供しているのか」が明確になります。そして、その理解を元に、営業活動やマーケティング施策、プロダクト開発の精度を高めることができるのです。
なぜ便益整理が重要なのか
「うちのサービスは誰にでも使えます」「どんな業種でも対応できます」という言葉は、一見すると強みのように聞こえます。しかし、実際には「誰にも刺さらない」メッセージになってしまっています。
便益整理を行うことで、以下のようなメリットがあります。
1. 営業活動の効率が上がる
どんな企業にアプローチすべきか、優先順位が明確になります。過去の受注実績から、受注率が高い企業属性がわかれば、そこに営業リソースを集中投下できます。やみくもに営業するのではなく、「刺さる確率の高いターゲット」に絞ってアプローチできるようになります。
2. 提案の質が上がる
ターゲット群ごとに、抱えている課題や求めている価値が異なります。便益整理ができていれば、相手の課題に合わせた提案ができます。また、同じターゲット群の成功事例を紹介することで、説得力が増します。
3. マーケティング施策の精度が上がる
Web広告のターゲティングや、クリエイティブ(広告文やバナー)の訴求内容を、ターゲット群ごとに最適化できます。「誰にでも刺さるメッセージ」ではなく、「特定のターゲットに深く刺さるメッセージ」を作ることができます。
4. プロダクト開発の方向性が定まる
サービス改善や新機能開発を行う際、「誰のための改善なのか」を明確にできます。便益整理ができていないと、異なるターゲット群のニーズが混在し、ちぐはぐな改善になってしまいます。
便益整理は、事業成長の起点となる重要な作業なのです。
ステップ1:受注企業の情報を一覧化する
便益整理の第一歩は、既存の受注企業の情報を一覧化することです。
使用するツール
まず、ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトを用意します。SalesforceやHubSpotなどのSFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)を使っている場合は、そこからデータをエクスポートして活用します。
一覧化する情報
表には、以下のような項目を設定します。
基本情報
- 企業名
- 業種
- 従業員数
- 売上高
- 所在地(都道府県、エリア)
- 企業のWebサイトURL
担当者情報
- 担当者名
- 部署
- 役職
- 決裁権の有無
取引情報
- 初回受注日
- 契約プラン(松竹梅などのプラン差がある場合)
- 契約金額(月額、年額)
- 契約商品(複数商品がある場合、どの商品を契約しているか)
- 契約状況(継続中、解約済み)
課題・ニーズ情報
- 導入前に抱えていた課題
- 導入の決め手(なぜ自社を選んだのか)
- 導入後の成果(どんな効果が出ているか)
- 競合と比較された際のポイント
この「課題・ニーズ情報」は、商談時のメモや、カスタマーサクセスが収集したヒアリング内容、顧客インタビューの記録などから拾い集めます。定性情報(顧客の生の声)は非常に重要なので、できるだけ丁寧に収集しましょう。
新規営業だけでなくカスタマーサクセスの情報も活用する
便益整理を行う際、新規営業担当者が持っている情報だけでなく、導入後のサポートを担当するカスタマーサクセスが持っている情報も一緒にまとめることが重要です。
なぜなら、カスタマーサクセスは、顧客がサービスを実際に使ってみて感じた価値や、当初想定していなかった使い方、追加で出てきたニーズなどを把握しているからです。こうした情報は、より精度の高い便益整理につながります。
受注企業数が少ない場合の対処法
もしサービスが開始間もなく、受注企業数が潤沢でない場合(例えば20社以下など)、受注企業だけでは分析の精度が低くなってしまいます。
その場合は、以下のような企業も含めて情報整理することで、分析の精度を上げることができます。
- 商談化した企業:提案まで進んだが、最終的には受注に至らなかった企業
- 案件化した企業:金額提案や見積提出まで到達した企業
- 失注企業:競合に負けた企業(なぜ負けたのかの理由も記録する)
これらの企業の情報も含めることで、「どんな企業が興味を持ちやすいのか」「どんな企業は受注しにくいのか」といった傾向が見えてきます。
情報収集の実例
例えば、BtoB向けのWebマーケティング支援サービスを提供している企業の場合、以下のような情報を収集します。
| 企業名 | 業種 | 従業員数 | 担当者部署 | 契約プラン | 月額 | 導入前の課題 | 導入の決め手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 製造業 | 50名 | 営業部 | スタンダード | 30万円 | Web問い合わせが少ない | 製造業の実績が豊富だった |
| B社 | IT | 30名 | マーケ部 | プレミアム | 50万円 | リード獲得数を増やしたい | MA連携がスムーズだった |
| C社 | 小売業 | 100名 | 経営企画 | ライト | 15万円 | 広告費を削減したい | 低価格で始められた |
このように、一覧化することで、パターンが見えてきます。
ステップ2:分析のための並べ替えを行う
情報を一覧化したら、次は並べ替えや集計を行い、パターンを発見していきます。
ロイヤルカスタマー分析
ロイヤルカスタマー分析とは、売上単価の高い順に並べて、累積で全体の80%を占める企業を分析する手法です。これは、パレートの法則(80:20の法則)に基づいています。
具体的な手順は以下の通りです。
- 受注企業を売上単価(または年間契約金額)の高い順に並べる
- 累積売上を計算する
- 累積売上が全体の80%に達するまでの企業を抽出する
例えば、全20社の受注企業があり、年間売上が5,000万円だとします。売上上位5社で累積4,000万円(80%)に達したとしたら、この5社がロイヤルカスタマーです。
次に、この5社の共通点を分析します。
- 業種は何か?(5社中4社が製造業など)
- 従業員数は?(50名以上の企業が多いなど)
- 担当者の役職は?(部長以上が決裁しているなど)
- どんな課題を抱えていたか?(新規開拓に課題を感じていたなど)
このように、ロイヤルカスタマーの共通点を見つけることで、「売上単価が高くなりやすいターゲット群」が明確になります。
高受注率分析
高受注率分析とは、受注企業と全商談企業の割合の差分を見つけて、より受注率の高い企業群を見つける手法です。
具体的には、以下のように分析します。
例えば、過去1年間の商談企業が100社あり、そのうち受注に至ったのが20社だとします。
全体の受注率は20%です。しかし、業種別に見ると以下のような違いがあるかもしれません。
| 業種 | 商談数 | 受注数 | 受注率 |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 30社 | 10社 | 33% |
| IT | 20社 | 6社 | 30% |
| 小売業 | 25社 | 3社 | 12% |
| サービス業 | 25社 | 1社 | 4% |
この分析から、製造業とITは平均以上の受注率であり、小売業とサービス業は平均以下であることがわかります。
製造業やITにアプローチすれば、効率的に受注を増やせる可能性が高いです。一方、小売業やサービス業は、アプローチ方法を見直すか、そもそもターゲットから外すかを検討する必要があります。
失注が多い企業群からの学び
高受注率分析の逆も重要です。つまり、失注が多い企業群を分析することで、改善のヒントが得られます。
例えば、小売業の受注率が低い理由を深掘りすると、以下のような仮説が立てられます。
- 小売業は予算が限られており、価格がネックになっている
- 小売業に適した機能が不足しており、競合に負けている
- 小売業向けの事例が少なく、信頼を得られていない
このような仮説を元に、価格プランの見直しや、機能追加、事例作りなどの改善策を検討できます。
その他の分析軸
売上単価や受注率以外にも、以下のような軸で分析することができます。
- 契約継続率:どの企業群が長く契約を継続しているか
- アップセル率:どの企業群が上位プランにアップグレードしやすいか
- 紹介率:どの企業群が他社を紹介してくれやすいか
- 導入期間:どの企業群が導入決定までのスピードが早いか
これらの分析を通じて、自社にとって「理想的な顧客像」が浮かび上がってきます。
ステップ3:Who、What、独自性をまとめる
分析を通じてパターンが見えてきたら、ターゲット群ごとに以下の3つの要素をまとめます。
Who:企業属性と担当者属性
企業属性
- 業種:製造業(特に部品メーカー)
- 従業員数:30名〜100名
- 売上高:年商3億円〜10億円
- 地域:関東・中部地方
担当者属性
- 部署:営業部、経営企画部
- 役職:部長、課長
- 決裁権:あり(または、社長への上申が通りやすい)
このように、企業属性だけでなく、担当者属性まで明確にすることが重要です。なぜなら、同じ業種・規模の企業でも、担当部署が違えば、抱えている課題や求めている価値が異なるからです。
例えば、同じ製造業でも、営業部が主導で導入する場合と、経営企画部が主導で導入する場合では、重視するポイントが違います。
- 営業部主導:「新規顧客の獲得数」を重視
- 経営企画部主導:「全社的な営業効率の向上」を重視
このように、担当者属性まで分類することで、より精度の高いターゲティングが可能になります。
What:何に価値を感じているか
次に、そのターゲット群が「何に価値を感じているか」を明確にします。
具体的には、以下のような情報を整理します。
導入前の課題
- 新規顧客の獲得が頭打ちになっている
- 営業担当者によって成果にばらつきがある
- Webからの問い合わせが少ない
求めている成果
- 月間の新規問い合わせ数を2倍にしたい
- 営業の商談数を増やしたい
- 営業担当者の負担を減らしたい
導入によって得られた価値
- 月間問い合わせ数が10件から25件に増加した
- 商談数が月20件から35件に増えた
- 営業担当者がリスト作成に使っていた時間が半減した
このように、課題→求める成果→実際の成果という流れで整理すると、「このターゲット群にとっての価値」が明確になります。
独自性:なぜ自社が選ばれたのか
最後に、競合他社や他の選択肢と比べて、なぜ自社が選ばれたのかを整理します。これが「独自性」です。
例えば、以下のような理由があるかもしれません。
- 実績:製造業での支援実績が豊富だった
- 専門性:BtoB営業に特化したノウハウがあった
- 対応力:地方拠点でも訪問対応が可能だった
- 価格:競合よりも低価格で始められた
- 機能:既存のMAツールとスムーズに連携できた
- サポート:導入後の伴走支援が手厚かった
独自性を把握することで、営業やマーケティングで訴求すべきポイントが明確になります。
ターゲット群の数
1サービス内に、5〜10個程度のターゲット群が含まれていると言われています。しかし、最初の分析では、2〜5個まとめられるだけでも十分です。
無理にすべてのパターンを網羅しようとせず、まずは明確に見えているターゲット群から整理していきましょう。事業が成長し、顧客数が増えていけば、より細かな分類ができるようになります。
便益整理の具体例
例えば、Webマーケティング支援サービスの場合、以下のようなターゲット群が浮かび上がるかもしれません。
ターゲット群1:製造業の新規開拓強化型
- Who(企業):製造業、従業員30〜100名、年商3億〜10億円、関東・中部地方
- Who(担当者):営業部長、経営企画部長
- What(課題):新規顧客の獲得が頭打ち、展示会以外の集客方法がない
- What(価値):Web経由の問い合わせ数が月10件→25件に増加
- 独自性:製造業での支援実績が豊富、専門用語を理解している
ターゲット群2:IT企業のリード育成型
- Who(企業):IT・SaaS企業、従業員10〜50名、創業3年以内、全国
- Who(担当者):マーケティング担当者、事業責任者
- What(課題):リードは獲得できているが、商談化率が低い
- What(価値):MAツールとの連携で、リード育成が自動化され、商談化率が15%→30%に向上
- 独自性:MAツールとのスムーズな連携、IT業界特有の商談プロセスへの理解
ターゲット群3:地方企業の初めてのWeb活用型
- Who(企業):地方の中小企業、従業員10〜30名、業種は問わず、地方都市
- Who(担当者):経営者、総務担当者
- What(課題):Webマーケティングを始めたいが、何から手をつけていいかわからない
- What(価値):基礎から丁寧にサポートしてもらい、初めてのWeb広告で月5件の問い合わせ獲得
- 独自性:地方でも訪問対応可能、初心者向けの丁寧なサポート、低価格プランあり
このように、Who、What、独自性を整理することで、それぞれのターゲット群に刺さる提案ができるようになります。
便益整理の営業・マーケティングへの活用
便益整理ができたら、それを営業活動やマーケティング施策に活用していきます。
優先営業先のリストアップ
まず、まだ受注や商談に至っていない企業の中から、同じようなターゲット群に該当する企業をリストアップします。
例えば、「製造業の新規開拓強化型」が受注率が高いとわかったら、以下のような条件でリストを作成します。
- 業種:製造業
- 従業員数:30〜100名
- 地域:関東・中部地方
- 未商談または失注から半年以上経過している企業
このリストに対して、優先的にアプローチすることで、効率的に受注を増やすことができます。
ターゲット群に合わせた提案ストーリー
便益整理ができていれば、ターゲット群ごとに最適化された提案ができます。
具体的には、以下のような要素をカスタマイズします。
1. 課題の共感
最初に、相手が抱えている課題に共感を示します。
例:「製造業の企業様からよくお聞きするのが、展示会以外の新規開拓方法が見つからないというお悩みです。御社も同じような課題を感じていらっしゃいますか?」
同じターゲット群の典型的な課題を挙げることで、「この人は自分たちの状況を理解している」と感じてもらえます。
2. 解決策のストーリー提案
次に、その課題をどう解決するかをストーリーで伝えます。
例:「製造業の場合、専門的な製品を扱っているため、一般的なWeb広告では効果が出にくいです。そこで、業界特化型のメディアへの広告出稿や、技術情報を発信するコンテンツマーケティングを組み合わせることで、質の高い問い合わせを獲得できます。」
一般論ではなく、そのターゲット群に特化した解決策を提示することで、説得力が増します。
3. 適切な事例の紹介
最後に、同じターゲット群の成功事例を紹介します。
例:「実際に、部品メーカーのA社様では、同様のアプローチで、月間問い合わせ数が10件から25件に増加し、そのうち5件が商談化、2件が受注につながりました。」
同じような企業属性、同じような課題を持つ企業の事例を紹介することで、「自社でも実現できそう」と感じてもらえます。
アウトバウンド営業での活用
便益整理は、アウトバウンド営業(テレアポ、メール営業、フォーム営業など)でも活用できます。
例えば、メール営業の文面を、ターゲット群ごとに作り分けます。
製造業向けの文面例
件名:【製造業向け】展示会以外の新規開拓方法のご提案
〇〇株式会社
営業部長 様
突然のご連絡失礼いたします。
〇〇(自社名)の△△と申します。
製造業の企業様から、「展示会以外の新規開拓方法が見つからない」というお悩みをよくお聞きします。
弊社では、製造業に特化したWebマーケティング支援を行っており、部品メーカーのA社様では、月間問い合わせ数が10件から25件に増加した実績がございます。
もしご興味があれば、15分ほどのオンライン相談にて、具体的な施策例をご紹介させていただけますでしょうか。
(以下略)
このように、ターゲット群の課題、解決策、事例を盛り込んだ文面を作ることで、返信率や商談化率を高めることができます。
広告のターゲティングとクリエイティブ
Web広告においても、便益整理は非常に有効です。
ターゲティング
例えば、Facebook広告やLinkedIn広告では、以下のような条件でターゲティングできます。
- 業種:製造業
- 企業規模:従業員数30〜100名
- 役職:部長、課長、経営者
- 地域:関東、中部地方
便益整理で明確になったターゲット群の条件を、そのまま広告のターゲティング設定に反映できます。
クリエイティブ(広告文・バナー)
広告の訴求内容も、ターゲット群に合わせて最適化します。
製造業向けの広告文例: 「展示会以外の新規開拓方法にお悩みの製造業様へ。Web経由の問い合わせを月10件→25件に増やした方法をご紹介します。」
IT企業向けの広告文例: 「リードは獲得できているのに商談化率が低い…。MAツール連携で商談化率を15%→30%に改善した事例をご紹介します。」
このように、ターゲット群ごとに刺さる訴求を行うことで、広告のクリック率やコンバージョン率を高めることができます。
便益整理のプロダクト開発への活用
便益整理は、営業やマーケティングだけでなく、プロダクト開発やサービス改善にも活用できます。
誰のための改善かを明確にする
サービス改善を行う際、「誰のための改善なのか」を明確にすることが重要です。便益整理ができていれば、ターゲット群を定量的に把握できているため、改善の優先順位をつけやすくなります。
例えば、以下のような改善要望が上がってきたとします。
- A機能の追加(製造業の顧客から要望が多い)
- B機能の改善(IT企業の顧客から要望が多い)
- C機能の新規開発(地方企業の顧客から要望がある)
この場合、どの改善を優先すべきでしょうか?便益整理ができていれば、以下のような判断ができます。
- 製造業の顧客が売上の50%を占めている → A機能を優先
- IT企業の顧客は数は少ないが、売上単価が高く、成長余地がある → B機能を優先
- 地方企業の顧客は受注率が低く、今後の注力対象ではない → C機能は後回し
このように、ターゲット群の重要度を踏まえて、改善の優先順位をつけることができます。
ちぐはぐな改善を防ぐ
便益整理ができていないと、異なるターゲット群のニーズが混在し、ちぐはぐなサービスになってしまうことがあります。
例えば、以下のような状況です。
- 製造業向けには、専門的で高度な機能が求められている
- 地方企業向けには、シンプルで使いやすい機能が求められている
この2つを同時に満たそうとすると、どちらにとっても中途半端なサービスになってしまいます。
便益整理ができていれば、「製造業向けのプレミアムプラン」と「地方企業向けのライトプラン」というように、ターゲット群ごとにサービスを分けるという判断ができます。
社内の目線を合わせる
便益整理の結果を、営業、マーケティング、プロダクト開発、カスタマーサクセスなど、社内の各部門で共有することで、目線を合わせることができます。
例えば、四半期に一度、便益整理の結果を更新し、全社ミーティングで共有します。
- 現在の主要ターゲット群は3つ
- それぞれのターゲット群の売上比率、受注率、契約継続率
- 各ターゲット群が求めている価値と、自社の独自性
- 今四半期の注力ターゲットと、そのための施策
このように、定量的なデータを元に議論することで、「なんとなく」ではなく、「データに基づいた」意思決定ができるようになります。
まとめ:便益整理は事業成長の起点
便益整理は、一度やったら終わりではありません。事業が成長し、顧客数が増えていく中で、定期的に見直し、アップデートしていく必要があります。
便益整理を行うことで、以下のような効果が得られます。
営業活動の効率化
- 受注率の高いターゲット群に絞ってアプローチできる
- ターゲット群に合わせた提案ストーリーを作れる
- 適切な事例を紹介できる
マーケティング施策の精度向上
- 広告のターゲティングを最適化できる
- ターゲット群ごとに刺さるクリエイティブを作れる
- 無駄な広告費を削減できる
プロダクト開発の方向性の明確化
- 誰のための改善かを明確にできる
- ちぐはぐな改善を防げる
- 社内の目線を合わせられる
便益整理は、「なんとなく」営業するのではなく、「戦略的に」顧客を獲得していくための起点となる重要な作業です。
特に、地方企業においては、限られたリソースの中で効率的に成果を出す必要があります。便益整理を通じて、「誰に、何を、どう伝えるか」を明確にすることで、少ないリソースでも大きな成果を上げることができます。
まだ便益整理を行っていない方は、ぜひ本記事で紹介した手順を参考に、取り組んでみてください。最初は2〜3個のターゲット群を整理するだけでも、営業やマーケティングの精度が大きく変わります。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。