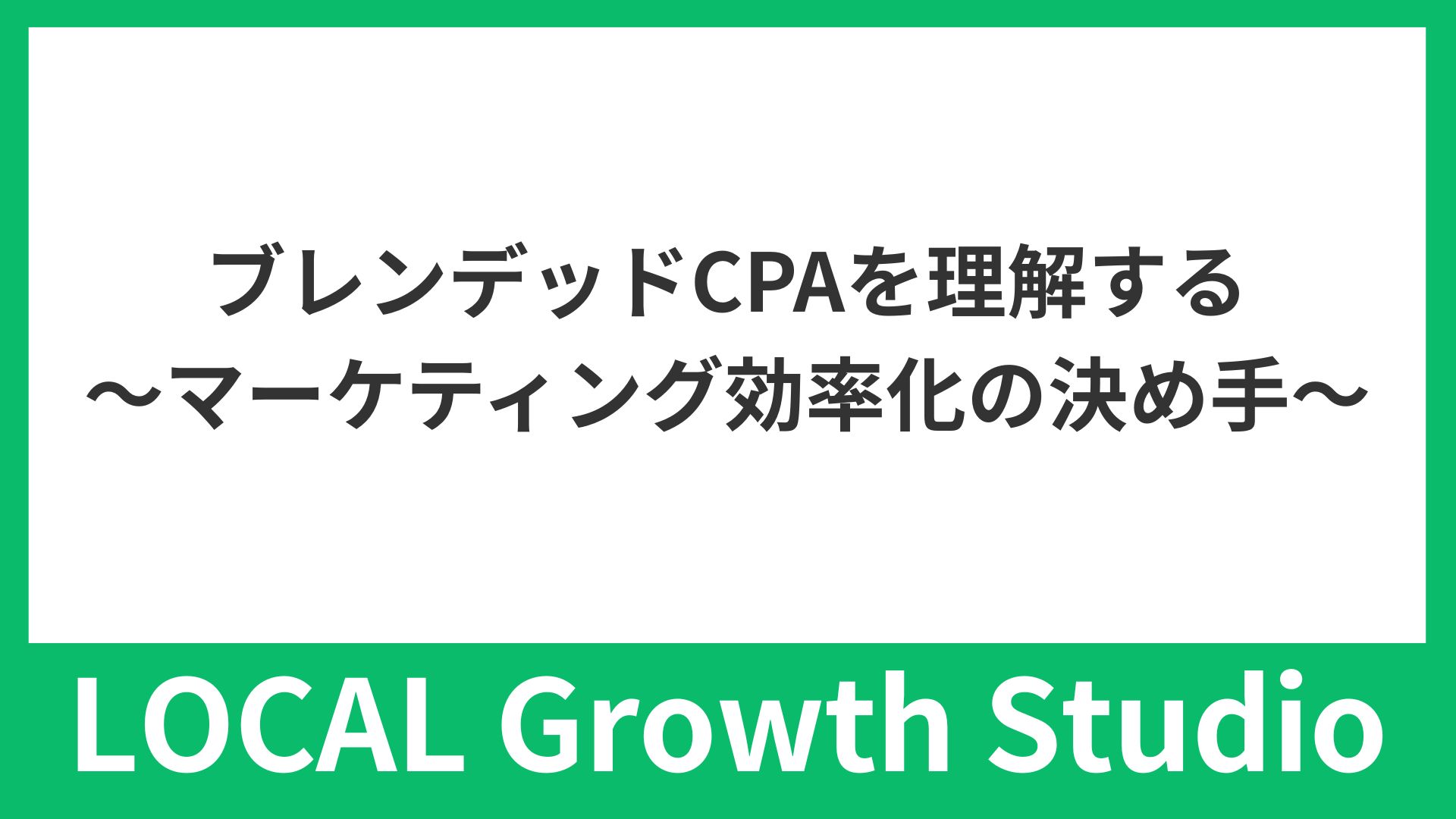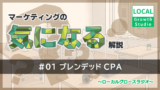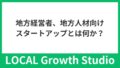ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
この記事は、「ブレンデッドCPAを理解する~マーケティング効率化の決め手~」について記載しています。
この記事はポッドキャストでも音声解説を行っております。各種サイトで無料で聞くことができます。
なぜブレンデッドCPAが重要なのか
「広告費が高すぎて、利益が出ない…」
「もっと効率的に集客できないか…」
このような悩みは、マーケティング担当者なら誰もが一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。地方企業の経営者の方々からは、特に「限られた予算でどう効率的に集客すべきか」という相談をよく受けます。
実は、顧客獲得コスト(CPA:Cost Per Acquisition)は、単一のチャネルだけを見ていては本質が見えてこないのです。広告、紹介、自然流入など、すべての獲得チャネルを総合的に見る。つまり「ブレンデッド(総合的)」な視点で捉える必要があるのです。
多くの経営者から「広告は高いけど効果がわからない」という声を聞きますが、その悩みの根本には、チャネル全体を俯瞰して見る視点が欠けていることが多いのです。地方企業でも活用できるノウハウとして、まずはこのブレンデッドCPAの基本から理解していきましょう。
ブレンデッドCPAの基本
ブレンデッドCPAとは、すべての獲得チャネルを合わせた平均獲得コストのことです。具体例で見てみましょう。
ある月の新規獲得100件の内訳が以下のようになっていたとします:
- リスティング広告:40件(1件3万円)
- SNS広告:30件(1件2.5万円)
- オーガニック流入:30件(コスト0円)
この場合の計算式は:
- 広告費総額:(40件×3万円)+(30件×2.5万円)= 195万円
- 総獲得件数:100件
- ブレンデッドCPA:195万円÷100件 = 1.95万円
つまり、1件あたりの平均獲得コストは約1.95万円になるのです。これが「ブレンデッドCPA」です。
チャネル間の相互作用を分析すると、例えばリスティング広告を行うことでオーガニックのWEBサイト流入のコンバージョン率が向上するなど、複合的な効果がある場合があります。これは規模の小さな地方企業でも把握して取り組む必要がある内容です。
許容CPAをどう考えるか
では、どの程度のCPAまでなら許容できるのでしょうか。
一般的な考え方として、顧客生涯価値(LTV:Life Time Value)の1/3以下が目安となります。この考え方をユニットエコノミクスと呼び、LTV>CPA×3などの数式でコスト管理を行っていきます。
具体的な例を見てみましょう:
BtoBサービスの場合
- 月額単価:10万円
- 想定契約期間:24ヶ月
- 粗利率:70%
- LTV計算:10万円×24ヶ月×70% = 168万円
- 許容CPA:168万円÷3 = 56万円以下
EC事業の場合
- 平均購入単価:1万円
- 年間購入回数:3回
- 継続年数:2年
- 粗利率:30%
- LTV計算:1万円×3回×2年×30% = 1.8万円
- 許容CPA:1.8万円÷3 = 6,000円以下
多くの企業の支援を行う中で痛感したのは、「許容CPA」を明確に設定していない企業が非常に多いということです。そのため、費用対効果を正確に測定できず、経営判断が感覚的になりがちなのです。
特に地方企業では、マーケティングの投資対効果に対する不安が大きいと感じています。しかし、このように数字で明確に「いくらまでなら投資していい」という基準を持つことで、経営判断の精度が格段に上がるのです。実際に、地方企業の支援において、こうした数値基準を導入した企業は、マーケティング投資に対する心理的障壁が下がり、積極的な施策展開につながったケースが多いのです。
チャネル分析とその特徴を理解する
では、具体的なチャネルの分類と、それぞれの特徴を見ていきましょう。
獲得チャネルは、大きく5つに分類できます:
1. ペイドメディア(広告)
- リスティング広告
- SNS広告
- ディスプレイ広告
コストは高いが、即効性があり、スケールしやすいのが特徴です。地方企業でも取り組みやすいチャネルですが、継続的な予算確保が必要です。
2. アーンドメディア(成果報酬)
- アフィリエイト
- セールスパートナー
- 紹介報酬制度
実績に応じた支払いのため、コストコントロールがしやすいのが特徴です。初期投資を抑えたい企業に向いています。
3. リファラル(紹介)
- 既存顧客からの紹介
- 取引先からの紹介
- 専門家からの推薦
信頼性が高く、成約率も高いのが特徴です。特に地方企業では、地域内のつながりを活かしたリファラル施策が効果的です。
4. アウトバウンド(営業)
- テレアポ
- ダイレクトメール
- FAX施策
人的リソースは必要だが、ターゲットを絞った接触が可能です。既存の営業リソースを活用できる点が地方企業にとってのメリットです。
5. オーガニック(自然流入)
- SEO対策
- コンテンツマーケティング
- SNSでの情報発信
初期投資は必要ですが、長期的にはコストが低く抑えられます。地方企業こそ、独自性のあるコンテンツ発信によって差別化できる可能性があります。
多くの企業で「広告出稿=マーケティング」と考えているケースがあります。しかし実際には、これらの5つのチャネルをバランスよく組み合わせることで、より効率的な集客が実現するのです。特に予算に限りがある地方企業こそ、複数チャネルの特性を理解し、最適な組み合わせを見つけることが重要なのです。
チャネル別のLTV分析
重要なのは、チャネルごとにLTVが異なる点です。これは多くの企業が見落としがちな視点です。
例えば、以下のような違いが出ることがあります。(数値は参考)
1. リファラル経由
既存顧客からの紹介のため、サービスの価値を理解した見込み顧客と契約することができ、高いLTV(高単価・高継続率)の新規顧客となった。
- 平均契約期間:36ヶ月
- 月額単価:15万円
- LTV:540万円
2. リスティング広告経由
リスティングという一定の目的検索の流入のため、サービスの理解度が高い新規顧客となった。
- 平均契約期間:18ヶ月
- 月額単価:12万円
- LTV:216万円
3. SNS広告経由
キャッチーな画像や動画でひきつけ、新規契約を行ったが、サービス理解度が低い状態から商談がスタートし、相対的に低LTVな新規顧客となった。
- 平均契約期間:12ヶ月
- 月額単価:10万円
- LTV:120万円
このように、獲得チャネルによって顧客の質が大きく異なることがあるのです。ある企業支援の事例では、既存顧客の分析から顧客ニーズ別のサポート手法を設計したところ、チャネル別のLTV差異が明らかになりました。その結果をマーケティング戦略にフィードバックすることで、投資効率が大幅に向上したのです。
地方企業においても、「とにかく顧客を獲得する」という発想から一歩進んで、「質の高い長期顧客を獲得する」という視点が重要です。むしろ地方企業こそ、限られた顧客基盤を大切にし、LTVを最大化する戦略が欠かせません。そのためには、チャネル別のLTV分析が不可欠なのです。
チャネル別の獲得属性を理解する
さらに、チャネルごとに獲得できる顧客層の特徴も異なってきます。これを理解することで、ターゲット層に合わせた効果的なチャネル選択が可能になります:
1. リスティング広告
- 課題意識が明確
- 情報収集を能動的に実施
- 比較検討を行う傾向
2. SNS広告
- 潜在的な興味関心層
- 情緒的な訴求が効果的
- 認知からの育成が必要
3. オーガニック(SEO)
- 専門性の高い情報を求める層
- 重点のキーワード検索において流入が見込める
- 昨今はAI検索の発達により、AIOへの最適化も求められている
ある事業では、全顧客インタビューを見直し、チャネル別に顧客特性を分析して便益整理(Who, What, 独自性)を行いました。その結果、ターゲット属性の認識統一ができ、マーケティング施策の精度が向上したのです。
地方企業の場合、商圏が限られているからこそ、効率的なターゲティングが重要です。チャネル別の顧客特性を理解することで、限られたリソースを最適に配分することができるのです。これはコスト効率に敏感な地方企業にとって、特に重要な視点と言えるでしょう。
チャネルポートフォリオの設計と予算管理
ここからが実践的な予算管理の話です。
まず、現状のブレンデッドCPAを把握することから始めましょう。多くの企業では、以下のような課題に直面します:
1. 現状の把握
- 広告費:月間300万円
- 新規獲得:50件
- 現在のブレンデッドCPA:6万円
- 目標のブレンデッドCPA:4万円
このとき、大きなギャップが見えてきます。しかし、「予算を増やす」という安易な解決策は、必ずしも正しくありません。むしろ、チャネルミックスを最適化することで、同じ予算でも効率を上げることが可能なのです。
中長期的な改善のアプローチ
ここで重要になってくるのが、オーガニック施策の強化です。広告だけに頼らない集客基盤を作ることが、中長期的なCPA改善の鍵となります。
1. コンテンツマーケティング
- 業界知識の体系的な発信
- ユーザーの悩みに応える記事作成
- 専門性の高い情報提供
2. 共催ウェビナー
- パートナー企業との協業
- 相互送客の仕組み作り
- コスト分散のメリット
3. プレスリリース・メディア露出
- 業界メディアとの関係構築
- ニュース性のある情報発信
- 認知度向上の施策
これらは、すぐには効果が出にくいものの、長期的に見ると非常に効率の良い獲得チャネルとなります。一過性のコスト消化ではなく、ストック的な価値として、キーワード流入や被リンクの獲得という複利的な効果を生み出します。
地方企業でも、自社の強みや地域性を活かしたコンテンツ発信は十分に可能です。むしろ、地域に根差した独自の視点があることが、大手企業には真似できない差別化要因になり得るのです。地域の特産品や観光資源、地元の人にしか分からない情報など、地方ならではのコンテンツは、実はオーガニック集客において大きな武器になります。
具体的な予算配分の例
月間予算300万円の場合の配分例:
- 広告費:月間300万円
- 新規獲得:50件
- 現在のブレンデッドCPA:6万円
- 目標のブレンデッドCPA:4万円
上記を分解すると、
ペイドチャネル:CPA 10万円×30件、オーガニックチャネル:CPA 0万円×20件
という配分になっているケースが多くあります。
ここで行うことは、ペイドチャネルの最適化(10万円をさらに下げられる広告手法はないか?)と、オーガニックチャネルの成長(コンテンツ追加や被リンク追加)の2つになります。
現状使っている予算を見直し、300万円を広告だけに使うのではなく、長期的なオーガニックチャネル増加に予算投下を検討していく流れになります。一時的に成果にバラつきがでる可能性がありますが、事業計画を見越した判断が必要です。
ある企業支援では、マーケティングからカスタマーサクセスまでのユニットエコノミクスの精緻化に取り組みました。チャネル別のCACを算出し、再現性の高い販路を特定してリソースを集中投下したのです。こうした分析に基づく予算配分が、効率的なマーケティングの鍵となります。地方企業においても、限られたリソースをどこに集中させるべきかを判断するためには、このような分析が欠かせないのです。
PDCAを回すためのポイント
ブレンデッドCPAの改善は、一度の施策で完結するものではありません。継続的なモニタリングと改善のサイクルを回すことが重要です。
1. 週次でのモニタリング
- チャネル別の獲得数
- CPAの推移
- 予算消化状況
2. 月次での振り返り
- LTVの確認
- チャネル別の分析
- 予算配分の見直し
3. 四半期での改善
- 新規チャネルの開拓
- 効果検証と判断
- 中長期施策の進捗確認
特に重要なのは、単なる数字の追跡ではなく、「なぜその結果になったのか」という深堀りと、「次にどう改善するか」という行動計画までを含めたPDCAサイクルです。
地方企業では、専任のマーケティング担当者がいないケースも多いですが、こうした基本的なモニタリングと改善のサイクルを確立することで、限られたリソースでも効果的なマーケティングを実現することができるのです。経営者自身が週に1時間でも時間を取り、このサイクルを回すことで、マーケティング効率は着実に向上していきます。
成功のための3つのポイント
最後に、ブレンデッドCPAを活用したマーケティング効率化の成功ポイントをまとめておきます。
1. 全体最適を考える
単一チャネルの効率だけでなく、ブレンデッドCPAとして全体最適を目指すことが重要です。チャネル間の相互作用も考慮に入れましょう。
2. 時間軸を意識する
即効性のある施策と、じっくりと育てる施策のバランスを取ることが大切です。短期的な成果と長期的な基盤づくりの両方に投資しましょう。
3. 継続的な改善
定期的な効果検証と改善のサイクルを回し続けることで、徐々に効率は上がっていきます。一朝一夕ではなく、継続的な取り組みがブレンデッドCPAの改善につながるのです。
「安定的な集客が実現できない」「広告費が高騰している」といった課題を抱える企業は多いはずです。特に地方企業では、限られたリソースの中で最大限の効果を出すことが求められます。
しかし、このようにチャネルポートフォリオを整理し、中長期的な視点で改善を続けることで、必ず道は開けます。私たちは、この「ブレンデッドCPA」の考え方によって多くの企業が成果を上げるのを見てきました。
マーケティングは短期的な勝負ではなく、長期的な基盤づくりです。目先の成果に一喜一憂するのではなく、この記事で解説したような体系的なアプローチで取り組んでいただければ幸いです。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。