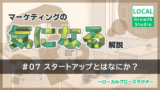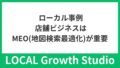ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
この記事は、「地方経営者、地方人材向け:スタートアップとは何か?」について記載しています。
この記事はポッドキャストでも音声解説を行っております。各種サイトで無料で聞くことができます。
スタートアップとは何か
「スタートアップ」という言葉を聞いたとき、どのようなイメージを持つでしょうか?若い起業家たちが新しいアイデアで事業を始める様子を思い浮かべるかもしれません。あるいは、IT企業のような新しい会社を想像するかもしれません。確かにそれは間違いではありませんが、スタートアップとはもう少し特定の意味を持つ言葉なのです。
スタートアップとは、短期間で急成長することを前提とした事業の仕組みを持つ会社のことを指します。単に「新しく始まった会社」「若い会社」という意味ではありません。重要なのは、その「成長志向」と「スピード感」なのです。
スタートアップの世界では、通常8〜10年という時間軸で、外部からお金を集めながら急成長を目指し、最終的には株式を市場に公開したり(上場)、大きな企業に買ってもらったりすることが一般的です。この8〜10年という期間は偶然ではなく、スタートアップに投資するベンチャーキャピタル(VC)のファンド償還期限と一致しています。つまり、投資家側は8〜10年以内に投資金額の何倍もの見返りを得ることを期待しているのです。
このような背景から、スタートアップは「時間をかけて少しずつ成長する」のではなく、「短期間で一気に大きくなる」ことを目指します。例えば、数年間で売上を数十倍〜100倍以上に成長させることが求められます。近年ではグロース市場などでの上場において時価総額数十億円の事例も増えていますが、投資家からの期待値としては大きな成長が求められるのが一般的です。
この考え方でいくと、例えば地元で開いた小さな小売店や飲食店は、それが新しくできた会社であっても、必ずしも「スタートアップ」とは呼ばれません。なぜなら、多くの場合、こうした会社は地域に根を張った安定した経営を目指しており、急激な成長や全国展開、ましてや世界展開を前提としていないからです。
ただし、注意すべきは「新しい事業だからスタートアップ」「IT企業だからスタートアップ」「若者が始めたからスタートアップ」といった単純な分け方ではないということです。あくまでも「短期間での急成長」と「外部からのお金集めを前提とした事業の仕組み」に特徴があるのです。
スタートアップの特徴
では、スタートアップには具体的にどのような特徴があるのでしょうか。
1. 短期間での急成長を目指す
先に説明した通り、スタートアップの最大の特徴は「短期間での急成長」を目指すことです。設立から数年で従業員数や売上を数十倍、場合によっては100倍以上に伸ばすことを目標とします。これは、お金を出してくれる投資会社(ベンチャーキャピタル)が期待する見返りを実現するために必要な成長の速さです。
例えば、ベンチャーキャピタルは投資額の10倍、20倍のリターンを期待することも珍しくありません。そのために、スタートアップは通常の会社とは桁違いのスピードで成長する必要があるのです。
2. 外部からお金を集めることを前提とした事業の組み立て
スタートアップは通常、自分のお金や銀行からの借入(デット)だけでなく、個人投資家や投資会社からお金(エクイティ投資)を集めます。この「外部からのお金集め」という点が重要です。銀行からの借入(デット)との大きな違いは、返済する必要がない代わりに会社の株式(つまり会社の所有権の一部)を渡すことにあります。
このエクイティ投資を前提とした事業設計では、投資家が求める「急成長」と「出口戦略(Exit)」を組み込む必要があります。つまり、どのように短期間で大きく成長し、どのように投資家に見返り(リターン)を提供するかを最初から考えておく必要があるのです。
3. 新しさや革新性のある事業
スタートアップはたいてい、今ある市場に新しい価値を提供するか、あるいは全く新しい市場を作り出すことを目指します。単に今あるビジネスの真似ではなく、何らかの新しさや革新性を持っていることが多いのです。これが事業を大きく広げる可能性を高めます。
革新性があるからこそ、短期間で市場を席巻したり、新しい市場を創造したりすることが可能になります。また、この革新性によって参入障壁が生まれ、競合他社に対する優位性を確保できるのです。
4. 高いリスクと高いリターン
スタートアップは、成功すれば大きな価値を生み出す可能性がある一方で、失敗するリスクも非常に高い事業です。統計的には、立ち上げられたスタートアップの90%以上が失敗するとも言われています。この「リスクが高い代わりに成功したら大きなリターンがある」という性質がスタートアップの本質的な特徴です。
投資家はこのハイリスク・ハイリターンの性質を理解した上で、複数のスタートアップに分散投資します。多くのスタートアップが失敗しても、一部の大成功企業で全体の投資を回収する以上のリターンを得る「ポートフォリオ戦略」を取るのです。
5. 素早い決断と柔軟な組織
スタートアップは市場や顧客の要望に素早く対応するため、決断の速さを重視します。また、状況の変化に応じて事業内容や進め方を柔軟に変える「方向転換(ピボット)」も珍しくありません。
これらの特徴からも分かるように、スタートアップは「安定」より「成長」を、「堅実さ」より「挑戦」を大事にする会社の文化を持っているのです。
スタートアップの成長段階
スタートアップは成長に合わせていくつかの段階に分けられます。これらの段階はお金を集める回数(ファイナンスラウンド)とも深く関係しています。
タネまき段階(シード段階)
まさに「種をまく」という意味のタネまき段階は、会社を始めたばかりの最初の段階です。この時点では、事業のアイデアや試作品はあるものの、本格的な商品やサービスはまだできていないことが多いです。数人の創業メンバーだけで活動していることもよくあります。
お金の集め方としては、創業者の自分のお金や、友人・家族からのお金、個人投資家(エンジェル投資家)からの投資など、比較的小さな額のお金を集めることが一般的です。タネまき段階として数百万円から数千万円程度のお金を集めることが多いでしょう。
この段階での最大の課題は、事業の仕組みが本当に成り立つかを確かめること(Proof of Concept)と、最初の商品・サービスを作ることです。
初期段階(アーリー段階)
初期段階では、商品やサービスが形になり、市場に出始めます。最初のお客さんを獲得し、事業の仕組みが実際に機能することを証明することが焦点となります。
お金の集め方としては、「シリーズA」と呼ばれる本格的な投資会社からの投資が行われることが多くなります。数千万円から数億円規模のお金集めが一般的です。
初期段階での主な課題は、商品と市場がうまく合うかどうか(PMF:プロダクト・マーケット・フィット)を確認し、成長の軌道に乗せることです。この段階では、組織も大きくなり始め、創業メンバー以外の人の採用が活発になります。
中期段階(ミドル段階)
中期段階のスタートアップは、事業の仕組みが証明され、安定した売上を上げ始めています。市場での立ち位置が確立され、成長の速さも高い水準を保っています。
お金の集め方としては、「シリーズB」や「シリーズC」と呼ばれる比較的大きな投資ラウンドを行います。数億円から数十億円規模のお金集めが行われることが一般的です。
この段階での主な課題は、事業を大きく広げること(スケーリング)です。事業の規模を急速に拡大し、市場での占有率を高めることが求められます。また、組織としての土台も強化され、専門的な役割を持つ人が増えます。
後期段階(レイター段階)
後期段階は、スタートアップが成熟期に入った段階です。市場での地位が確立され、安定した収益の土台を持っています。株式を公開したり(IPO)、大きな企業に買収されたり(M&A)する出口戦略が視野に入ってきます。
お金の集め方としては、「シリーズD」や「シリーズE」、あるいは株式公開前の最後の投資ラウンド(プレIPOラウンド)と呼ばれる大規模な投資が行われることがあります。数十億円から数百億円規模のお金集めも珍しくありません。
この段階での主な課題は、長く続けられる成長の仕組みの確立と、出口戦略の実行です。株式公開に向けた体制整備や、買収のための魅力的な会社の価値の創出が焦点となります。
これらの段階は連続的であり、はっきりとした境界線があるわけではありません。また、すべてのスタートアップがこれらの段階を順調に進むわけではなく、途中で挫折したり、方向転換を余儀なくされることも少なくありません。
外部からお金を集める方法
スタートアップの特徴的な要素の一つが、外部からのお金集めです。ここでは、その主な方法について説明します。
エクイティ(株式)による資金調達
エクイティ調達とは、会社の株式(所有権の一部)を投資家に売ってお金を集める方法です。これは、スタートアップにとって最も一般的なお金の集め方です。
エクイティ調達の特徴は、以下の通りです:
- 返す必要がない(配当金を出すことはあるが必ず出さなければならないわけではない)
- 投資家は会社の一部の所有権(株式)を得る
- 会社の価値(バリュエーション)に基づいて投資額と株式の割合が決まる
- 投資家は株式を売ることで利益を得ることを期待する
エクイティ調達は、特に初期段階のスタートアップにとって重要です。なぜなら、この段階では売上が少なく、借金を返す能力が限られているからです。また、大きく成長するための資金を確保できるため、急成長を目指すスタートアップに向いています。
エクイティ調達の主な相手先には、以下のようなものがあります:
- エンジェル投資家: 個人でお金を出す裕福な人たち。主にタネまき段階のスタートアップにお金を出します。
- ベンチャーキャピタル(VC): 機関投資家や裕福な人から集めたお金でスタートアップに投資する会社。通常、初期段階から後期段階までの幅広い段階に投資します。
- コーポレートベンチャーキャピタル(CVC): 大企業が作る投資部門。自社の事業との相乗効果が見込める場合に投資することが多いです。
デット(借入金)による資金調達
デット調達は、お金を借りることでの資金調達です。銀行融資やローンがこれに該当します。デット調達の特徴は、以下の通りです:
- 返す義務がある(利息も含む)
- お金を貸した相手は会社の所有権を得ない
- 会社の信用力や担保に基づいて借りられる額が決まる
- お金を貸した相手は利息という形で一定の見返りを得る
デット調達は、特に以下のような場合に適しています:
- すでに安定した売上があり、返す能力が十分にある場合
- 所有権の薄まり(希薄化・ダイリューション)を避けたい場合
- 特定の設備購入など、はっきりとした使い道がある場合
スタートアップがデット調達を行う主な相手先には、以下のようなものがあります:
- 銀行: 一般的な金融機関からの借入。通常、ある程度の実績や担保が必要です。
- ベンチャーデット: スタートアップ向けの専門融資。通常の銀行融資よりも柔軟な条件で提供されることが多いです。金利は高めですが、成長性を評価して融資を行います。
- 株式転換型の借入(転換社債): 最初は借金として始まり、特定の条件(例:次の株式発行時)で自動的に株式に変わる仕組み。
エクイティとデットはそれぞれ特徴が異なり、スタートアップの成長段階や状況によって最適な選択は変わります。多くのスタートアップは、成長の過程でこれらを組み合わせたお金集めの戦略を取っています。また、最近では、これら以外にも「クラウドファンディング」など様々なお金の集め方が出てきています。
スタートアップを取り巻く環境
日本におけるスタートアップの環境は、近年急速に整ってきました。特に注目すべきは、政府が進めるスタートアップ支援策の充実です。
日本のスタートアップ政策
2022年11月に閣議決定された「スタートアップ育成5か年計画」は、2027年までに10兆円規模のスタートアップ投資を実現することを目標としています。この計画には、以下のような取り組みが含まれています:
- スタートアップがお金を集めやすい環境の整備
- 人が会社間を移動しやすくする取り組み
- 大学発のスタートアップの立ち上げ促進
- スタートアップが活動しやすい制度の整備
- スタートアップの海外展開支援
このような政策的な後押しにより、日本のスタートアップ環境は以前より整ってきています。地方においても、地域の特性を活かしたスタートアップ支援の取り組みが増えてきています。
アメリカの先行事例と日本への影響
スタートアップの先進国であるアメリカでは、常に新しい流れが生まれています。近年では、以下のような傾向が目立ちます:
- 人工知能や高度な科学技術への投資増加: 人工知能や高度な科学技術をベースとした「ディープテック」と呼ばれるスタートアップへの投資が増加しています。
- 持続可能性に関わるスタートアップの台頭: 気候変動対策や持続可能な社会の実現に貢献するスタートアップへの注目が高まっています。
- 遠隔勤務を前提とした分散型組織: コロナ禍をきっかけに、地理的な制約にとらわれない組織運営が一般的になっています。
これらの流れは少し遅れて日本にも広がってきており、日本のスタートアップ環境にも大きな影響を与えています。特に注目すべきは、地理的な制約が薄れてきていることで、地方に拠点を置きながらも全国的、世界的に事業展開するスタートアップが増えている点です。
地方とスタートアップの関係
近年、スタートアップは都市部だけではなく、地方にも広がりを見せています。特に興味深いのは、地方ならではのスタートアップの特性です。
地方におけるディープテックスタートアップの可能性
地方には多くの国立大学や研究機関があり、世界レベルの研究が行われていることも少なくありません。こうした研究から生まれる技術を基にした「ディープテック」と呼ばれるスタートアップは、地方で生まれる可能性が高いのです。
ディープテックとは、高度な科学技術を基盤としたスタートアップを指します。例えば、バイオテクノロジー、新素材、ロボット工学、量子コンピュータなどの分野が該当します。これらの分野は多額の研究開発投資と長期的な視点が必要であり、都市部の短期的な流行に左右されにくい特性を持っています。
地方の大学や研究機関を基盤としたディープテックスタートアップは、その地域の特色ある産業や課題と結びつくことで、独自の価値を生み出せる可能性があります。例えば、農業地域では農業技術(アグリテック)、工業地域ではものづくり革新、観光地では観光技術(トラベルテック)など、地域特性と最先端技術を組み合わせた事業が考えられます。
地方スタートアップの課題と可能性
地方でスタートアップを展開する場合、以下のような課題があります:
- 資金調達環境の制約: 都市部に比べてベンチャーキャピタルやエンジェル投資家へのアクセスが限られています。
- 人材確保の難しさ: 特に専門性の高い人材を地方で確保することは容易ではありません。
- スタートアップエコシステムの未熟さ: メンター、アクセラレーター、コワーキングスペースなどの基盤が不足しています。
一方で、地方ならではの強みもあります:
- 生活コストの低さ: 都市部に比べて家賃や生活費が安く、同じお金でより長く事業を続けられます。これは「バーンレート」(資金を使い切るまでの時間)の観点で大きな優位性となります。
- 地域のつながりの強さ: 地域の企業や行政との連携が取りやすく、実証実験などを行いやすい環境があります。
- 独自の地域資源: 地方特有の産業、文化、自然環境などを活かした事業が可能です。
地方スタートアップは、これらの課題を克服しつつ、地域の強みを最大限に活かすことで、独自の成長経路を見出すことができるでしょう。特に注目すべきは、必ずしも東京などの大都市へのオフィス移転を前提とせず、地方に拠点を残しながらも全国・全世界に事業を展開するモデルが増えている点です。
専門的な視点:会社の価値の考え方
スタートアップの世界では、会社の価値(バリュエーション)がどのように決まるのかを理解することが重要です。これは特にお金を集めるときや出口戦略を考えるときに大きな影響を持ちます。
時価総額の算定方法
スタートアップの時価総額(バリュエーション)は、一般的に次の方法で算定されます:
- 収益倍率(マルチプル)方式: 売上高や利益などの指標に一定の倍率をかけて会社の価値を推定する方法です。例えば、サブスクリプション型のソフトウェア企業(SaaS企業)では、年間経常収益(ARR)の10〜20倍程度で評価されることがあります。
- PER(株価収益率): 株価を1株当たり利益(EPS)で割った指標です。例えば、PERが20倍であれば、現在の利益の20年分の価値が会社の価値として評価されていることになります。
- DCF(割引キャッシュフロー)法: 将来の現金の流れを予測し、現在の価値に割り引いて合計する方法です。理論的には最も正確な方法ですが、成長初期のスタートアップでは将来予測が難しく、適用が困難なケースも多いです。
- 類似企業比較法: 同じ業界の似た企業の評価を参考にする方法です。
初期のスタートアップでは、将来の成長可能性を見込んだ「物語(ストーリー)」に基づく評価も大きな割合を占めます。投資家がその事業の将来性をどう評価するかによって、同じ財務状況でも大きく評価が異なることがあります。
特に、将来の上場を目指す場合、投資家の期待に応える成長率を実現する必要があります。例えば、現在の時価総額が5億円の会社が5年後に大きく成長するには、年平均でも相当高い成長率が必要になります。
各段階での株式放出の目安
スタートアップが成長過程で外部からお金を集める際、段階的に株式を放出(売却)していくことになります。一般的な目安は以下の通りです:
- タネまき段階: 創業者・初期メンバーの持ち株比率は80〜90%程度。投資家へは10〜20%程度の株式を売却します。
- シリーズA: さらに15〜25%程度の株式を売却することが多いです。この時点で創業者チームの持ち株比率は60〜70%程度になります。
- シリーズB: 10〜20%程度の追加株式を売却。創業者チームの持ち株比率は50〜60%程度に下がります。
- シリーズC以降: ラウンドごとに5〜15%程度の株式を売却していきます。最終的に上場の時点では、創業者チームの持ち株比率は20〜30%程度になることも珍しくありません。
これはあくまで一般的な目安であり、業界や企業の状況、調達金額などによって大きく異なります。重要なのは、上場などの出口戦略までに創業者チームが一定の決定権を維持できるよう、持ち株比率の薄まり(希薄化・ダイリューション)をコントロールすることです。
なお、投資家側にはベンチャーキャピタルファンドの償還期限(通常8〜10年)があるため、その期間内に出口戦略を実行することが求められます。これがスタートアップが8〜10年という時間軸で急成長を目指す構造的な理由の一つとなっています。
地方経営者・人材がスタートアップから学べること
スタートアップの世界は一見すると地方の伝統的な事業とは遠い存在に感じられるかもしれません。しかし、そのノウハウや考え方には、地方の企業や人材にとっても学ぶべき点が多くあります。
資源が限られた中での成長戦略と人材活用
スタートアップは、特に初期段階では限られた資源(お金、人材、時間など)の中で成長を実現しなければなりません。この「制約の中での創意工夫」は、資源が限られがちな地方企業にも通じるものがあります。
例えば、以下のような取り組み方は地方企業にも応用可能です:
- 必要最小限の機能ですぐに市場に出す(MVP戦略): 完璧な商品を目指すのではなく、最小限の機能ですぐに市場の反応を見る手法です。地方企業でも、完成度にこだわりすぎず早めに市場の声を聞く姿勢が重要です。
- 低コストで効果を上げる工夫(グロースハック): 少ない予算で最大の効果を得る方法を常に考えることが大切です。広告宣伝にも大きなお金をかけるのではなく、SNSの活用や地域のつながりを活かした口コミなど、費用対効果の高い方法を選ぶことができます。
- 戦略的な連携: 自社にない資源を外部との協力関係で補う考え方です。地方企業同士の連携や、地域の大学・研究機関との協力などが効果的です。
- 兼業・副業人材の活用: 都市部の専門人材をフルタイムで雇用できなくても、兼業・副業として関わってもらうことで、高度な専門知識やスキルを得ることができます。
特に人材面では、スタートアップと地方企業は似た課題を抱えています。大企業のような高い給与や充実した福利厚生で人を集めることが難しい中、いかに「この会社・地域で働く意義」を見出してもらうかが重要になるのです。
以下のような人材戦略も参考になります:
- 目的と将来像の共有: 金銭的報酬だけでなく、共感できる目的や将来像で人を引きつけることが重要です。地方企業も単に「雇用を提供する」だけでなく、「この地域にどのような価値を生み出すのか」というビジョンを明確にし、それに共感する人材を集めることができます。
- 自主性の重視: 細かい指示ではなく、目標を共有して自主的に動ける環境を整えることで、限られた人数でも効率的に働けます。地方企業でも、一人一人が複数の役割を担い、自分で考えて動ける人材が重宝されます。
- 多様なバックグラウンドの活用: スタートアップでは多様な経験や知識を持つ人材が強みになります。地方企業も、Uターン・Iターン人材の持つ都市部での経験や、異業種での経験を積極的に活かすことで、新しい視点を取り入れることができます。
- 少数精鋭の組織づくり: スタートアップでは、一人が複数の役割を担う「マルチプレイヤー」型の人材が重視されます。地方企業でも同様に、専門性と柔軟性を兼ね備えた人材の採用・育成が効果的です。
- リモートワークの活用: コロナ禍以降、リモートワークが一般化したことで、地理的制約なく人材を確保できる可能性が広がりました。地方企業も、一部リモートワークを導入することで、都市部の専門人材と協働することが可能になっています。
限られた経営資源の中で、スタートアップは常に「選択と集中」を迫られます。どの市場に参入するか、どの顧客層をターゲットにするか、どの機能を優先して開発するかなど、常に優先順位を明確にして意思決定する姿勢は、地方企業にとっても大いに参考になるでしょう。
まとめ
スタートアップとは、単に「新しい会社」ではなく、外部からお金を集めることを前提に短期間での急成長を目指す特徴的な事業の仕組みを持つ会社です。タネまき段階、初期段階、中期段階、後期段階という成長段階を経て、最終的には株式上場や会社売却による出口戦略を目指します。
特に重要なのは、スタートアップが8〜10年という時間軸で事業を組み立てている点です。これはベンチャーキャピタルファンドの償還期限に合わせたものであり、その期間内に短期間で数十倍〜100倍以上の成長を実現することが期待されているのです。
このようなハイリスク・ハイリターンの成長モデルは、すべての企業に適しているわけではありません。しかし、その考え方や手法には、地方企業が学べる点が多くあります。特に、限られた資源の中で最大の効果を生み出す方法や、魅力的なビジョンによって人材を惹きつける戦略は、地方企業の成長にも大いに参考になるでしょう。
また、地方においても、地域の強みを活かしたスタートアップが誕生しています。特に大学や研究機関からの技術を活かしたディープテックスタートアップは、地方から生まれる可能性が高いと言えます。地方企業とスタートアップの間の連携・協業の機会も増えており、お互いの強みを活かした新たな成長の形も生まれつつあります。
地方企業がスタートアップのすべてを真似る必要はありませんが、その一部を自社の状況に合わせて取り入れることで、新たな成長の可能性が広がるかもしれません。リスクの高さやスピード感の違いはあれど、限られた資源を最大限に活用し、独自の価値を創造するという根本的な経営姿勢は共通しているのです。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。