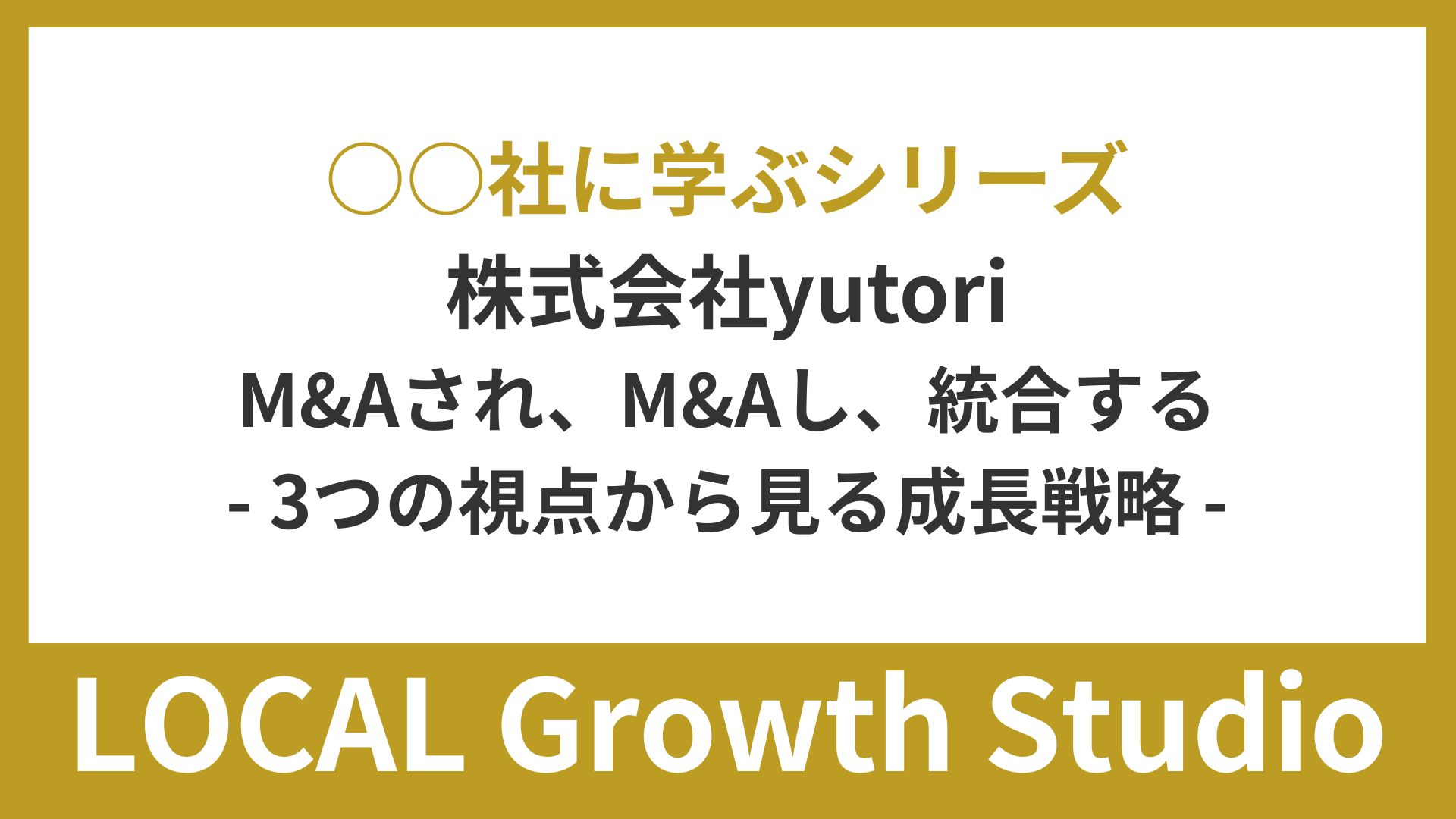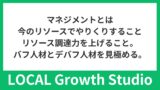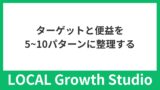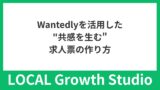ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
「○○社に学ぶシリーズ」の第2弾として、今回取り上げるのは、2018年に創業し、わずか5年で東証グロース市場への上場を果たした株式会社yutoriです。創業からの7年間で5件のM&Aを実施し、売上高は16百万円から8,306百万円へと約520倍に成長しました(2025年3月期時点)。
前回のGENDA社の記事では「買収する側」として55件のM&Aを支える成長基盤づくりを学びました。今回のyutoriは、それとは異なる視点を提供してくれます。
特筆すべきは、yutoriが「M&Aされる側」と「M&Aする側」の両方を経験し、さらにその後の統合(PMI)においても独自の手法を確立している点です。2020年にZOZOグループ入り(51%資本提携)を経て上場し、その後はheart relation社(Her lip to運営)など複数企業を買収。現在は38ブランドを展開し、5年で70ブランドへの拡大を目指しています。
本記事では、yutoriの成長戦略を「①M&Aされる側の戦略」「②M&Aする側の戦略」「③PMI(買収後統合)の実践」という3つの視点から分析し、M&Aをすぐに行う予定のない企業や、成長中の地方企業でも応用できる成長の原則を抽出していきます。
参考資料
ポイント① M&Aされる側の戦略 – 「スイングバイIPO」という選択
資金調達からM&Aへの転換
yutoriは2020年、当初はエクイティ(株式)での資金調達を目的にZOZOに接触しました。しかしZOZO側は「マイノリティ(少数株主)はやっていない」として、当初は100%買収を提案。その後、「君たちまだ遊ばせないよ」という意図から51%の資本提携に変更されました。
この51%という数字には重要な意味があります。yutori側にとって「残り49%のアップサイド(成長余地)も残った状態で、ダウンサイド(リスク)だけ削る」という「いいことしかない」形だったのです。完全子会社化されれば創業者のインセンティブ(動機付け)は失われますが、49%を保持することで上場時のキャピタルゲイン(株式売却益)も狙えるわけです。
「スイングバイIPO」という戦略
yutoriが選んだのは「スイングバイIPO」という道でした。これは宇宙探査機が惑星の重力を利用して加速する現象から名付けられた戦略で、大企業の支援を受けて成長し、その後上場を目指すアプローチです。
重要なのは、ZOZOとは契約の段階から「上場しないの?」「上場を目指そう」という方向性を共有していた点です。買収後の出口戦略(最終的にどうなるか)が明確であったため、ZOZO側も過度な干渉をせず、yutori側も自律的な成長にコミットできました。もしこの方向性が共有されていなければ、経営の自由度は大きく制限されていたかもしれません。
信用力のレバレッジ効果
ZOZOグループ入りによって、yutoriが得た具体的なメリットは以下の通りです。
ファイナンス面
ZOZOの信用力を元に銀行からの借り入れを増やし、その資金を買収(M&A)に使い事業成長につなげました(注目すべきは、ZOZOからの直接借り入れはない点です。あくまで信用力のレバレッジです)。
採用面
ZOZOがバックアップしたことで「センスもあって尖っているけど、ちゃんとビジネスもしている」というストーリーに説得力が生まれ、アパレル業界の中途人材などが入りやすくなりました。結果、応募者数が2~3倍になりました。
出店交渉
商業施設への出店交渉もスムーズになり、ZOZOのブランド力が店舗展開を加速させました。
独立性の維持
重要なのは、グループ入り後も独立性を維持した点です。親子間の利益相反を避けるため、親会社からの借入れやリソース使用、事業提供は行わず、子会社(yutori)の独立性を保つことを重視しました。
また、グループ入りを機に、当時並行して行っていたバーチャルモデル事業を終了し、売上や利益が出ており、メンバーの熱量も高いアパレルブランド事業に集中しました。
地方企業が学べること:資本提携による成長加速の可能性
M&Aされることについて、「身売り」や「敗北」というイメージを持つ経営者もいらっしゃるかもしれません。しかし、yutoriのケースは異なる視点を提供してくれます。
応用ポイント1:完全買収ではなく資本提携という選択肢
100%買収ではなく、51%などの資本提携であれば、経営の自由度を保ちながら大企業の信用力や資金力を活用できます。特に事業承継を控えた地方企業にとって、単純な親族内承継ではなく「資本提携+事業承継」という選択肢も可能性として考えられるでしょう。
応用ポイント2:信用力のレバレッジ活用
yutoriはZOZOの信用力を活用して銀行からの借入を増やし、それをM&Aに投資しました。地方企業も、信用力のある企業と資本提携することで、単独では困難だった資金調達や人材採用が可能になります。
応用ポイント3:出口戦略の事前共有
yutoriがZOZOと「いずれ上場を目指す」という方向性を最初から共有していたことは重要です。地方企業が資本提携を検討する際も、5年後・10年後の姿について明確なビジョンを共有することで、互いのインセンティブを整合させることができます。
具体的な実践方法
- 地方の優良中堅企業との資本提携(地元の上場企業、金融機関の子会社など)
- 業界大手との業務資本提携(仕入先や販売先との関係強化)
- 事業承継時に外部投資家を入れる選択肢(プライベートエクイティファンドなど)
重要なのは「M&Aされる=終わり」ではなく「M&Aされる=成長のステップ」と捉えることです。
ポイント② M&Aする側の戦略 – Her lip to買収に学ぶ買収の作法
M&Aの内製化という選択
yutoriは創業以来7年間で5件のM&Aを実施していますが、そのすべてが仲介業者やエージェントを介さない内製化案件です。ソーシング(案件発掘)からPMIまで、基本的に社内メンバーで実行しています。
具体的には、役員やメンバーのコネクション、特に「勢いのある後輩」などを通じて案件を発掘。社内には税理士、公認会計士が在籍しており、初期的な検討を機動的に行うため、基本合意までスピーディーに進められます。
買収対象の選定基準
yutoriが買収対象を選ぶ際の基準は明確です。
基準1:業界インパクトとEPS向上
業界インパクトが大きく、かつEPS(1株あたり利益)の向上に貢献する企業を選定します。
基準2:Z世代ターゲットで圧倒的な熱狂
Z世代をターゲットに何らかのプロダクトを出し、そこに圧倒的な熱狂がある会社を興味の対象としています。
基準3:時価総額の差分
興味深いのは「買われる側と買う側の企業実態(時価総額)が乖離していればいるほど良い」と考えている点です。サイズが近いと買い手側が経営に深く関与するインセンティブが働きすぎるため、企業家にとって良くないことが多いという判断なのです。この考え方は、yutori自身がZOZOに買収された経験から得た学びといえるでしょう。
heart relation(Her lip to)買収の戦略
2024年8月、yutoriは小嶋陽菜氏が代表を務めるheart relation社の株式51%を約17億円で取得しました。yutori史上最大規模のM&Aです。
買収の狙い1:顧客層の拡張
yutoriは主にZ世代向けストリートブランド(「9090」「HTH」など)を展開するのに対し、Her lip toはフェミニンな女性向け(Y世代以上)の顧客層を持ちます。この買収により、顧客基盤を大きく拡大できました。
買収の狙い2:商材の多角化
heart relationは、主力のアパレルブランド「Her lip to」に加え、ランジェリーブランド「ロジア」、ビューティブランド「Her lip to BEAUTY」を展開。アパレル以外の領域への事業拡張モデルとして参考になります。
買収の狙い3:店舗運営ノウハウの獲得
heart relationが持つ店舗運営のノウハウも、yutoriの成長に大きく貢献するとされています。
経営者間の長期的な関係性
yutoriの片石社長と小嶋陽菜氏は、yutori創業時の2018年に共通の知り合いを通じて会っており、長い時間軸でお互いの事業ストーリーを把握していました。
片石社長は、小嶋氏が「成功体験にとらわれず、時代を見ながら新しいことを始めようとしていた点にフィール(共感)した」と述べています。M&Aは財務数値だけでなく、経営者の価値観やビジョンの共有が重要であることを示しています。数字上の魅力だけで買収を決めてしまうと、統合後に「こんなはずではなかった」というミスマッチが生じるリスクが高まるのです。
51%資本提携という提案の説得力
yutori自身がZOZOから受けた51%資本提携の成功体験があったため、heart relationにも同様の提案が可能でした。「自分たちもこの形で成長できた」という実例があることで、説得力が大きく増しました。もし yutori自身が100%買収されていたら、この提案の説得力は大きく損なわれていたでしょう。
また、yutori側が「クリエイティブ領域のM&Aにおいて、再現性がない方が良くないですか?」と問いかけたことが、小嶋氏の心に響いたといいます。再現性を追求することはオリジナリティや独創性を失い、参入障壁を下げることになるという考え方です。この「クリエイティブは標準化しない」という哲学が、両社の価値観の共通点となりました。
地方企業が学べること:M&Aを成長の手段として活用する
「M&Aは大企業が行うもの」というイメージを持つ経営者も多いかもしれません。しかし、yutoriの事例は規模に関わらずM&Aを成長手段として活用できることを示しています。
応用ポイント1:M&Aの内製化は可能
yutoriは仲介業者を使わず、人脈ベースで案件を発掘しています。地方企業でも、地元の商工会議所、金融機関、同業他社の経営者ネットワークを活用すれば、仲介手数料(通常、譲渡価格の5〜10%程度)をかけずに案件を見つけることができます。
特に地方では、後継者不在で廃業を検討している優良企業が多数存在します。こうした企業を見つけるには、税理士や地域金融機関との日頃からの関係構築が重要です。「事業承継で困っている企業があれば教えてください」と一言伝えておくだけでも、情報が集まりやすくなります。
応用ポイント2:隣接領域への拡張
yutoriがheart relationを買収したように、自社の顧客層を補完する企業を買収することで、顧客基盤を一気に拡大できます。
地方企業の例で言えば:
- 建設業A社(新築中心)が、リフォーム専門のB社を買収して、既存顧客の住宅メンテナンスニーズに対応
- 飲食店C社(ランチ中心)が、夜営業中心のD社を買収して、店舗稼働率を向上
- 製造業E社(B to B中心)が、小売店F社(B to C)を買収して、エンドユーザーの声を直接聞ける体制を構築
重要なのは「完全に異なる業種」ではなく「顧客層や商材が補完関係にある企業」を選ぶことです。全く別の業界に飛び込むのではなく、自社の強みを活かせる隣接領域に拡張するという発想が成功の鍵となります。
応用ポイント3:51%資本提携という選択肢
100%買収ではなく51%の資本提携であれば、買収資金を抑えられるだけでなく、売り手側の経営者のモチベーションも維持できます。特に地方の事業承継案件では、創業者が一定の影響力を保ちながら事業を次世代に引き継ぎたいというニーズがあります。
具体的な実践方法
- 地域金融機関に「事業承継案件があれば紹介してほしい」と依頼
- 同業他社の経営者との定期的な情報交換会を開催
- 商工会議所の後継者育成プログラムに参加し、ネットワークを構築
- 顧問税理士に「廃業を検討している取引先はないか」を定期的にヒアリング
M&Aは大企業の専売特許ではありません。規模に関わらず、適切な準備とネットワーク構築により、成長の手段として活用できます。
ポイント③ PMI(買収後統合)– 独立性と効率化の両立
ブランドの独立性を守る
yutoriのPMI戦略で最も特徴的なのは「ブランドの独立性を徹底的に守る」という方針です。
グループ入り後も「Her lip toがストリートになるわけでも、yutoriがフェミニンになるわけでもない」ように、ブランドの独立性を保ち、お互いに切磋琢磨することを大前提としています。
事業サイドでは、成功事例を共有するに留め、それを採用するかどうかは各ブランド自身で選択するスタンス。服作りや物流など、裏側(バックヤード)の効率化については協力し、相乗効果を図る一方で、クリエイティブ領域には介入しません。
企業文化の親和性
heart relationのメンバーは、yutori社と文化が似ており、「プライベートと仕事がすごい良い意味で曖昧に混ざってて」自然体な感覚で会社運営をしている点が共通しています。
M&Aの成否は、財務数値だけでなく、企業文化の親和性に大きく左右されます。いくら財務的に魅力的な企業でも、文化が合わなければ統合後に大きな摩擦が生じるでしょう。yutoriとheart relationは、数年前からの関係性の中で、価値観の共有ができていました。この「長期的な関係性の中での相互理解」が、M&A成功の重要な要因となっているのです。
規律あるブランドポートフォリオ管理
yutoriは「Yリーグ」という独自のルールでブランドを管理しています。月間平均売上で5段階(Y1~Y5)にランク分けし、立ち上げ後1年でY4にランクアップしないブランドは原則として撤退します。
2025年6月末には、Y5ブランドを中心とする合計8ブランドの撤退を決定しました。該当ブランドの在庫金額約2,600万円を商品評価損として計上しましたが、業績への影響は限定的。撤退に伴い人員リソースを成長性の高いブランドへ集中させ、効率的な経営を追求しています。
のれんの健全性管理
4件のM&Aに係る約8.5億円ののれんが計上されていますが、yutoriは「仮にのれんの全額が減損となっても直ちに債務超過とならないよう」、のれんの残高を純資産の金額以内に収めることで財務健全性を維持しています。
これは地方企業がM&Aを行う際にも重要な原則です。過度に高値で買収し、のれんが膨らみすぎると、業績が悪化した際に減損リスクが企業の存続を脅かします。
急成長を実現したPMIの成果
heart relationの業績取り込み効果もあり、2026年3月期1Qの連結業績は、売上高が前年同期比で2.9倍、営業利益は7.4倍と大幅に増加しました。heart relation単体も四半期として過去最高の売上を記録し、前年同期比130%超の成長を達成しました。
地方企業が学べること:統合後の成長を最大化する原則
M&Aは「買収がゴール」ではなく「買収がスタート」です。買収後の統合(PMI)こそが、M&Aの成否を決定します。
応用ポイント1:クリエイティブ領域には介入しない
yutoriが「Her lip toがストリートにならない」ように独立性を守ったように、買収先企業の強みや独自性を尊重することが重要です。
地方企業の例で言えば:
- 老舗和菓子店を買収した際、伝統的な製法や味は変えない
- 地域密着型の小売店を買収した際、店主と顧客の関係性を維持する
- 技術力のある製造業を買収した際、職人の裁量権を尊重する
過度な「効率化」や「標準化」は、買収先企業の強みを殺してしまう可能性があります。
このポイントについては、以下の記事でも組織マネジメントにおける人材の強みの活かし方について詳しく記載しています。
応用ポイント2:バックヤードは徹底的に効率化
一方で、物流、経理、人事、ITシステムなど、裏側の業務は積極的に統合・効率化すべきです。yutoriも「服作りや物流など、裏側の効率化については協力」としています。
地方企業が複数の事業所や子会社を持つ場合、以下のような統合が有効です:
- 経理業務の本社集約
- 仕入先の統合による調達コスト削減
- ITシステムの共通化
- 採用活動の共同実施
応用ポイント3:明確な撤退基準を持つ
yutoriの「Yリーグ」のように、事業の継続・撤退を判断する明確な基準を持つことが重要です。
地方企業でも、以下のような基準を設定できます:
- 営業利益率が3期連続でマイナスの事業は撤退検討
- 新規事業は2年以内に黒字化しなければ撤退
- 売上高が前年比80%を下回った事業は原因分析と改善計画を義務付け
「情」で赤字事業を続けることは、企業全体の成長を阻害します。明確な基準に基づいた意思決定が、健全な成長を支えます。
応用ポイント4:財務健全性の維持
yutoriが「のれんの残高を純資産以内に収める」ことで減損リスクを管理しているように、買収価格は慎重に設定すべきです。
地方企業がM&Aを行う際の原則:
- 買収価格は純資産の1.5倍以内に抑える(のれんが純資産の50%を超えない)
- 買収資金の50%以上は自己資金で賄う
- 買収先企業の債務は精査し、簿外債務がないことを確認
具体的な実践方法
- 買収後100日以内に「統合計画」を策定(何を統合し、何を独立させるか)
- 月次で買収先企業の業績をモニタリング
- 四半期ごとに統合効果を測定(コスト削減額、売上シナジーなど)
- 買収先企業の経営者・従業員との定期的なコミュニケーション
M&Aをすぐに行わない企業でも使える – yutoriの成長原則の応用
ここまでyutoriのM&A戦略を見てきましたが、「うちの会社はまだM&Aを検討する段階ではない」と感じる経営者も多いでしょう。しかし、yutoriの成長原則は、M&Aを行わない企業にも応用できる普遍的な要素を含んでいます。
原則1:ポートフォリオ思考で事業を管理する
yutoriの「Yリーグ」は、複数ブランドを管理する仕組みですが、この考え方は単一事業の企業でも応用できます。
地方企業への応用
- 製品ラインナップをポートフォリオとして管理し、利益率の低い製品は撤退
- 顧客をセグメント分けし、収益性の高い顧客層に経営資源を集中
- 複数店舗を運営する企業は、店舗ごとに明確な業績目標を設定
重要なのは「すべての事業・製品・顧客が同じ重要度ではない」と認識し、選択と集中を行うことです。
このポイントについては、以下の記事でも顧客属性ごとに異なる価値提供を設計する手法について詳しく記載しています。
原則2:「NICOモデル」で新規事業を立ち上げる
yutoriはブランド立ち上げのノウハウを「NICOモデル」として体系化しています。
- N (NICHE):マス向けではなく、ニッチだが熱量のある領域の選定
- I (ITEM):そのブランド領域におけるアイコニックな商品として認知される商品企画
- C (COLLABO):インフルエンサーや他企業とコラボすることで、さらなる認知拡散
- O (OFFLINE):ユーザーを獲得後、POPUPや店舗展開により販路を拡大して収益を確保
地方企業への応用
地方企業が新規事業や新製品を立ち上げる際も、この4ステップは有効です。
例:地方の醤油製造業が新製品を開発する場合
- N:マス向けではなく「無添加・有機栽培」というニッチ市場を選定
- I:「100年続く伝統製法」を全面に出した看板商品を開発
- C:地元の有名シェフや料理研究家とコラボして認知拡散
- O:まずは自社ECで販売し、反応が良ければ地元スーパーに展開
重要なのは、いきなり大きな市場を狙うのではなく、ニッチで熱量のある顧客層からスタートし、段階的に拡大することです。
このポイントについては、以下の記事でも顧客の深層的な願望(インサイト)の捉え方について詳しく記載しています。
原則3:SNSマーケティングを内製化する
yutoriの強みの一つは、InstagramやTikTokなどのSNS運用を全て内製で行っている点です。現在、グループ全体で277万人のInstagramフォロワーを抱えています。
地方企業への応用
SNSマーケティングについて、「若手社員に任せるもの」「広告代理店に外注するもの」というイメージを持つ企業も多いかもしれません。しかし、yutoriの成功は内製化の重要性を示しています。
具体的な実践方法:
- 社内に「SNS担当」を配置(若手社員が適任です)
- 毎日投稿する習慣を作る(質より量を重視する初期段階)
- 商品の宣伝ではなく、「ブランドの世界観」を発信
- フォロワー数ではなく、エンゲージメント率(いいね・コメント率)を重視
地方の老舗企業でも、職人の技術、地域の風景、商品ができるまでのストーリーなど、発信できるコンテンツは豊富にあります。重要なのは「継続すること」です。
このポイントについては、以下の記事でもストック型(継続的に効果を発揮する)施策としてのマーケティング手法について詳しく記載しています。
原則4:人材投資を惜しまない
yutoriの連結従業員数は、2023年3月期の180人から2025年3月期には385人へと倍増しています。特にZOZOグループ入り後、採用活動が加速しました。
片石社長は「競争力の源泉は人材」と明言しており、人材投資により強靭な成長基盤の構築を目指しています。
地方企業への応用
成長中の地方企業では「人を増やすタイミング」を慎重に検討することが多いでしょう。しかし、yutoriの事例は「人材投資こそが成長の鍵」であることを示しています。
具体的な実践方法:
- 売上目標から逆算して必要な人員数を計算する
- 「今は忙しくないから採用しない」ではなく「成長のために先行投資として採用する」という発想
- 地元の大学・高専との連携を強化(インターンシップ、共同研究など)
- Uターン・Iターン人材の積極採用(住宅補助、引越し費用補助などの支援)
特に地方企業は、都市部に比べて採用難易度が高いため、早めに動くことが重要です。「良い人材が応募してきたら採用する」という受け身の姿勢ではなく、「この会社で働きたい」と思ってもらえる魅力を発信することが求められます。
このポイントについては、以下の記事でも採用活動の第一歩となる求人票作成の手法について詳しく記載しています。
原則5:事業の集中と選択を徹底する
yutoriはZOZOグループ入りを機に、並行して行っていたバーチャルモデル事業を終了し、アパレルブランド事業に集中しました。また、「Yリーグ」による規律あるブランド管理で、成長性の低い事業からは撤退しています。
地方企業への応用
成長中の企業では、さまざまな事業機会に対応しようとするあまり、経営資源が分散してしまうことがあります。yutoriのように「選択と集中」を徹底することで、成長スピードが加速します。
具体的な実践方法:
- 全事業の利益率を一覧化し、赤字事業の撤退を検討
- 「創業時からやっている」という理由だけで続けている事業を見直す
- 経営者の時間配分を可視化し、成長性の高い事業に時間を集中
- 年に1回「事業ポートフォリオ会議」を開催し、継続・撤退を判断
「撤退は失敗ではない。次の成長への投資である」という認識を持つことが重要です。
まとめ:M&Aの有無に関わらず、成長する企業の原則
yutoriの成長戦略から学べることは、M&Aという手法の巧みさだけではありません。その根底には、規模や業種を問わず応用できる普遍的な成長原則があります。
1. 外部の力を借りることを恐れない
yutoriは自らZOZOの傘下に入ることで成長を加速させました。地方企業も、資本提携、業務提携、アライアンスなど、外部の力を借りることで単独では不可能な成長を実現できます。「すべて自前でやる」という考え方は、時として成長のボトルネックになるのです。
2. 明確な基準で意思決定する
「Yリーグ」のような明確な基準を持つことで、感情に流されない経営判断が可能になります。地方企業でも、事業継続・撤退の基準、新規事業への投資基準、人材採用の基準など、定量的な指標を持つべきでしょう。
3. クリエイティブと効率化を両立させる
yutoriはブランドの独立性を守りながら、バックヤード(裏側の業務)は徹底的に効率化しています。地方企業も、職人技術や顧客との関係性など「変えてはいけないもの」と、業務プロセスやシステムなど「効率化すべきもの」を明確に区別する必要があります。
4. ポートフォリオ思考で事業を管理する
すべての事業・製品・顧客が同じ重要度ではありません。選択と集中により、経営資源を成長性の高い領域に投下することで、全体としての成長速度が上がるのです。
5. 人材投資を惜しまない
yutoriが385人まで人員を拡大したように、人材投資は成長の前提条件です。「人が足りないから成長できない」ではなく「成長するために人を採用する」という発想の転換が必要でしょう。
yutoriの事例は、M&Aという手法を通じて、これらの原則を極めて高いレベルで実践した結果と言えるでしょう。M&Aを行う・行わないに関わらず、これらの原則を自社に取り入れることで、地方企業も持続的な成長を実現できます。
「M&Aは大企業の専売特許」という固定観念を捨て、成長の選択肢を広げること。そして、M&Aをしない場合でも、yutoriの成長原則を自社の経営に取り入れること。その両方が、成長を目指す経営者に求められています。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。