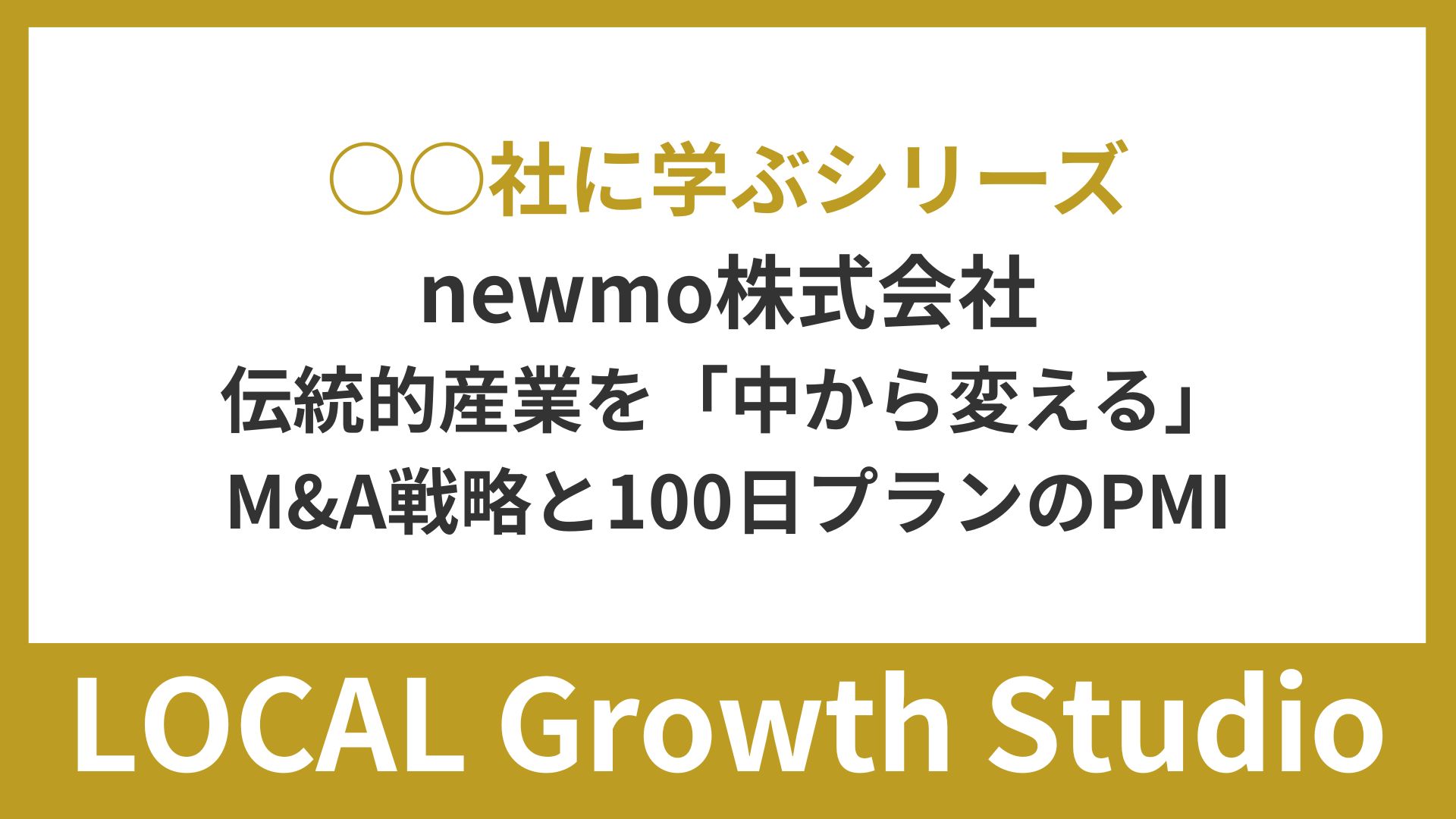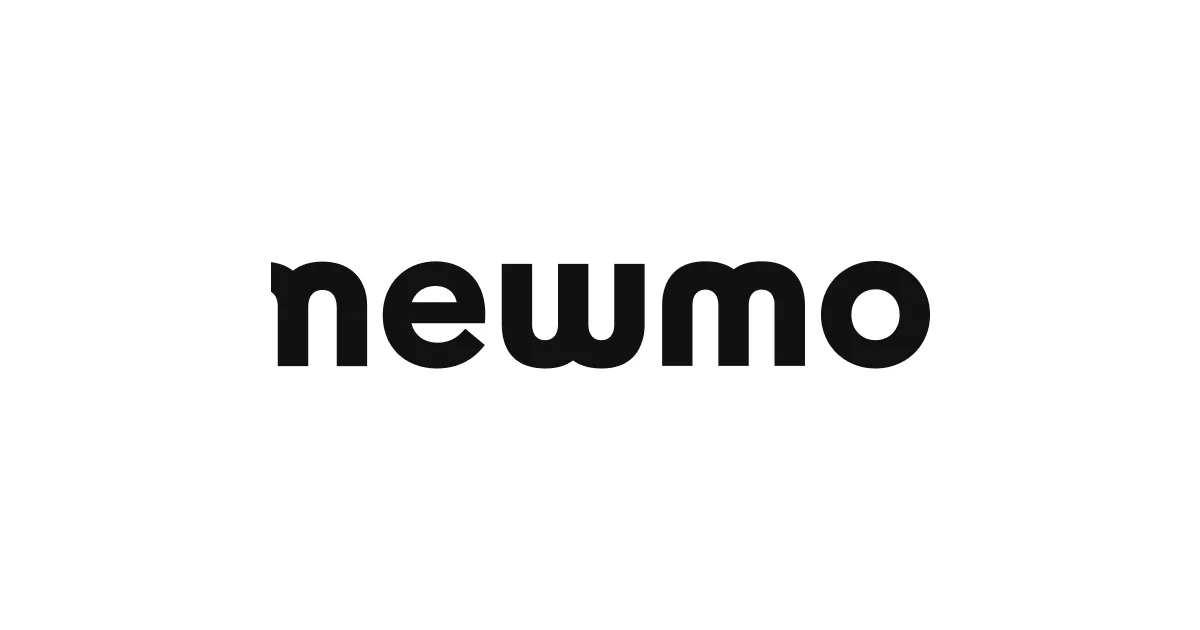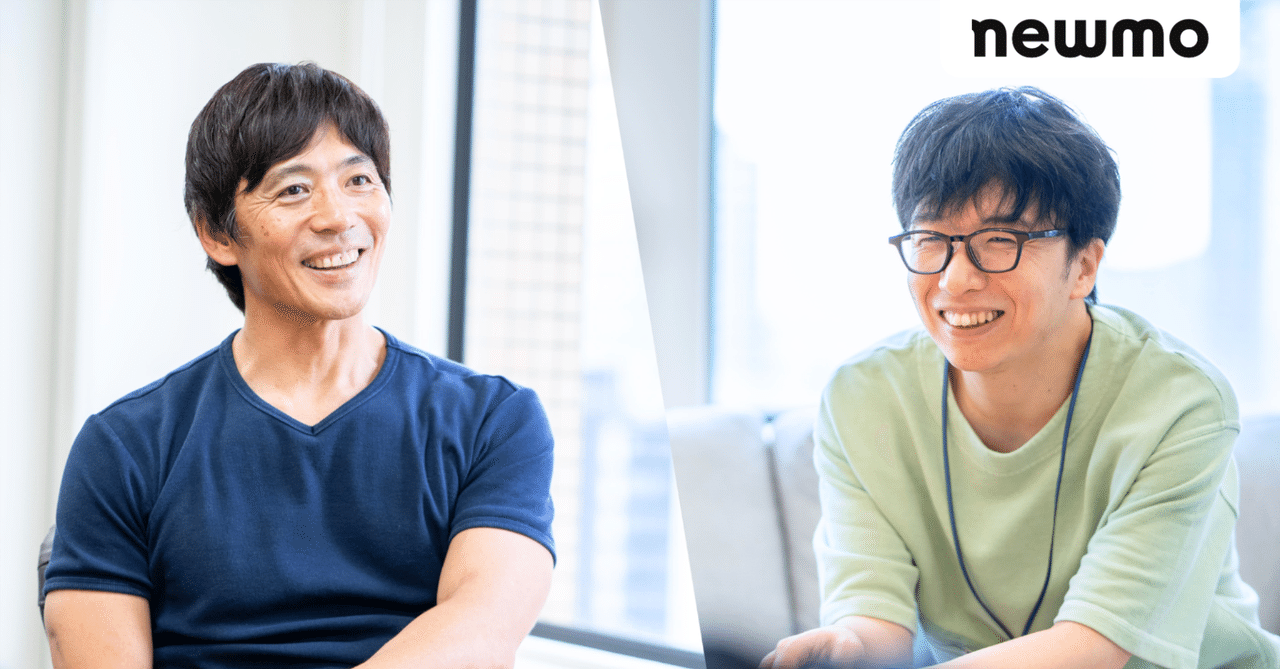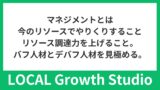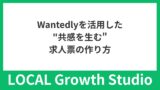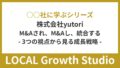ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
「○○社に学ぶシリーズ」の第3弾として、今回取り上げるのは、2024年1月に設立され、わずか10ヶ月で累計約187億円という異例の資金調達を成功させたnewmo株式会社です。創業1年でタクシー車両1,000台超、従業員1,000人以上を抱え、大阪府内で保有台数3位のタクシー会社となりました。
前回のGENDA社は55件のM&Aを実行する買収側、yutori社はM&Aされる側とM&Aする側の両方を経験した企業でした。今回のnewmoは、スタートアップでありながら伝統的なタクシー業界という規制の厚い既存産業を「中から変える」ために、積極的にM&Aを活用している点が特徴的です。
本記事では、newmoの成長戦略を「①なぜタクシー会社を買収するのか」「②100日プランと心のPMI」「③伝統的産業のDX」という3つの視点から分析し、地方の伝統的産業に携わる企業でも応用できる成長の原則を抽出していきます。
参考資料
ポイント① 「中から変える」M&A戦略 – なぜスタートアップがタクシー会社を買収するのか
ライドシェア事業参入の「現実的な道」
newmoの青柳直樹CEO(元グリー取締役、メルカリ日本事業トップ)が掲げるミッションは「移動で地域をカラフルに」です。その実現手段としてライドシェア事業を展開しようとしたとき、日本特有の大きな壁に直面しました。
日本版ライドシェア(2024年4月解禁)は、運行の安全性確保のため、運営主体を既存のタクシー会社に限定するルールが設けられています。つまり、ライドシェアを実現するためには、まずタクシー事業者の経営権を取得する必要があったのです。
「外から批判」ではなく「中から変革」
日本のタクシー業界には約7,000社が存在し、業界団体が政治的な強いパワーを持っています。かつて多くのスタートアップが「規制を変えるべきだ」と外から主張しましたが、なかなか実現しませんでした。
青柳CEOが選んだのは、異なるアプローチでした。外から「規制を変えるべきだ」と主張するのではなく、「中(タクシー会社)に飛び込んで一緒にやっていく」方が、日本においては現実的に受け入れられると判断したのです。
この「中から変える」戦略は、単なる妥協ではありません。既存業界の知見やアセット(車両、人材、営業許可)を活用しながら、デジタル技術で効率化を進めるという、伝統と革新の融合を目指す戦略なのです。
ロールアップ戦略による効率的な拡大
newmoが採用したのは「ロールアップ戦略」と呼ばれる手法です。これは、同質性の高い企業(この場合はタクシー会社)を連続的に買収・統合していくことで、効率的に事業を拡大する方法です。
買収実績(創業1年での成果):
- 2024年3月:岸交(岸和田交通グループ)に資本参加
- 2024年7月:未来都(みらいと、600台以上保有)の経営権取得
- 2025年4月:堺相互タクシーの経営権取得
- 2025年11月:タカラ自動車(63台)の営業権取得
グループ規模:
- タクシー車両:1,000台超
- 従業員数:1,000人以上
- 大阪府内での順位:保有台数3位
一つひとつのタクシー会社を買収し、デジタル化や効率化の「勝ち筋」を見つけて横展開していくことで、スケールメリットを活かした成長を実現しています。
規制変化への「2の矢」戦略
興味深いのは、newmoが当初期待していたライドシェアの全面解禁が実現しなかったという点です。
2024年4月に日本版ライドシェアが解禁されましたが、これは「タクシーが不足する時間帯・エリア限定」という条件付きでした。青柳CEOは万博期間中の大阪府全域24時間運行許可を「全面解禁の転機」と期待し、ライドシェアドライバーとして1万人以上を募集しました。
しかし万博終了後、常時運行は再び不可能となり、ドライバーは1,000人から200人ほどに減少。規制改革の議論は事実上先送りとなりました。
この「挫折」に対し、newmoは戦略を転換しました。「ライドシェアという手法」にこだわらず、「地方における移動の足不足の解消」という目的を重視し、タクシー業界の変革(DXとM&A)に注力する方向に舵を切ったのです。
同時に、この規制の議論は「必ず戻ってくる」テーマであるため、規制が再燃した際に「一番良いポジション」にいられるよう、タクシー会社を強固にし続けるという「2の矢」の戦略を持っています。これは、将来の規制変更に備えて基盤を固めておくという、長期的視点に立った判断といえるでしょう。
地方企業が学べること:「中から変える」という成長戦略
newmoの「中から変える」アプローチは、地方の伝統的産業にも大きな示唆を与えてくれます。
応用ポイント1:外から批判するのではなく、内側から変革する
地方には、長年の慣習や業界の常識が根強く残る産業が多く存在します。「時代遅れだ」「非効率だ」と外から批判するのは簡単ですが、それでは業界全体の反発を招くだけです。
newmoのように、まず業界の一員となり(M&Aや事業参入)、内側から少しずつ変革を進めていく方が、現実的な成果につながります。
応用ポイント2:規制産業でも成長の余地はある
「規制が厳しいから成長できない」という諦めは、時として思考停止につながります。newmoは規制の中でも、タクシー会社の買収という合法的な手段で事業基盤を築きました。
地方企業でも、建設業、運送業、医療・介護など、規制の厳しい産業は多数存在します。しかし、規制の範囲内でできることを最大化し、将来の規制緩和に備えて準備しておくことで、競争優位を築けるのです。
応用ポイント3:同質性の高い企業群のロールアップ
newmoのロールアップ戦略は、地方企業にも応用できます。例えば:
- 地方の小規模運送会社を束ねて、配送網を効率化
- 複数の工務店を統合し、資材調達コストを削減
- 地域の小売店をグループ化し、共同仕入れとPOSシステム導入
重要なのは「同質性の高い企業群」を対象にすることです。全く異なる業種を買収するのではなく、同じビジネスモデルを持つ企業を統合することで、ノウハウの横展開が容易になります。
具体的な実践方法
- 地域の同業他社の経営状況を把握する(商工会議所、金融機関経由)
- 後継者不在で廃業を検討している企業にアプローチ
- まずは1社を買収し、効率化の「勝ち筋」を見つける
- その成功モデルを横展開する形で2社目、3社目を検討
ポイント② 「100日プラン」と「心のPMI」 – 買収後の統合戦略
明確な「100日プラン」による迅速な統合
newmoは、買収したタクシー会社に対して「100日プラン」という明確な統合計画を実行しています。これは、買収後100日以内に実施すべき施策を事前に計画し、迅速に実行に移すアプローチです。
100日プランで実施された主な施策:
- 経営指標の可視化と管理会計の導入
- グループウェアを導入し、全営業所での経営指標を可視化
- 営業所単位の管理会計を導入(どの営業所が黒字・赤字かを明確化)
- オペレーションの効率や目標数字を明確化
- デジタルツールの導入
- 自動点呼システムの導入
- デジタルシフト表への移行
- 無線配車依頼の一部自動化
- バックオフィスの近代化
- 経理・労務などのバックオフィス業務の改善
- コーポレートIT基盤の整備
- グループ横断でのツール導入やデータ統合
- ローカルデータのクラウド・オンライン化
- 現場との関係構築
- 青柳CEOが各営業所を頻繁に訪問
- 現場との対話(分科会など)を通じた「あるべき姿」の模索
- 従業員体験の改善
- より柔軟な働き方ができる勤務形態の整備
- 時代に合わせた身だしなみ基準のアップデート
このプランの特徴は、事前に計画を立て、買収完了後に迅速に実行を開始する点にあります。「買収してから考える」のではなく、買収前の段階から統合計画を検討しておくことで、統合のスピードが大きく変わります。
このポイントについては、以下の記事でもGENDA社の「最初の100日」の取り組みについて詳しく記載しています。
「心のPMI」 – トップが現場を理解する重要性
newmoのPMI戦略で最も特徴的なのは、青柳CEOが「心のPMI」と呼ぶ、人間関係の構築を重視している点です。
CEOが二種免許を取得
青柳CEOは、タクシードライバーの気持ちを理解するため、自らタクシーの二種免許を取得し、実際に大阪で乗務することもあります。これは、約1,100人のドライバーから「社長は乗務員の気持ちを分かっている」という信頼を得る上で非常に有効に機能しています。
二拠点生活で現場に頻繁に訪問
青柳CEOは東京と大阪の二拠点生活をし、買収した未来都の営業所を頻繁に訪問しています。経営者が現場に足を運び、ドライバーと直接対話することで、「ウェットな」信頼関係を築き、ハードな課題にも踏み込める素地を作っているのです。
「接客業」としての意識改革
newmoは、タクシー事業を単なる「運送業」ではなく「接客業」と再定義しています。接客の得意・不得意はサービス品質とブランディングに直結するため、接客意識の徹底が図られています。
従業員体験の重視
お客様に「応援されて選ばれるタクシー会社」になるためには、ドライバーのホスピタリティが重要です。そのためにはドライバーがハッピーに働ける環境(良い従業員体験)の構築が最重要だと考えられています。
採用が根幹
現場に足を運ぶ中で、タクシー会社の経営にとって採用が根幹であるという発見がありました。この認識に基づき、デジタルツールの導入・効率化により、未来都ではグループ参画から3ヶ月(2024年7月〜9月)で、採用の応募数が前年比1.5倍のペースに増加し、内定率も2倍に改善する成果が出ています。
このポイントについては、以下の記事でも組織マネジメントにおける人材の重要性について詳しく記載しています。
トップダウンとボトムアップのバランス
newmoのPMIでは、トップダウンとボトムアップのバランスを重視しています。
タクシー業界には非効率な習慣が多く残っているため、newmoが強い意思で「あるべきタクシー会社」に向けてトップダウンに経営指針を示すアプローチが必要な場合もあります。
一方で、現場との対話(分科会など)を通じてお互いが腹落ちできる「あるべき姿」を見つけていくことも大切にされています。一方的な押し付けではなく、現場の声を聞きながら変革を進めるというバランス感覚が、統合の成功につながっているのです。
地方企業が学べること:統合後の信頼関係構築
M&Aは「買収がゴール」ではなく「買収がスタート」です。買収後の統合(PMI)こそが、M&Aの成否を決定します。
応用ポイント1:トップが現場を理解する
青柳CEOが二種免許を取得したように、買収先企業の事業を本当に理解するためには、トップ自らが現場に入ることが重要です。
地方企業の例で言えば:
- 製造業を買収したら、社長自ら工場で数日間作業してみる
- 飲食店を買収したら、社長自らホールやキッチンで働いてみる
- 介護施設を買収したら、社長自ら介護業務を体験してみる
現場の苦労を理解しない経営者の言葉は、従業員の心に響きません。トップが「現場のことを分かっている」という信頼があってこそ、変革を受け入れてもらえるのです。
応用ポイント2:100日以内に「見える成果」を出す
newmoの100日プランのように、買収後早期に「見える成果」を出すことが重要です。デジタルツールの導入、業務効率化、働き方の改善など、従業員が実感できる変化を短期間で実現することで、「この会社に買収されて良かった」という納得感が生まれます。
応用ポイント3:「接客業」という再定義
newmoがタクシーを「接客業」と再定義したように、自社の事業を異なる視点で捉え直すことで、新しい価値が見えてきます。
地方企業の例で言えば:
- 建設業を「住まいの困りごと解決業」と再定義
- 製造業を「お客様の課題解決パートナー」と再定義
- 小売業を「地域のライフスタイル提案業」と再定義
事業の再定義は、従業員のマインドセットを変え、サービス品質の向上につながります。
このポイントについては、以下の記事でも顧客の深層的な願望(インサイト)の捉え方について詳しく記載しています。
具体的な実践方法
- 買収前にPMI計画を策定(100日以内に実施する施策のリスト化)
- 買収完了後、1週間以内にトップが買収先企業を訪問し、全従業員と対話
- 月次で進捗をモニタリングし、計画を柔軟に修正
- 3ヶ月以内に「小さな成功」を積み重ね、従業員の信頼を獲得
ポイント③ 伝統的産業×DX – デジタル化で生産性を劇的に向上
営業所単位の管理会計導入
newmoのPMIにおいて特に重要だったのは、タクシー会社の営業所単位の管理会計の導入です。
買収前の未来都では、「どの営業所が黒字で赤字なのかもわかっていなかった」という状況でした。全社の売上や利益は把握していても、営業所ごとの収益性が不明確だったため、どこに経営資源を集中すべきか判断できなかったのです。
newmoは、営業所ごとの売上、コスト、利益を明確化し、オペレーションの効率や目標数字を可視化しました。これにより、黒字営業所のノウハウを赤字営業所に横展開したり、赤字営業所の問題点を特定して改善策を講じることが可能になりました。
管理会計導入の効果:
- 各営業所の収益性が明確化
- 効率的な営業所と非効率な営業所の差分が可視化
- 改善すべきポイントの特定が容易に
- 営業所長がデータに基づいた意思決定をできるように
配車業務の効率化とAI活用
未来都では1日1,000件以上の電話配車依頼があり、その半数が電話予約です。しかし、電話が繋がらないと顧客離れにつながってしまいます。
newmoは、AIを活用した配車業務の効率化に取り組んでいます。具体的には:
- 電話配車の自動応答システム
- AIによる最適配車アルゴリズム
- 需要予測に基づくドライバー配置
これにより、取りこぼしによる3割のビジネスチャンスの損失をなくすことを目指しています。3割という数字は非常に大きく、これが改善されれば売上は大幅に向上します。
バックオフィスのデジタル化
タクシー業界のバックオフィス業務は、非常にアナログで非効率的です。newmoは、CFOの武藤氏とCTOの曾川氏が主導し、経理や労務などのバックオフィス業務を改善しています。
具体的な施策:
- グループ横断でのツール導入(会計ソフト、勤怠管理システムなど)
- データ統合(各営業所のバラバラなデータを一元管理)
- ローカルデータのクラウド・オンライン化
- 給与計算や会計システムとの連動
これらのデジタル化により、本社のバックオフィス担当者の業務負荷が大幅に削減され、その分の人員を成長分野に振り向けることができます。
自動点呼システムの導入
タクシー事業では、運転手の出勤時と退勤時に、管理者が対面で健康状態やアルコールチェックを行う「点呼」が法律で義務付けられています。
従来は、管理者が24時間体制で営業所にいる必要がありましたが、newmoは自動点呼システムを導入しました。これは、ドライバーが自分でタブレット端末を使って健康状態を入力し、アルコールチェッカーで測定する仕組みです。
この導入により:
- 管理者の労働時間削減
- 深夜・早朝の点呼業務からの解放
- データの自動記録による管理業務の効率化
が実現しました。
地方企業が学べること:段階的なDX推進
newmoのDX戦略は、地方の伝統的産業にも大いに参考になります。
応用ポイント1:「見える化」から始める
まずは営業所ごと、部門ごと、製品ごとの収益性を「見える化」することから始めましょう。多くの地方企業では、全社の売上・利益は把握していても、どの部門や製品が稼いでいるのか明確でない場合があります。
管理会計を導入し、セグメント別の収益性を把握することで、経営判断の精度が大きく向上します。
応用ポイント2:ボトルネックを特定する
newmoが配車業務の「3割の損失」を特定したように、自社の業務フローの中で最大のボトルネックがどこにあるのかを特定することが重要です。
地方企業の例で言えば:
- 製造業:どの工程が全体のボトルネックになっているか
- 小売業:どの時間帯にレジ待ちが発生し、機会損失が生まれているか
- 建設業:どの作業に最も時間がかかり、工期遅延の原因になっているか
ボトルネックを特定し、そこにデジタル技術を投入することで、最大の効果が得られます。
応用ポイント3:小さく始めて横展開する
newmoのように、まず1つの営業所や1つの業務プロセスでデジタル化を試し、成功したら他の営業所に横展開するというアプローチが現実的です。
いきなり全社で大規模なシステムを導入すると、失敗のリスクが高く、コストも膨大になります。まずは小規模に試して「勝ち筋」を見つけ、それを横展開していく方が成功確率が高まります。
応用ポイント4:従業員体験の向上を最優先する
newmoが「ドライバーがハッピーに働ける環境」を重視しているように、デジタル化の目的は「従業員の業務負荷を減らし、働きやすい環境を作ること」にあります。
単なる効率化や人員削減を目的とするのではなく、「従業員がより価値の高い仕事に集中できるようにする」という視点が重要です。この姿勢があってこそ、現場がデジタル化を前向きに受け入れてくれます。
具体的な実践方法
- 現状把握(1ヶ月)
- 各部門の売上・利益を可視化
- 業務フローの棚卸しとボトルネック特定
- 従業員へのヒアリング(何が一番大変か)
- 小規模テスト(3ヶ月)
- 1つの部門や営業所でデジタルツールを試験導入
- 効果測定(時間削減、売上向上、従業員満足度など)
- 課題の洗い出しと改善
- 横展開(6ヶ月〜1年)
- 成功した施策を他部門に展開
- 社内勉強会で成功事例を共有
- 段階的に全社展開
- 継続的改善
- 四半期ごとに効果を測定
- 従業員からのフィードバックを反映
- 次のデジタル化テーマを特定
M&Aをすぐに行わない企業でも使える – newmoの成長原則の応用
ここまでnewmoのM&A戦略とPMIを見てきましたが、「うちの会社はまだM&Aを検討する段階ではない」と感じる経営者も多いでしょう。しかし、newmoの成長原則は、M&Aを行わない企業にも応用できる普遍的な要素を含んでいます。
原則1:「中から変える」という姿勢
newmoが「外から批判するのではなく、中から変える」というアプローチを取ったように、自社の業界や地域コミュニティに対しても、同じ姿勢が有効です。
地方企業への応用
「行政が何もしてくれない」「業界団体が古い」と批判するのではなく、自らが業界団体の役員になったり、商工会議所の活動に積極的に参加することで、内側から変革を推進できます。
外から文句を言うだけでは何も変わりませんが、内側に入って信頼関係を築いてから提案すれば、受け入れられる可能性が高まります。
原則2:トップが現場を理解する
青柳CEOが二種免許を取得し、実際に乗務したように、経営者が現場を本当に理解することの重要性は、どの業種にも共通します。
地方企業への応用
- 社長が年に数回、現場で実際に作業してみる
- 営業に同行し、顧客の生の声を聞く
- コールセンターに入り、顧客からのクレームに対応してみる
経営者が現場を理解していれば、的確な経営判断ができるだけでなく、従業員からの信頼も得られます。「社長は現場のことを分かっている」という認識が、組織の一体感を生むのです。
原則3:「見える化」から始めるDX
newmoが営業所単位の管理会計を導入したように、まずは現状を「見える化」することがDXの第一歩です。
地方企業への応用
デジタル化というと、高額なシステム導入を想像しがちですが、まずはエクセルでも構いません。部門別、製品別、顧客別の売上や利益を可視化するだけで、経営の解像度が大きく上がります。
見える化により、どこが稼いでいて、どこが赤字なのかが明確になれば、経営資源の配分を最適化できます。
原則4:採用が根幹
newmoが「採用が根幹」と認識したように、成長企業にとって人材確保は最重要課題です。
地方企業への応用
多くの地方企業は「良い人材が来ない」と嘆きますが、「良い人材が来たくなる会社」になっているでしょうか。
newmoは、デジタル化による業務効率化と従業員体験の向上により、応募数1.5倍、内定率2倍を実現しました。採用の課題は、実は「会社の魅力」の課題なのです。
働きやすい環境、成長できる機会、明確なビジョン。これらを整備し、発信することで、人材は集まってきます。
このポイントについては、以下の記事でも採用活動の第一歩となる求人票作成の手法について詳しく記載しています。
原則5:小さく始めて横展開する
newmoのロールアップ戦略は「勝ち筋を見つけて横展開」というアプローチですが、これはM&A以外でも有効です。
地方企業への応用
新しい取り組みを始めるとき、いきなり全社で実施するのではなく、まず1つの店舗、1つの営業所、1つのチームで試してみます。成功したら、そのノウハウを他に横展開していくのです。
例:
- 新しい販売手法を1店舗で試す → 成功したら全店舗に展開
- 新しい製造プロセスを1ラインで試す → 成功したら他ラインに展開
- 新しい営業スタイルを1チームで試す → 成功したら全営業部に展開
小さく始めることで、失敗のコストを最小化しながら、成功確率を高められます。
まとめ:伝統的産業こそ、変革の余地がある
newmoの成長戦略から学べることは、M&Aという手法の巧みさだけではありません。その根底には、規模や業種を問わず応用できる普遍的な成長原則があります。
1. 「中から変える」という現実的なアプローチ
外から批判するのではなく、内側に入って信頼関係を築きながら変革を進める。これは、規制産業や伝統的産業において特に有効なアプローチです。
2. 「100日プラン」による明確で迅速な統合
買収前に統合計画を策定し、買収完了と同時に実行を開始する。早期に「見える成果」を出すことで、従業員の信頼を獲得できます。
3. 「心のPMI」 – トップが現場を理解する
青柳CEOが二種免許を取得したように、トップ自らが現場に入り、従業員の苦労を理解することが、変革を受け入れてもらうための前提条件です。
4. 伝統的産業×DX – デジタル化で生産性を劇的に向上
タクシー業界のような伝統的産業こそ、デジタル化の余地が大きく、改善効果も大きくなります。「見える化」から始め、ボトルネックを特定し、小さく試して横展開する。
5. 採用が根幹 – 従業員体験の向上
業務効率化や働き方改革により従業員がハッピーに働ける環境を作ることが、採用力の強化につながります。
newmoの取り組みは、「伝統的産業は成長の余地がない」という先入観を覆すものです。むしろ、デジタル化が遅れている産業ほど、改善の余地が大きく、競争優位を築けるチャンスがあるのです。
地方の伝統的産業に携わる経営者の皆さまにとって、newmoの事例は「自分たちの業界でも、まだまだできることがある」という希望を与えてくれるでしょう。重要なのは、外から批判するのではなく、内側から変革を起こす勇気と実行力です。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。