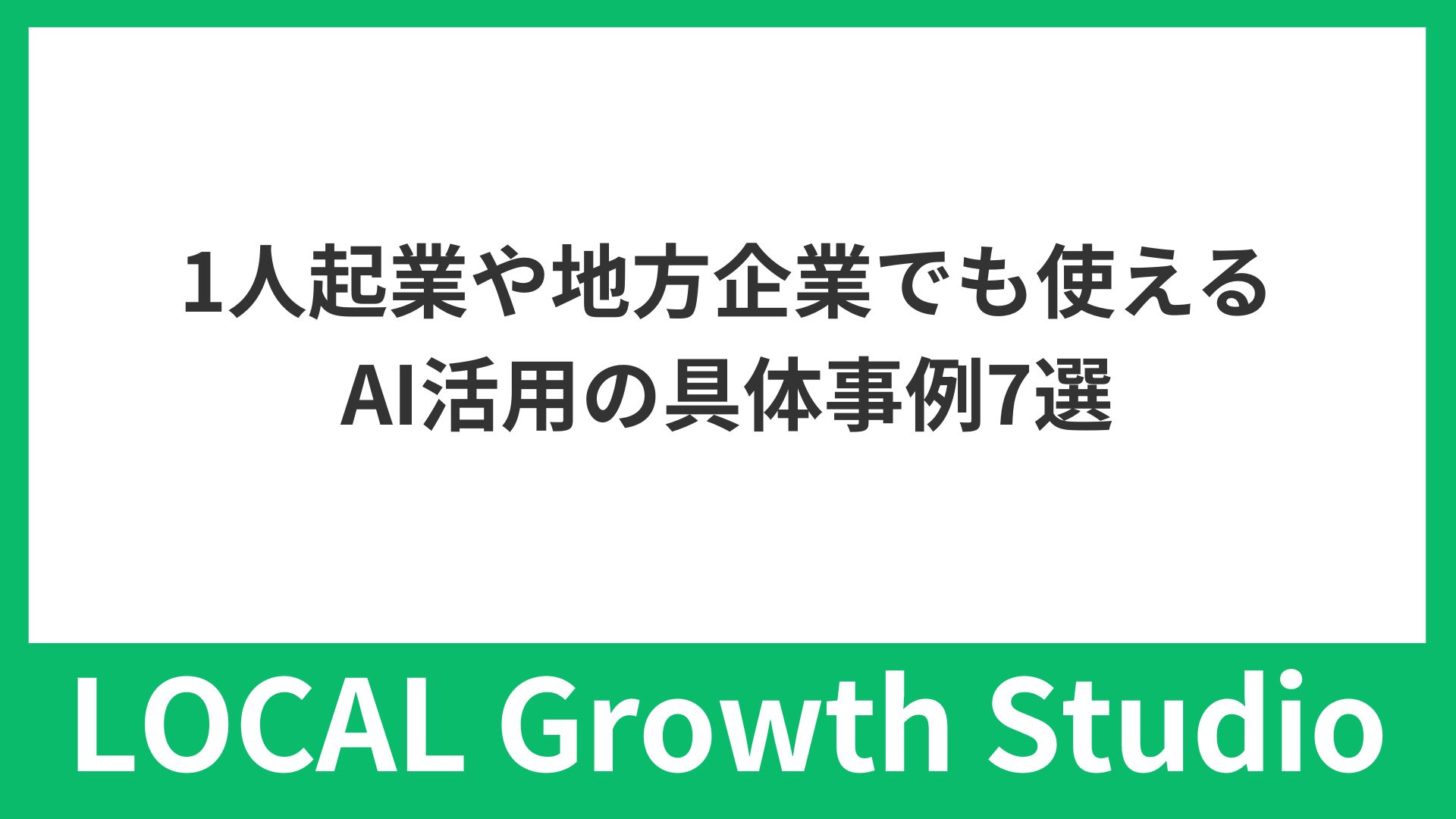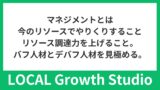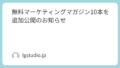ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
私は2017年に1度起業をし、今回2025年に2度目の起業を行いました。その比較の中で、格段に起業がしやすくなったと感じており、その理由はAIとリモート環境前提の業務サービスが拡充したことでした。
リモート環境前提の業務サービスとは、オンライン面談ツールやバーチャルオフィスなどの事を指し、今までなら数万円〜数十万円かかっていた登記用の住所確保が月々1,500円程度になったり、デジタルで様々なことができるようになった結果、用意するべき設備や機器が最小で済ませられるようになりました。
この記事では、特にAIの部分に焦点をあて、詳しく活用事例をご紹介していきます。実際の活用事例をもとに、AIツールの具体的な使い方を7つのシーンに分けて紹介します。「AIは難しそう」と感じている方にこそ読んでいただきたい内容です。実際に使ってみると、思っているよりずっとシンプルで、確実に業務の効率化につながります。
この記事はポッドキャストでも音声解説を行っております。各種サイトで無料で聞くことができます。
AIが起業のハードルを劇的に下げた
2017年と2025年、起業環境の違い
2017年の起業と2025年の起業を比較すると、AIツールの普及により、業務環境が大きく変わっています。
2017年の起業時:
- わからないことがあれば、書籍を購入して勉強するか、詳しい人に教わる必要がありました
- ウェブサイトを作るには、制作を外注に依頼するか、ノーコードツールでの制作で機能に制約がある状態で作成する必要がありました
- 経理の仕訳で迷ったときは、ネットで細かく調べるか、税理士に確認するまで待つ必要がありました
- 文章を書くための調べものや精査に時間がかかり、コンテンツ作成の頻度をあげることができませんでした
2025年の起業時、AIでできること:
- わからないことを質問すると、すぐに基本的な回答が得られます
- ウェブサイトのコードを生成してもらえます(修正も即座に対応可能)
- 経理の仕訳や法律の基礎知識をその場で確認できます
- 文章の読みやすさをチェックしてもらえます
限られた予算と時間の中で、やりたいことを進められる環境が整ってきています。特に人手が限られている企業にとっては、大きな変化です。
AI活用の本質
AI活用で最も大きく変わるのは、業務のスピードです。
調べ物をするとき、以前はGoogle検索で複数のページを見て回っていました。今はAIに質問すると、すぐに要点をまとめて教えてくれます。ウェブサイトのコードを修正したいとき、以前は外注して返事を待つ必要がありました。今は「このコードを修正してください」とAIに依頼すれば、すぐに対応してくれます。
このスピードアップにより、限られた時間の中で、より多くの施策を試せるようになりました。試して、うまくいかなければ修正して、また試す。この改善サイクルを速く回せることが、最も大きな効果だと考えています。
また、AI活用は「特別なスキル」ではありません。スマートフォンを使えるレベルの知識があれば、誰でも活用できます。プログラミングの知識は不要です。
AI活用の本質は、以下の3点にあります:
- 強みを伸ばす:自分が得意なこと(営業、企画、技術など)に集中し、それ以外はAIに補完してもらう
- 知識の格差を埋める:都市部と地方、大企業と中小企業の知識格差をAIで埋める
- スピードを上げる:さまざまな業務のスピードを上げ、より多くの施策を試し、改善サイクルを回す
よく使われているAIツール
この記事で紹介する活用事例では、主に以下の2つのAIツールを使用しています。
Claude:自分に合うAIを選ぶ
この記事で紹介する事例では、主にClaude(クロード)を使用しています。ChatGPTやGeminiも試しましたが、最終的にClaudeを選びました。
選んだ理由は、質問に対する回答の質が好みに合っていたからです。これは個人の好みなので、ChatGPTはプラグインが豊富、Geminiは無料版の性能が高いなど、それぞれに強みを調べて自分のメインAIをお選びください。まずは複数のツールを試して、自分が使いやすいと感じるものを選ぶことをお勧めします。
NotebookLM:情報整理を効率化する
情報収集においては、NotebookLM(ノートブックLM)が活用されています。これはGoogleが提供する、資料を読み込んで要約してくれるツールです。
特に便利なのは、記事のURLやYouTubeのリンクを貼るだけで、すべて読み取ってくれる点です。通常、動画を見ながらメモを取るのは時間がかかりますが、NotebookLMなら動画や記事を登録しておいて、後から「この3つの動画に共通するポイントは何か」と質問すれば、まとめて教えてくれます。
例えば、「M&A」について学びたいとき、関連する記事や動画を10個ほどNotebookLMに登録しておきます。その後「地方企業がM&Aで成長するポイントは何か」と質問すると、10個の情報を横断的に分析して、要点を抽出してくれます。この要約をさらにClaudeに読み込ませて、記事を書くこともできます。
AI活用の具体シーン7選
ここからは、実際の業務でAIがどのように活用されているか、具体的なシーンを7つ紹介します。
シーン① 法律や経理などルールのあるもののチェック
活用シーン: 起業するときや新しい事業を始めるとき、法律や経理のルールについて確認が必要になります。税理士や弁護士に相談するのが最も確実ですが、「これは専門家に聞くべきレベルか、自分で調べられるレベルか」の判断が難しいケースもあります。
AIの活用方法:
基本的な知識であれば、AIに質問することで、すぐに確認できます。
質問例:
- 「飲食店を開業するのに必要な許認可を教えてください。福岡県で開業予定です」
- 「取引先との打ち合わせで使ったカフェ代3,000円は、どの勘定科目で処理すればよいですか」
- 「宅地建物取引士の資格を取りたいのですが、必要な勉強時間と効率的な勉強法を教えてください」
基礎知識を事前にAIで確認しておくことで、専門家に相談する際も「この点だけ確認したい」と具体的に質問できるため、相談時間を効率的に使えます。
注意点: AIの回答はあくまで参考情報です。最終的な判断や重要な手続きは、必ず専門家(税理士、弁護士、行政書士など)に確認してください。AIは「最初の一歩」を早めるツールとして活用しています。
シーン② 最適なツールの選定と実装
活用シーン: ウェブサイトを作りたい、マーケティングツールを導入したいというとき、「どれを選べばよいか」の判断に迷うことがあります。また、選定後も実装に専門知識が必要になるケースがあります。
AIの活用方法:
ツール選定の相談: 「建設業向けのマーケティングサイトを作りたいです。WordPressの無料テーマでおすすめはありますか。SEO対策がしやすく、初心者でもカスタマイズしやすいものを教えてください」
このように質問すると、候補を複数提示してくれて、それぞれのメリット・デメリットも説明してくれます。
実装のサポート: 実際に、WordPressとCocoon(無料テーマ)で2つのサイトを構築した事例があります。費用は、ドメイン代とサーバー代のみで、年間1サイトあたり約1万円でした。
実装時には、以下のようにAIを活用できます:
- 画面のイメージを共有する スクリーンショットを添付して、「このようなヘッダーを作りたいのですが、CocoonのカスタムCSSでどのように実装できますか」と質問します
- コードを生成してもらう 「3カラムのブログカード風で、最新記事3件を表示したいです。HTMLとCSSを書いてください」
- エラーを修正してもらう 「このコードを実装したら、スマホ表示が崩れました。レスポンシブ対応に修正してください」
外注すると数日かかる作業を、その場で解決できるのは大きなメリットです。
シーン③ 技術系の細かな質問を即座に解決
活用シーン: Google Analytics 4(GA4)のタグ埋め込み、Search Consoleの設定など、デジタルマーケティングツールには細かな設定が多く、公式ドキュメントを読むだけでも時間がかかります。
AIの活用方法:
質問例:
- 「WordPressのCocoonテーマで、GA4のタグを埋め込む方法を教えてください」
- 「Search Consoleで『クロール済み – インデックス未登録』というエラーが出ています。原因と対処法を教えてください」
- 「Google Tag Managerで、特定のボタンのクリック数を計測したいです。設定手順を教えてください」
Googleで検索して正解を探すより、AIに質問した方が効率的です。
効果的な質問のコツ: できるだけ具体的な情報を伝えると、精度の高い回答が得られます。
- 使っているツール名(WordPress、Cocoonなど)
- エラーメッセージがあれば全文
- 実現したい具体的な動作
これらの情報を含めて質問すると、そのまま使える回答が返ってくることが多いです。
シーン④ 人材の相性確認と採用判断
活用シーン: 採用は企業成長において重要な意思決定の一つですが、「スキルは十分だが、チームにフィットするか」という点で迷うケースがあります。特に小規模組織では、1人の採用が組織全体に与える影響が大きくなります。
AIの活用方法:
このアプローチは、yutori社の事例を参考にしています。yutori社では、MBTIやストレングスファインダーなどの性格診断・強み診断を活用し、さらに生年月日をもとにした動物占いや算命学も取り入れています。
同様の方法で、AIを使った相性確認ができます:
質問の流れ:
まず代表やチームメンバーの情報を入力します。 「私のMBTIはINTJ(建築家型)で、ストレングスファインダーのTop5は『戦略性、学習欲、最上志向、着想、分析思考』です。現在のチームはENFPとISTPです」
次に候補者の情報を入力します。 「採用候補者はESFJ(領事官型)で、Top5は『共感性、調和性、責任感、親密性、適応性』です」
そしてAIに質問します。 「この人を採用した場合、チームとしてどのような相乗効果が期待できますか。また、注意点があれば教えてください」
AIの回答例: 「INTJ(戦略的・論理的)とESFJ(共感的・調和重視)の組み合わせは補完関係になる可能性があります。INTJが見落としがちな『チームの感情面のケア』や『関係性の構築』をESFJが担うことで、組織の安定性が高まります。ただし、意思決定のスピード感に差が出る可能性があるため、重要な決定事項については事前に十分なコミュニケーションを取ることが重要です」
このような分析により、採用後のミスマッチを減らし、チームの多様性を意識した採用に役立てることができます。
注意点: 性格診断や占いは、あくまで参考情報の一つです。最終的な採用判断は、面接での対話や実務スキルの確認など、総合的に行うことが重要です。
このポイントについては、以下の記事でもチーム構築における人材のフィットの重要性について詳しく記載しています。
シーン⑤ 文章の推敲や校正
活用シーン: 記事やブログを執筆する際、「わかりやすく書く」ことは簡単ではありません。自分では当たり前と思って使っている専門用語が、読者には難しい場合があります。
AIの活用方法:
記事執筆では、以下のようにAIを活用できます。
まず自分で執筆する: これは重要なポイントです。AIに丸投げするのではなく、まず自分の言葉で書きます。
AIに推敲を依頼する: 「この記事を読みやすくするために、以下の点を改善してください。
- 専門用語に注釈を加える
- 長い文章を短く分割する
- 読者が理解しやすい順序に並び替える
- 具体例を追加すべき箇所を指摘する」
タイトルや要約も依頼する: 「この記事のタイトル候補を5つ提案してください。SEOを意識し、かつクリックしたくなるタイトルでお願いします」 「この記事の要約を200文字以内で作成してください」
このような活用により、記事の推敲にかかる時間が短縮され、読みやすさも向上します。
この記事での活用: 実際に、この記事も骨子を執筆した後、Claudeに「地方企業の経営者が読みやすいように、専門用語に注釈を加え、具体例を増やしてください」と依頼しています。タイトルや見出しも、複数の候補から選択しました。
シーン⑥ プロジェクト機能で学習内容をテーマ別に管理
活用シーン: AIとのチャットが長くなると、応答速度が遅くなることがあります。また、新しいチャットを始めると、過去の情報が引き継がれないため、同じ説明を繰り返す必要があります。
AIの活用方法:
ClaudeやChatGPTには「プロジェクト機能」(ツールによって名称は異なります)があり、これを活用することで、テーマ別に過去の学習内容を引き継げます。
プロジェクトの分け方の例:
- 経理・法務などのコーポレート関連
- 会計処理の質問履歴
- 法律や許認可の確認履歴
- 社内規程や労務管理の相談履歴
- マーケティング関連
- SEO対策の施策履歴
- 記事執筆の推敲履歴
- ウェブサイトのコード修正履歴
- 人材採用・人材紹介関連
- 採用要件の定義履歴
- 候補者の相性分析履歴
- 面接質問の作成履歴
効果的な使い方:
例えば「マーケティング関連」のプロジェクトには、以下のような情報を最初に登録しておきます:
- 自社のターゲット顧客(地方企業の経営者、40代以下)
- サービス内容(マーケティング支援、事業承継支援)
- 過去に成果が出た施策(SEOコンテンツ、事例記事)
- 使用しているツール(WordPress、Cocoon、GA4、Search Console)
このように設定しておくと、新しいチャットを始めても、過去の文脈を理解した上で回答してくれます。
チャットの応答速度を維持できるだけでなく、テーマごとに情報が整理されるため、後で見返すのも効率的です。
注意点: プロジェクトは3〜5個程度に絞ることをお勧めします。細かく分けすぎると、「どのプロジェクトで質問すればよいか」の判断に迷い、かえって非効率になります。
シーン⑦ 情報収集と要約のスピードアップ
活用シーン: 事業戦略を立てる際や、新しい施策を検討する際には、業界動向や競合分析、成功事例のリサーチが必要です。しかし、複数の記事や動画を見て、要点をまとめる作業には時間がかかります。
AIの活用方法:
NotebookLMを使った情報収集は、以下のような流れで進められます。
リサーチテーマを決める: 例えば「地方企業のM&A成功事例」
関連する記事や動画を集める:
- GENDA社のM&A戦略に関する記事(URL)
- yutori社の決算説明資料(PDF)
- newmo社の経営者インタビュー動画(YouTube)
- クアンド社のPMI事例記事(URL)
NotebookLMにすべて登録する: 「M&A事例研究」というノートブックを作成し、そこにすべてのソースを登録します。
質問して要約を得る: 「地方企業がM&Aで成長するために、最も重要なポイントを3つにまとめてください。各社の事例を引用しながら説明してください」
このような活用により、リサーチにかかる時間が短縮され、複数の情報源を横断的に分析できるため、見落としも減ります。
実際の活用例: 「○○社に学ぶシリーズ」の記事を作成する際も、NotebookLMで各社のIR資料、インタビュー記事、YouTube動画を読み込ませて、要約を作成しています。その要約をClaudeに読み込ませて、記事の骨子を作成する流れです。
地方企業がAI活用で得られる3つのメリット
ここまで具体的な活用シーンを紹介してきましたが、地方企業がAIを活用することで得られるメリットを、改めて整理します。
メリット① 人的リソースの制約を突破できる
地方企業の多くは、大企業のように専門部署を持つことが難しく、少人数で多くの業務をこなす必要があります。AIを活用することで、以下のような効果が得られます。
1人で複数の専門領域をカバーできる:
- 経理担当者がいない場合 → AIで仕訳をチェック
- マーケティング担当者がいない場合 → AIでSEO記事を推敲
- 法務担当者がいない場合 → AIで契約書の条文を確認
業務のスピードが向上する: 調べ物、文章作成、コード修正など、多くの業務でAIを活用することで時間を短縮できます。外注して返事を待つよりも、その場で解決できることが増えます。
「やりたいことはあるが、人手が足りない」という企業にとって、大きなメリットがあると考えています。
メリット② 初期投資を大幅に削減できる
2017年の起業時と比較すると、初期投資が大幅に削減できるようになりました。
2017年の起業時に必要だった投資:
- ノーコードツールでのウェブサイト制作
- ロゴやデザイン制作外注
- 法律・会計の調査や問い合わせの膨大な時間
2025年、AIを活用すると:
- ウェブサイト:年間約1万円(ドメイン+サーバー代のみ)
- ロゴやデザイン:デザインツールのAI機能を使い、内製化
- 法律・会計:基礎知識はAIで習得し、重要事項のみ専門家に確認
初期投資を抑えられるため、「まずは小さく始めて、成果が出たら投資を増やす」という柔軟な事業運営が可能になります。
メリット③ 知識の格差を埋められる
地方企業が都市部の企業と競争する際の大きな課題の一つが「知識の格差」です。都市部には、最新のマーケティング手法やデジタルツールに詳しい人材が集まりやすく、セミナーやイベントも豊富にあります。
一方、地方企業は以下のような状況にあります:
- 最新のマーケティング手法を学ぶ機会が少ない
- デジタルツールに詳しい人材が採用しにくい
- セミナーやイベントに参加するための移動コストが高い
AIは、この知識の格差を埋めるツールになります。
AIで得られる知識:
- 最新のSEO対策やSNSマーケティングの手法
- デジタルツールの使い方(GA4、GTM、Search Consoleなど)
- 業界の成功事例や競合分析
- 法律や会計の基礎知識
地方にいながらにして、都市部の企業と同じレベルの知識を得ることができます。これは大きな変化だと感じています。
AI活用を始めるには
「AIを使ってみたいが、何から始めればよいかわからない」という方向けに、具体的なステップを紹介します。
まずは無料版で試す(1週間程度)
目標:AIツールの使い方に慣れる
- ClaudeまたはChatGPTの無料版に登録
- Claude:https://claude.ai/
- ChatGPT:https://chatgpt.com/
- 簡単な質問から始める
- 「建設業の市場規模を教えてください」
- 「SEO対策の基本を教えてください」
- 「私の会社の強みを整理したいです。質問してください」
- 実際の業務で使ってみる
- 経理の仕訳を確認
- メールの文章を推敲
- 会議の議事録を要約
この段階では、「AIに質問すれば、それなりの回答が返ってくる」という感覚を掴むことが目標です。
有料版で本格的に活用する(1ヶ月程度)
目標:業務に組み込み、効果を実感する
無料版で使い方に慣れたら、有料版に切り替えることをお勧めします。有料版は応答速度が速く、長い文章も読み込めるため、実務での活用がスムーズになります。
- 有料版に登録
- Claude ProまたはChatGPT Plus:月額20ドル(約3,000円)
- プロジェクト機能を使い始める
- 「経理・法務」「マーケティング」「採用」など、3つ程度のプロジェクトを作成
- 自社の情報や過去の質問履歴を整理しておく
- 効果を記録する
- AIを使うことで、どの業務がどれくらい効率化されたかを記録
- 例:「記事の推敲時間が短縮された」「調べ物が早くなった」
この段階では、「月額3,000円以上の価値がある」と実感できることが目標です。
チーム全体で活用する(3ヶ月以降)
目標:組織全体でAI活用を定着させる
- 社内勉強会を開く
- AIの基本的な使い方を共有
- 各メンバーが試した活用事例を発表
- 「どの業務にAIを使えるか」をみんなで考える
- 活用事例を共有する
- SlackやチャットツールにAI活用チャンネルを作成
- 「こんな使い方が便利だった」という事例を共有
- 成功事例を表彰する
- 業務マニュアルに組み込む
- 「記事執筆時はAIで推敲する」
- 「経理の仕訳で迷ったらAIに確認する」
- 「新しいツールを使う前にAIで使い方を確認する」
この段階では、AI活用が「特別なこと」ではなく、「当たり前の業務プロセス」になることが目標です。
まとめ
この記事では、AIツールを活用した7つの具体的なシーンを紹介しました。
- 法律や経理のルール確認
- ツールの選定と実装
- 技術系の細かな質問の解決
- 人材の相性確認
- 文章の推敲や校正
- プロジェクト機能での情報管理
- 情報収集と要約
実際に使える活用シーンを具体的にお伝えしました。ぜひ使えそうなものから活用してみてください。成長中の起業や地方企業ほど、AIによる知識やスピードの改善効果を実感できると思います。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。