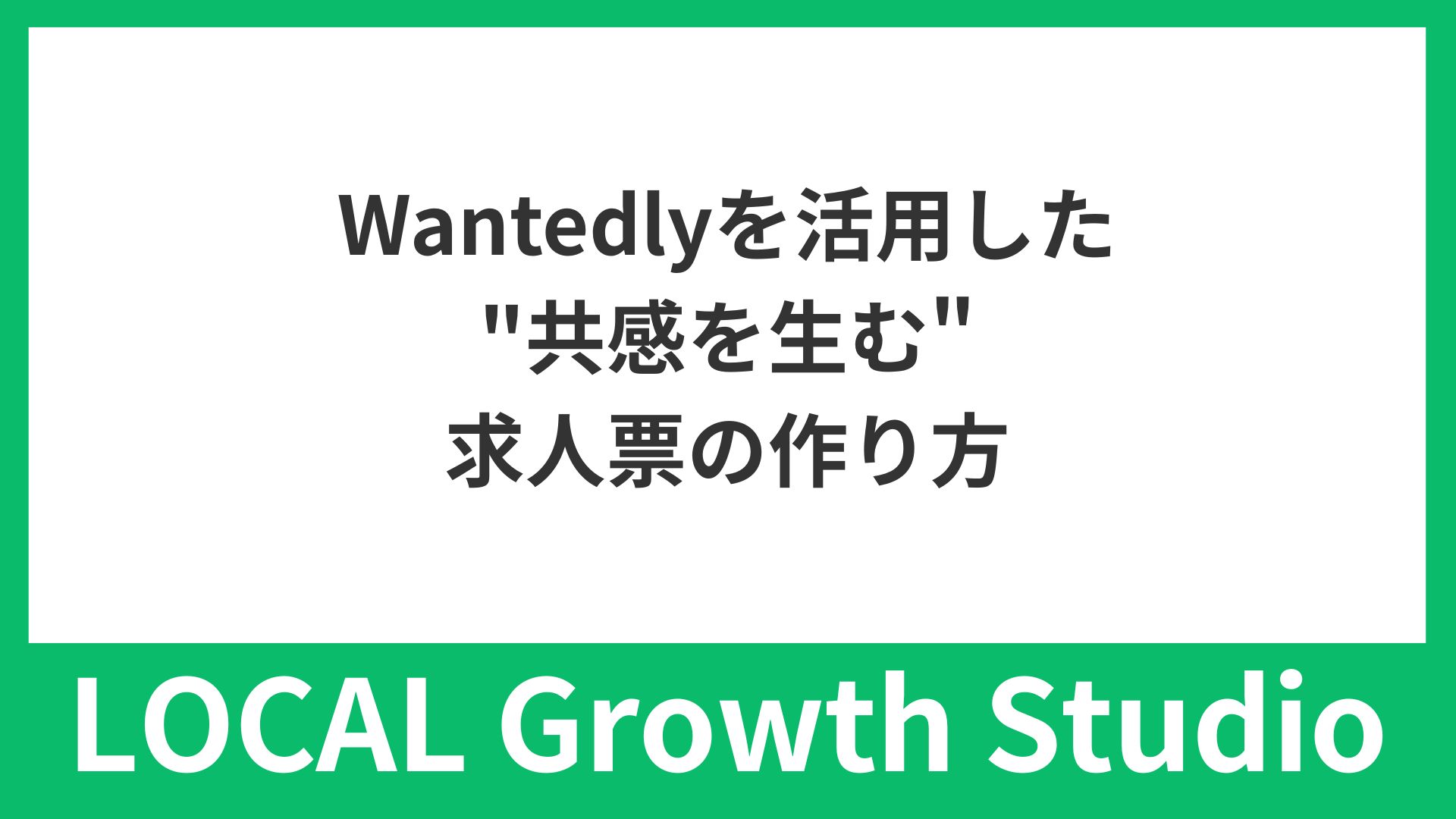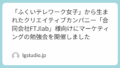ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
この記事は、「Wantedlyを活用した”共感を生む”求人票の作り方」について記載しています。
なぜ「良い求人票」が重要なのか
採用活動において、求人票は候補者との最初の接点となる極めて重要なツールです。しかし、多くの企業が「求人票は人事が書くもの」「テンプレートに沿って書けばいい」と考え、戦略的に設計していないのが実情です。
特に地方企業を取り巻く採用環境は、年々厳しさを増しています。近年、大手企業が新卒給与を軒並み引き上げており、地方大学の優秀な学生も都市部の大手企業に取られてしまうケースが増えています。給与や福利厚生といった条件面だけで競争しようとすると、地方企業にとっては非常に厳しい戦いになります。
だからこそ、地方企業が採用を成功させるためには、「地域に対する想い」や「職場の魅力」を丁寧に伝え、総合的な満足度を高めていくアプローチが必要です。給与という一つの要素だけでなく、「この会社で働く意義」「成長できる環境」「地域への貢献」といった多面的な価値を伝えることで、候補者の心を動かすことができます。
良い求人票とは、単にスキル要件や給与条件を並べたものではありません。自社のビジョンやカルチャーを丁寧に伝え、候補者が「ここで働きたい」と感じる動機を喚起するコミュニケーションツールです。そして、これは高額な採用費をかけなくても、無料のツールを活用して十分に実現できます。本記事では、その具体的な方法を段階的に解説していきます。
Wantedlyを活用した求人票設計の実践
Wantedlyとは何か
Wantedlyは、企業のミッションやビジョンへの「共感」を軸に、求職者と企業をマッチングするビジネスSNSです。従来の求人サイトが給与や待遇を前面に押し出すのに対し、Wantedlyは企業のストーリーを重視する設計になっています。
特徴的なのは、Wantedlyが求人票を「なにをやっているのか」「なぜやるのか」「どうやっているのか」「こんなことやります」という4つの項目で構成している点です。この構成に沿って自社の情報を整理していくことで、自然とリッチで魅力的な文章が書けるようになります。
この特性は、地方企業にとって大きな武器となります。前述の通り、給与水準や福利厚生だけでは都市部の大手企業に勝てない中で、ビジョンやカルチャー、地域への想いといった価値で候補者の共感を得ることができるからです。
競合分析から始める求人票設計
良い求人票を作るために、まずは同じ職種で人気のある他社の求人票を分析することから始めましょう。具体的な手順は以下の通りです。
ステップ1:類似職種の検索とピックアップ Wantedlyで自社が募集したい職種(例:Webマーケター、営業、エンジニアなど)を検索し、人気順で5社程度をピックアップします。この際、必ずしも同業種である必要はありません。むしろ、異業種であっても職種が同じであれば、新しい視点が得られることが多いです。
ステップ2:構造化された分析 ピックアップした5社の求人票について、Wantedlyの4つの項目に沿って、スプレッドシートやExcelで表にまとめていきます。
- なにをやっているのか:事業内容、サービス概要、取り組んでいる課題
- なぜやるのか:ミッション、ビジョン、社会的意義、創業の背景
- どうやっているのか:仕事の進め方、チーム体制、使用ツール、働き方の特徴
- こんなことやります:具体的な業務内容、期待される役割、キャリアパス
この分析を通じて見えてくるのは、人気のある求人票に共通するパターンです。例えば、「なぜやるのか」のセクションで創業ストーリーや社会課題への問題意識を丁寧に語っている企業は、共感を得やすい傾向にあります。また、「こんなことやります」のセクションで、単なる業務内容の羅列ではなく、「入社後3ヶ月でこんな成果を出してほしい」といった具体的な期待値を示している企業も印象に残ります。
ステップ3:自社の独自性を明確にする 他社の整理が終わったら、同じ表に自社の欄を作り、埋めていく作業に入ります。ここで重要なのは、「他社との差別化ポイント」を意識することです。
例えば、以下のような問いを自分に投げかけてみましょう。
- 自社が取り組んでいる事業の中で、最もユニークな点は何か?
- なぜ今、この事業に取り組む必要があるのか?(社会的背景や市場機会)
- 自社ならではの仕事の進め方や文化は何か?(意思決定のスピード、裁量の広さ、チームの雰囲気など)
- この職種で入社した人に、どんな成長機会を提供できるのか?
この問いに答えていくプロセスで、自社の独自性が浮き彫りになります。そして、その独自性こそが、求人票における最大の武器となります。
伝え漏れをチェックする
自社の欄を埋めた後、もう一度他社の求人票と見比べてみましょう。チェックすべきポイントは以下の通りです。
- 情報の網羅性:他社が記載している重要な情報で、自社が伝え漏れている項目はないか?
- 具体性:抽象的な表現に留まっていないか?数値や具体例で補強できる箇所はないか?
- 魅力の伝達:自社の強みや魅力が、候補者に伝わる形で表現できているか?
例えば、「風通しの良い職場です」という表現は抽象的すぎます。これを「意思決定は週次のミーティングで全員参加で行い、入社1年目のメンバーの提案が事業方針になった事例もあります」と具体化することで、説得力が格段に増します。
採用における3つのフィット
良い求人票を作る上で、もう一つ重要な視点があります。それが採用における「3つのフィット」の考え方です。
3つのフィットとは
組織の採用において重要なのは、以下の3つの観点でのマッチングです。
- ビジョンフィット(目指す方向性) 候補者が共感できるミッションやビジョンを持っているか。組織が目指す未来と、候補者が実現したいキャリアの方向性が一致しているか。
- カルチャーフィット(居心地の良さ) 組織の価値観、働き方、コミュニケーションスタイルが候補者と合っているか。一緒に働くメンバーとの相性は良いか。
- スキルフィット(求められている成果とのマッチ度合い) 候補者が保有するスキルや経験が、求められる業務内容や成果と合致しているか。
この3つの中で、特にビジョンフィットとカルチャーフィットは、入社後に育成することが難しい要素です。スキルは研修やOJTを通じて向上させることができますが、価値観や働き方への考え方は、そう簡単には変わりません。
だからこそ、求人票の段階で、自社のビジョンやカルチャーを丁寧に伝え、共感してくれる候補者を惹きつけることが重要です。逆に言えば、ビジョンやカルチャーが合わない候補者を採用してしまうと、入社後のミスマッチが生じ、早期離職につながるリスクが高まります。
求人票でビジョンとカルチャーを伝える
では、具体的にどのように求人票でビジョンとカルチャーを伝えればよいのでしょうか。
ビジョンの伝え方 ビジョンは、Wantedlyの「なぜやるのか」のセクションで明確に語る必要があります。ここで重要なのは、単に美しい言葉を並べるのではなく、創業者や経営者の想い、解決したい社会課題、事業を通じて実現したい未来を、具体的なエピソードとともに伝えることです。
例えば、「地域を活性化する」という抽象的な表現よりも、「地元の商店街がシャッター街になっていく現状を見て、デジタルマーケティングの力で地域の店舗を支援したいと考えた」という具体的なストーリーの方が、候補者の心に響きます。
カルチャーの伝え方 カルチャーは、Wantedlyの「どうやっているのか」のセクションで伝えます。仕事の進め方、意思決定のプロセス、チームの雰囲気、評価制度などを具体的に記載しましょう。
例えば、以下のような表現が効果的です。
- 「毎週金曜日の午後は、全員参加のブレストタイムを設けています」
- 「リモートワークと出社のハイブリッド型で、自分の働きやすいスタイルを選べます」
- 「四半期ごとの評価面談では、数値目標だけでなく、チームへの貢献度も重視しています」
こうした具体的な情報により、候補者は「自分がこの組織で働くイメージ」を描きやすくなります。そして、そのイメージが自分の理想と一致していれば、応募への動機が高まります。
求人票の戦略的な使い分け
自社のテキストがまとまったら、次は求人票の「使い分け」を考える段階に入ります。実は、1職種につき2つの異なる求人票を作成しておくことを強く推奨します。
理想の人材求人
1つ目は、「理想の人材求人」です。これは、即戦力として活躍できる理想的な候補者を想定した求人票です。
記載内容のポイント
- 必須要件:職種に必要なスキルや経験を具体的かつ詳細に記載します。例えば、「Webマーケター募集」であれば、「Google広告、Facebook広告の運用経験3年以上」「月間予算500万円以上の運用実績」「Google Analytics、GTMを使った分析経験」といった具体的な要件を設定します。
- 歓迎要件:あると望ましいスキルや経験も明記します。例えば、「SEO施策の企画・実行経験」「MAツール(HubSpot、Marketo等)の利用経験」など。
- 給与テーブル:市場水準を踏まえた、やや高めの給与レンジを設定します。即戦力人材は他社からも引く手あまたであるため、給与面での競争力も重要です。
この求人票は、「今すぐにでも成果を出せる人材」を採用するためのものです。応募数は少ないかもしれませんが、応募してくる候補者の質は高い傾向にあります。
チャレンジ枠求人
2つ目は、「チャレンジ枠求人」です。これは、スキル面では理想に届いていないかもしれませんが、ビジョンやカルチャーへの共感が強く、成長意欲の高い候補者を惹きつけるための求人票です。
記載内容のポイント
- 必須要件:ゆるめに設定します。例えば、「Webマーケティングに興味があり、学習意欲が高い方」「データを元に課題を分析し、改善提案ができる方」といった、意欲やポテンシャルを重視した要件にします。
- ビジョン・カルチャーの強調:Wantedlyの「なぜやるのか」「どうやっているのか」のセクションを充実させ、候補者が共感できる要素を前面に出します。
- 成長機会の提示:「未経験からでも、半年後にはこんなスキルが身につきます」「先輩社員のサポート体制が充実しています」といった、成長環境をアピールします。
- 給与テーブル:市場の標準的なレンジか、やや控えめの設定でも良いでしょう。ただし、成長に応じた昇給の仕組みを明記することで、長期的なキャリアの展望を示します。
この求人票は、「ポテンシャル採用」の色合いが強いです。すぐには即戦力として機能しないかもしれませんが、ビジョンへの共感が強ければ、長期的に組織の中核を担う人材に育つ可能性があります。
なぜ2つの求人票が必要なのか
求人市場において、理想の人材がすぐに見つかるとは限りません。特に地方企業の場合、都市部と比較して候補者の母数が少ないため、理想の人材求人だけでは採用が充足しないケースも多いです。
一方で、チャレンジ枠求人を用意しておくことで、幅広い候補者との接点が生まれます。その中から、スキルは足りなくともビジョンやカルチャーにフィットする人材を見つけ、育成していくという選択肢が取れるようになります。
また、2つの求人票を並行して運用することで、「今すぐ欲しい即戦力」と「将来の組織を担う人材」の両方を、同時に採用していくことが可能になります。
オープンポジションという選択肢
求人票の戦略を考える上で、もう一つ検討すべきなのが「オープンポジション」の掲載です。
オープンポジションとは
オープンポジションとは、特定の職種や業務内容に限定せず、幅広い役割で人材を募集する求人票です。「一緒に事業を創っていく仲間を募集」「あなたの経験を活かせる役割を一緒に考えます」といった形で、柔軟な採用スタイルを取ります。
なぜオープンポジションが重要なのか
採用市場において、「今すぐ転職したい」と考えている候補者は全体の一部に過ぎません。多くの人は、「良い機会があれば転職を考えたい」「半年〜1年後には動きたい」というスタンスで、情報収集をしている段階です。
オープンポジションは、こうした「潜在的な転職候補者」との接点を作るための有効な手段です。具体的な職種が決まっていない段階でも、自社のビジョンやカルチャーに共感してくれる人材とコミュニケーションを取ることで、将来的な採用につなげることができます。
候補者にとってのメリット
求職者の視点に立つと、多くの求人票は「自分の経験の一部分しか重なっていない」と感じることが多いです。例えば、営業経験もあるし、マーケティングの知識もある、という候補者にとって、「営業職」「マーケター職」という括りの求人票では、自分の持つスキルセット全体を活かせるかどうかが見えにくいです。
オープンポジションは、そうした「複数の領域にまたがるスキルを持つ人材」や「幅広い業務にチャレンジしたい人材」にとって、魅力的な選択肢となります。特に、裁量の広さや新しいことに挑戦できる環境を求める候補者には、オープンポジションの柔軟性が大きな魅力として映ります。
オープンポジションの書き方
オープンポジションの求人票では、以下の点を重視します。
- ビジョンとカルチャーを全面に:職種が明確でない分、「何をするか」よりも「なぜやるか」「どう働くか」を丁寧に伝えます。
- 柔軟性をアピール:「あなたの経験やスキルに応じて、最適な役割を一緒に考えます」といったメッセージを盛り込みます。
- 具体的な事例を提示:過去にオープンポジションで入社した人が、どんな役割で活躍しているかを紹介すると、イメージが湧きやすいです。
例えば、「オープンポジションで入社したAさんは、営業経験を活かしつつ、新規事業の立ち上げにも関わり、現在は事業部長として活躍しています」といった具体例を示すことで、候補者は自分の将来像を描きやすくなります。
無料ツールを使った求人票の一括管理
ここまでで、Wantedlyを活用した求人票の設計方法、3つのフィットの考え方、求人票の使い分け、オープンポジションの活用について解説してきました。最後に、これらの求人票を効率的に管理・配信するための無料ツールについて紹介します。
engageやAirワーク採用管理の活用
求人票の作成が完了したら、次はそれを各種求人サイトに掲載する作業に入ります。しかし、複数の求人サイトに個別に情報を登録していくのは、非常に手間がかかります。
そこで活用したいのが、engage(エン・ジャパン提供)やAirワーク採用管理(リクルート提供)といった無料のATS(採用管理システム)です。
これらのツールは、以下のような機能を提供しています。
- 求人票の一括作成:1つのプラットフォームで求人票を作成すれば、その情報を複数の求人サイトに自動で転記できます。
- 応募者管理:各求人サイトから応募があった候補者を、1つのダッシュボードで管理できます。
- 無料求人サイトへの自動掲載:IndeedやGoogleしごと検索、求人ボックスなど、主要な無料求人サイトへの掲載が自動で行われます。
具体的な活用の流れ
- engageやAirワーク採用管理に求人票を登録 前述の手順で作成した求人票(理想の人材求人、チャレンジ枠求人、オープンポジション)を、それぞれツールに登録します。
- 各種求人サイトへの自動掲載 ツールが提携している求人サイト(Indeed、Googleしごと検索、求人ボックス、スタンバイなど)に、自動で求人情報が掲載されます。これにより、複数の媒体に同時にリーチすることが可能になります。
- 応募者の一元管理 各サイトから応募があった候補者の情報は、ツールのダッシュボードに集約されます。選考ステータスの管理、面接日程の調整、候補者とのメッセージのやり取りなども、すべて1つのプラットフォームで完結します。
- データ分析と改善 どの求人票からの応募が多いか、どの媒体からの流入が多いか、といったデータを分析し、求人票の内容や掲載媒体の見直しに活かします。
無料ツールの限界と有料オプション
もちろん、無料ツールには限界もあります。例えば、掲載できる求人数に制限があったり、一部の有料求人サイトへの連携は有料プランが必要だったりします。しかし、まずは無料の範囲で始めてみて、採用活動の効果を検証した上で、必要に応じて有料プランや有料媒体への投資を検討するのが賢明です。
特に採用予算が限られている地方企業にとって、無料ツールの活用は、採用活動の第一歩として非常に有効な選択肢です。
まとめ:求人票は候補者との最初の接点
ここまで、無料でできる「良い求人票」の作り方について、具体的な手順を解説してきました。最後に、重要なポイントを振り返っておきましょう。
良い求人票を作るための5つのステップ
- Wantedlyで競合分析:類似職種の人気求人票を5社ピックアップし、Wantedlyの「なにをやっているのか」「なぜやるのか」「どうやっているのか」「こんなことやります」の4軸で分析します。
- 自社の独自性を明確化:他社との比較を通じて、自社ならではの魅力や強みを言語化します。
- 3つのフィットを意識:ビジョンフィット、カルチャーフィット、スキルフィットの3つの観点で、求人票の内容を設計します。
- 求人票を使い分ける:理想の人材求人とチャレンジ枠求人の2つを用意し、即戦力とポテンシャル人材の両方にアプローチします。
- 無料ツールで効率化:engageやAirワーク採用管理を活用し、求人票の作成・掲載・管理を一元化します。
オープンポジションで将来の人材とつながる
さらに、オープンポジションを掲載することで、今すぐ転職を考えていない潜在的な候補者とも接点を持つことができます。これは、長期的な採用戦略として非常に有効です。
求人票はコミュニケーションツール
最も重要なのは、求人票を単なる「募集要項」として捉えるのではなく、候補者とのコミュニケーションツールとして捉えることです。求人票は、自社のビジョン、カルチャー、仕事のやりがいを伝える、最初の、そして最も重要な接点です。
地方企業にとって、採用は組織の成長を左右する重要な経営課題です。大手企業が新卒給与を引き上げる中で、給与という条件面だけで競争するのではなく、地域への想いや職場の魅力を丁寧に伝えることで、総合的な満足度を高めて採用していくことが必要です。だからこそ、求人票でビジョンやカルチャーをしっかり伝えることが、これまで以上に重要になっています。
高額な採用費をかけなくても、工夫次第で「良い求人票」を作り、優秀な人材を惹きつけることは十分に可能です。本記事で紹介した手法を実践し、自社に合った求人票を設計してください。そして、その求人票を通じて、ビジョンに共感し、ともに成長していく仲間を見つけてください。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。