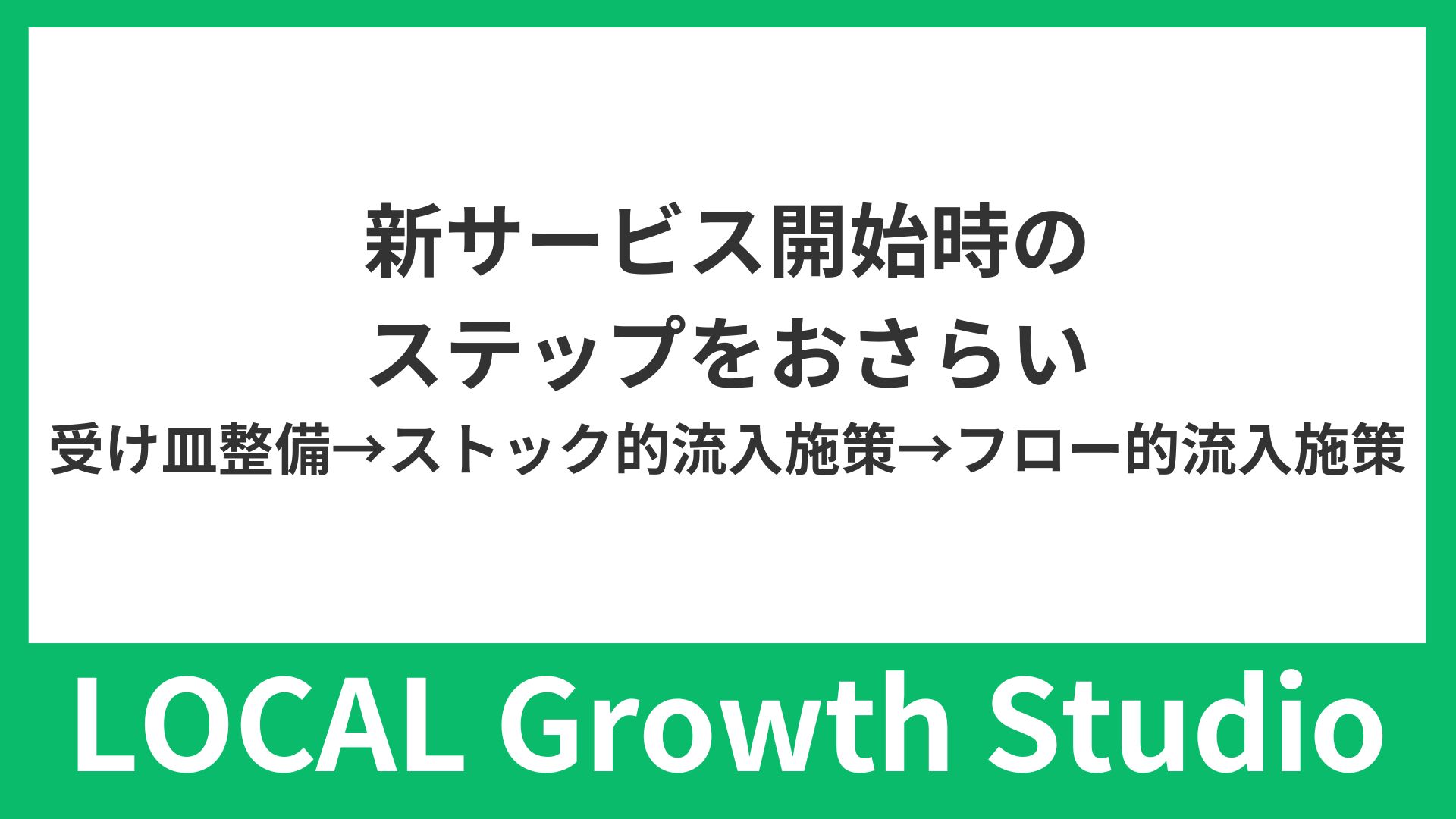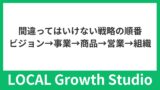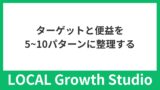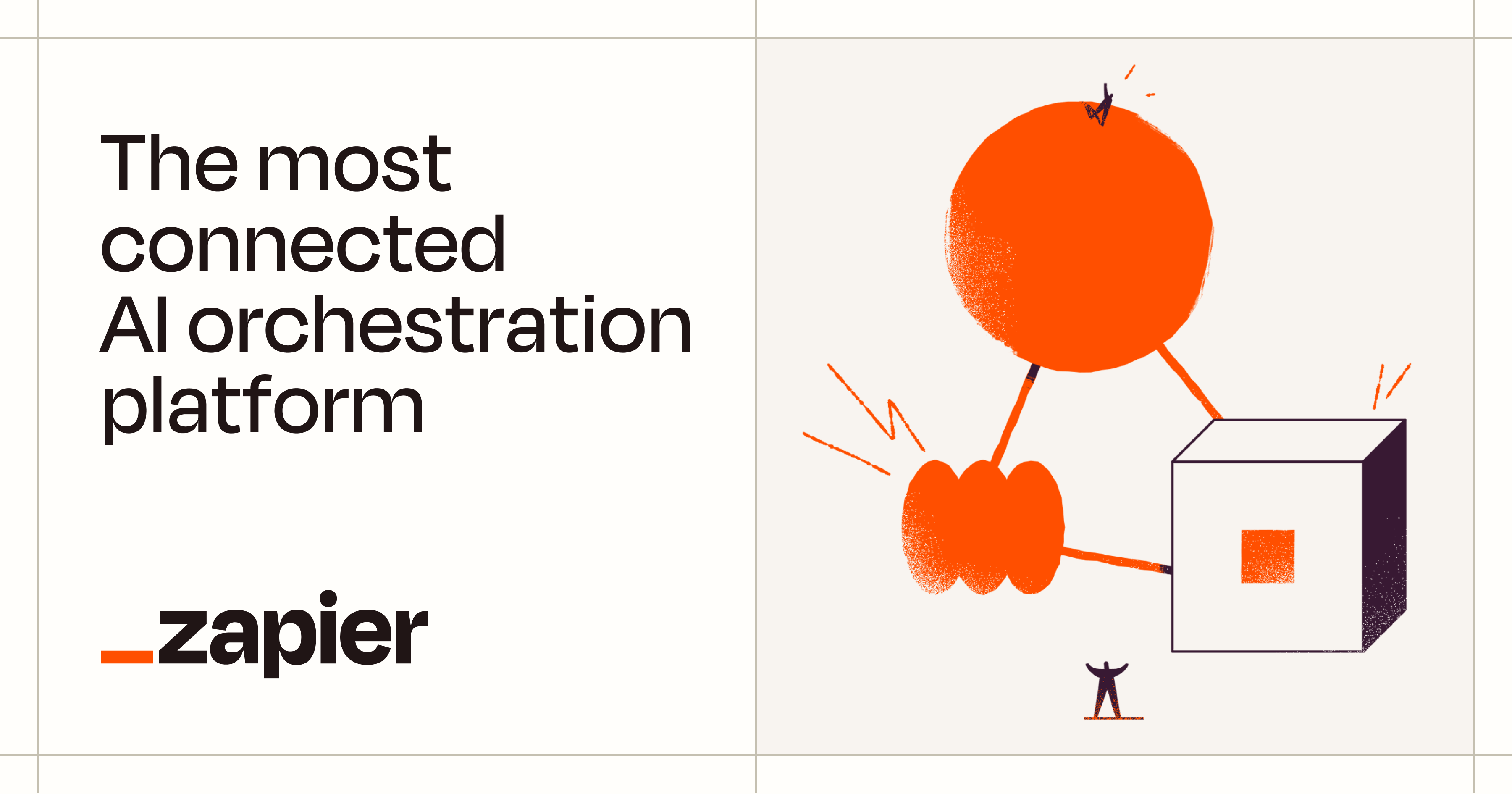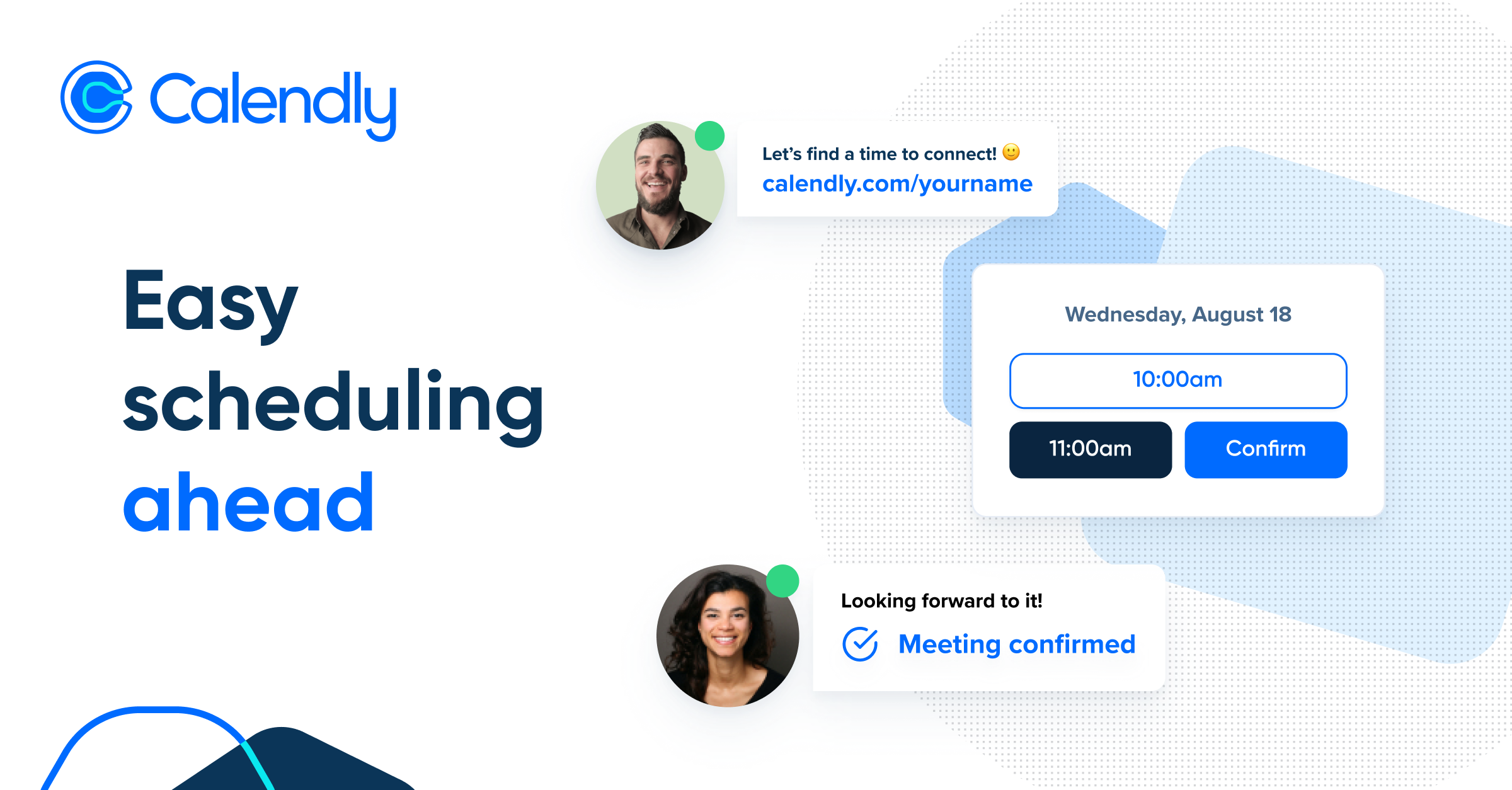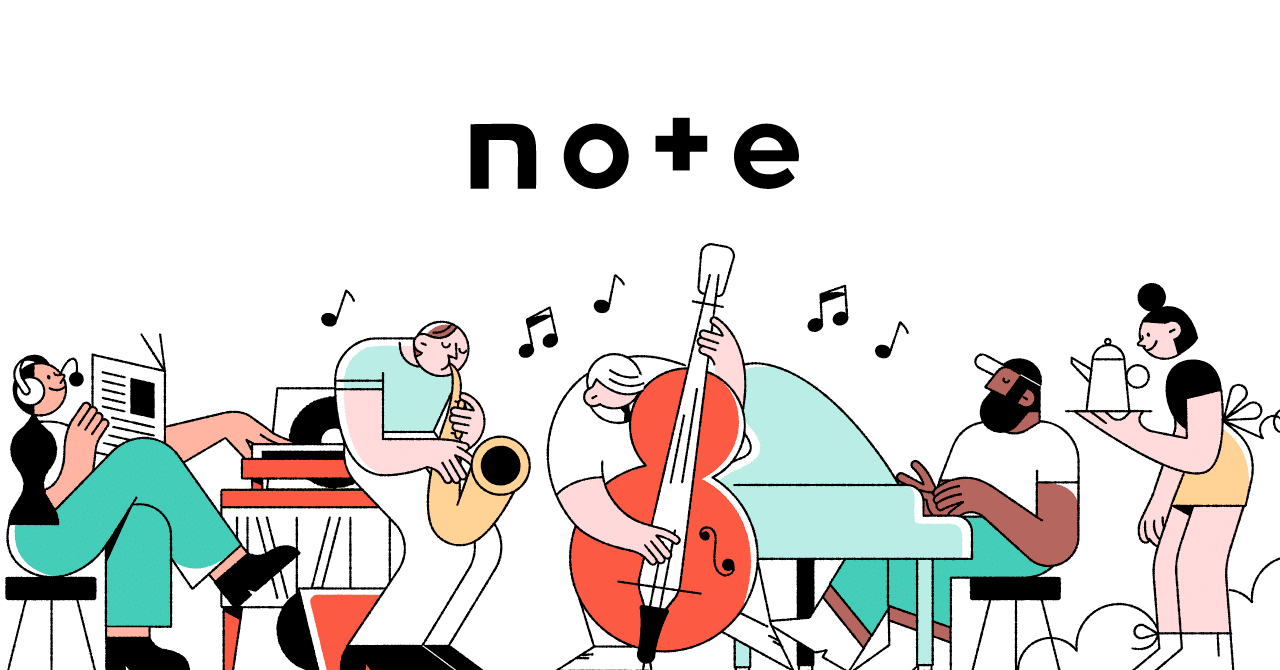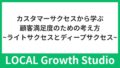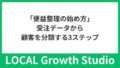ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
この記事は、「新サービス開始時のステップをおさらい:受け皿整備→ストック的流入施策→フロー的流入施策」について記載しています。
新サービス開始時の悩み
新しいサービスを開始するとき、「何から始めていいかわからない」という悩みを抱える方は非常に多いです。
特に、インターネットを活用してサービスを告知していこうと考えたとき、選択肢が多すぎて迷ってしまいます。Web広告を出すべきか、SNSで発信すべきか、ホームページを作るべきか、それとも営業活動から始めるべきか。どれも正解のように思えるし、どれから手をつければいいのか判断がつきません。
さらに、予算や時間が限られている中で、効率的に顧客を獲得したいというプレッシャーもあります。「早く成果を出さなければ」という焦りから、目先の施策に飛びついてしまい、結果として効果が出ずに予算を使い果たしてしまうケースも少なくありません。
本記事では、新サービス開始時に行うべきステップを、正しい順番で解説していきます。この順番を守ることで、効率的に顧客を獲得し、持続的な成長を実現することができます。
4つのステップの全体像
新サービスを開始する際のステップは、大きく4つに分けられます。
ステップ1:サービスの設計 誰に、何を、どのように提供するのかを明確にする段階です。
ステップ2:受け皿の整備 顧客がサービスを理解し、安心して問い合わせできる環境を作る段階です。
ステップ3:ストック的流入施策 中長期的に効果が持続する、資産となる施策を実施する段階です。
ステップ4:フロー的流入施策 短期的に集客を加速させる、変動費を使った施策を実施する段階です。
この順番が非常に重要です。多くの企業が、ステップ2や3を飛ばして、いきなりステップ4のフロー的流入施策(広告や営業活動)から始めてしまいます。しかし、それでは効率が悪く、コストばかりがかさんでしまいます。
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
ステップ1:サービスの設計
最初のステップは、サービスそのものの設計です。ここがしっかりしていないと、どんなにマーケティング施策を打っても成果は出ません。
クリアすべき項目
サービス設計でクリアすべき項目は、以下の3つです。
1. 自社の強みが生かせる独自性のあるサービス設計
まず、自社の強みが生かせるサービスになっているかを確認します。他社と比べて、明確な独自性がある必要があります。
独自性を生み出すポイントは、以下のような観点です。
- 特定の業界や企業規模に特化している(例:製造業専門、従業員30名以下の企業専門)
- 特定の課題解決に特化している(例:採用難に特化、EC売上向上に特化)
- 独自のノウハウや実績がある(例:〇〇業界で10年の経験、〇〇社の支援実績)
- 提供方法に独自性がある(例:完全オンライン対応、夜間・休日対応可能)
「何でもできます」というサービスは、結局「何もできない」と思われてしまいます。明確に「これが得意です」と言えるサービス設計が重要です。
2. 提供価値と価格が明確になっている
顧客に提供する価値が明確で、それに見合った価格設定ができているかを確認します。
提供価値を明確にするためには、以下の問いに答えられる必要があります。
- 顧客はどんな課題を抱えているのか?
- その課題を、あなたのサービスはどう解決するのか?
- 解決した結果、顧客にどんな良いことが起こるのか?
そして、価格設定については、前回の記事「間違ってはいけない戦略の順番」でも触れたように、ターゲットが感じる価値に対して決めることが重要です。顧客が現在その課題解決のためにかけているコスト(代替策の費用)や、解決によって得られる効果を踏まえて、納得感のある価格を設定します。
3. 重点ターゲット群が2〜5つ程度設定できている
「誰でもターゲットです」というサービスは、誰にも刺さりません。重点的にアプローチすべきターゲット群を、2〜5つ程度に絞り込む必要があります。
例えば、Webマーケティング支援サービスであれば、以下のようなターゲット設定が考えられます。
- ターゲット1:地方の製造業(従業員50名以下)で、初めてWeb広告に取り組む企業
- ターゲット2:BtoB向けSaaS企業(創業3年以内)で、リード獲得を強化したい企業
- ターゲット3:ECサイト運営企業(年商1億円以上)で、広告運用を内製化したい企業
このように、ターゲットを具体的に設定することで、それぞれに刺さるメッセージやアプローチ方法を考えることができます。
サービス設計がしっかりできていないまま、次のステップに進んでも、顧客に刺さらず、成果は出ません。まずは、この3つの項目をクリアすることに集中しましょう。
ステップ2:受け皿の整備
サービス設計ができたら、次は「受け皿の整備」です。受け皿とは、顧客があなたのサービスを知り、理解し、安心して問い合わせできる環境のことです。
多くの企業が、受け皿の整備を軽視して、すぐに集客施策に走ってしまいます。しかし、受け皿が整っていない状態で集客しても、せっかく訪れた見込み客が離脱してしまい、コストが無駄になってしまいます。
クリアすべき項目
受け皿の整備でクリアすべき項目は、以下の5つです。
1. サービス内容がわかる(Webサイトページなど)
まず、サービスの内容が明確にわかるWebページを用意します。最低限、以下の情報が掲載されている必要があります。
- サービス名と概要
- 提供価値(顧客の課題と解決方法)
- サービス内容(何をするのか、どこまでやるのか)
- 価格(料金プラン)
- 提供の流れ(申し込みから納品までのステップ)
- 会社情報(会社名、所在地、代表者名など)
見込み客は、このページを見て「自分に合っているか」「信頼できそうか」を判断します。情報が不足していると、不安を感じて離脱してしまいます。
2. 顧客が自社の悩みと課題解決方法がわかる
単にサービス内容を並べるだけでなく、顧客が抱える悩みと、その解決策を丁寧に説明する必要があります。
具体的には、以下のようなコンテンツを用意します。
- 「こんなお悩みはありませんか?」という形で、ターゲットが抱える典型的な課題を列挙する
- それぞれの課題に対して、あなたのサービスがどう解決するのかを説明する
- 実際の成功事例や参考事例を紹介する(顧客の声、Before/Afterなど)
見込み客は、「自分の悩みが書いてある」と感じたときに、初めて興味を持ちます。サービス紹介だけでなく、顧客視点での悩みと解決策を丁寧に説明することが重要です。
3. 十分に情報収集でき比較検討ができる
特に無名のサービスの場合、見込み客は複数のサービスを比較検討しています。あなたのWebページを見ているとき、横には競合他社のページが開かれていると想像してください。
その状況で、あなたのページが「専門性の高さ」「安心感」「信頼感」「納得度」において、同率3位以上のクオリティになっている必要があります。
具体的には、以下のようなコンテンツを充実させます。
- ノウハウ記事(例:「〇〇を成功させるための5つのポイント」)
- わかりやすい図解資料(例:「サービス導入の流れ」「料金プランの比較表」)
- よくある質問(FAQ)
- 実績や受賞歴、メディア掲載情報
- 代表者や担当者のプロフィール
情報量が少なく、薄っぺらいページでは、見込み客は「この会社で大丈夫かな?」と不安を感じてしまいます。十分な情報を提供し、安心して問い合わせできる状態を作ることが重要です。
4. 問い合わせ導線の整備
見込み客が「問い合わせしよう」と思ったとき、スムーズに問い合わせできる導線を用意します。
具体的には、以下のような工夫が有効です。
- 問い合わせフォームをページに埋め込む(別ページに遷移させない)
- 入力項目を最小限にする(名前、メールアドレス、簡単な質問内容程度)
- 「3分で完了」「まずは無料相談」など、ハードルを下げる表現を使う
- 電話番号やメールアドレスも併記し、好きな方法で問い合わせできるようにする
問い合わせのハードルが高いと、せっかく興味を持った見込み客が離脱してしまいます。できるだけ簡単に、気軽に問い合わせできる導線を作りましょう。
5. 自動返信などのストレスのない日程調整の整備
問い合わせを受けた後の対応も、受け皿の一部です。問い合わせ後、すぐに自動返信メールが届き、次のステップがわかる仕組みを作ります。
具体的には、以下のような仕組みが有効です。
- Zapierなどのツールを使い、問い合わせがあったらSlackに自動通知される仕組みを作る
- 自動返信メールに、SpirやCalendlyなどの日程調整ツールのリンクを埋め込む
- 見込み客が自分で都合の良い日時を選べるようにし、日程調整のやり取りを減らす
問い合わせ後、返信が遅かったり、日程調整に何度もメールをやり取りしなければならないと、見込み客はストレスを感じます。スムーズな対応ができる仕組みを整えることで、商談化率を高めることができます。
受け皿の整備は、地味で時間がかかる作業です。しかし、ここをしっかり作り込むことで、その後の集客施策の効果が大きく変わります。急がば回れ、という言葉の通り、まずは受け皿をしっかり整えましょう。
ステップ3:ストック的流入施策
受け皿の整備ができたら、次は「ストック的流入施策」です。ストック的流入施策とは、一度実施すれば中長期的に効果が持続する施策のことです。
ストック施策の特徴は、以下の通りです。
- 初期に時間や労力がかかる
- すぐには効果が出ない(効果が出るまで数ヶ月〜1年程度かかることもある)
- 一度積み上げれば、その後も継続的に効果が出続ける
- 変動費がかからない(または少ない)
多くの企業が、すぐに効果が出るフロー施策(広告など)に飛びつきがちですが、中長期的に事業を成長させるためには、ストック施策を粘り強く積み上げることが非常に重要です。
クリアすべき項目
ストック的流入施策でクリアすべき項目は、以下の通りです。
1. PR TIMESによる被リンク(バックリンク)の獲得
PR TIMESなどのプレスリリース配信サービスを活用し、自社サイトへの被リンクを獲得します。被リンクとは、他のサイトから自社サイトへのリンクのことで、SEO(検索エンジン最適化)において重要な要素です。
PR TIMESに掲載されると、多くのニュースサイトやメディアに転載されることがあり、一気に複数の被リンクを獲得できる可能性があります。また、プレスリリース自体が検索結果に表示されることで、社名やサービス名で検索した際の露出も増えます。
2. noteなどによる強いドメインサイトからの流入導線の作成
noteなど、ドメインパワーの強い外部プラットフォームにコンテンツを投稿し、自社サイトへの流入導線を作ります。
例えば、自社ブログで書いた記事の一部をnoteに転載し、「続きはこちら」という形で自社サイトへ誘導する方法があります。noteはドメインパワーが強いため、検索結果で上位表示されやすく、そこから自社サイトへの流入を増やすことができます。
3. 動画・音声メディアなど過去アーカイブが見返せるメディアでの告知
YouTubeやPodcastなど、過去の投稿が蓄積され、後から見返せるメディアでサービスを告知します。
これらのメディアの特徴は、投稿が資産として残り続けることです。例えば、YouTubeに投稿した動画は、数ヶ月後、数年後にも検索され、視聴される可能性があります。Podcastも同様に、過去のエピソードがプラットフォーム上に残り、新しいリスナーが後から聴くことができます。
地道にコンテンツを積み上げていくことで、徐々に流入が増えていきます。一方、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSは、投稿がタイムラインで流れていきやすく、ストック資産としての効果は限定的です。
4. パートナーやアライアンス企業などの他社との共同告知による被リンクの獲得や社名検索の導線
他社と提携し、お互いのサービスを紹介し合うことで、被リンクを獲得したり、社名検索の導線を作ります。
例えば、以下のような方法があります。
- パートナー企業のWebサイトに、自社サービスの紹介ページを作ってもらう
- 共同でセミナーやウェビナーを開催し、相互に告知する
- 相互にプレスリリースで提携を発表し、お互いの社名を露出する
他社と協力することで、単独では届かなかった見込み客にリーチできる可能性があります。
5. SNSでのフォロワーの獲得
XやLinkedIn、Facebookなどで、継続的に情報発信を行い、フォロワーを獲得します。フォロワーは、あなたの情報に興味を持っている見込み客の集まりです。
フォロワーが増えれば、新しいサービスやキャンペーンを告知した際に、多くの人にリーチできるようになります。これもストック型の資産です。
6. 取材記事メディアなど検索が残り続けるメディアへの露出
業界メディアや地域メディアなどに取材してもらい、記事として掲載してもらいます。こうした記事は、長期間検索結果に残り続けるため、継続的に流入が期待できます。
また、第三者(メディア)が紹介してくれることで、自社で発信するよりも信頼性が高まります。
ストック的流入施策は、すぐには効果が出ないため、途中で諦めてしまう企業が多いです。しかし、粘り強く継続することで、徐々にオーガニック流入(自然検索やSNSなどからの無料流入)が増え、広告費をかけなくても顧客が集まる状態を作ることができます。
ステップ4:フロー的流入施策
ストック施策を積み上げながら、並行して行うのが「フロー的流入施策」です。フロー的流入施策とは、変動費や時間をかけて、短期的に集客を加速させる施策のことです。
フロー施策の特徴は、以下の通りです。
- 即効性がある(実施すればすぐに効果が出る)
- 変動費がかかる(広告費や営業活動の時間コスト)
- 継続しなければ効果が止まる(広告を止めれば流入も止まる)
フロー施策は、短期的に成果を出したい場合や、特定のタイミング(新サービスローンチ、キャンペーン期間など)で集客を強化したい場合に有効です。
クリアすべき項目
フロー的流入施策でクリアすべき項目は、以下の通りです。
1. 成果報酬型のアフィリエイトやメディアの活用
成果報酬型のアフィリエイトプログラムを活用し、他社のメディアやインフルエンサーに自社サービスを紹介してもらいます。
成果報酬型であれば、実際にコンバージョン(問い合わせや成約)が発生したときだけ費用が発生するため、リスクが少ないです。ただし、アフィリエイト報酬の設計や、パートナーとの関係構築には時間がかかります。
2. SNSでの拡散を狙った投稿
通常のSNS投稿とは別に、意図的に拡散を狙った投稿を行います。例えば、以下のような投稿です。
- 業界の話題性のあるテーマについての意見
- 実績や成果の具体的な数値を公開する投稿
- ユーザーにとって有益なノウハウやTipsをまとめた投稿
こうした投稿がバズれば、一気に多くの人にリーチできます。ただし、狙ってバズらせるのは難しく、継続的に投稿し続ける必要があります。
3. 各種広告(リスティング、SNS、動画、ディスプレイなど)
最も即効性が高いのが、Web広告です。主な広告の種類は以下の通りです。
- リスティング広告:GoogleやYahoo!の検索結果に表示される広告。特定のキーワードで検索した人にリーチできる。
- SNS広告:Facebook、Instagram、X、LinkedInなどのSNSに表示される広告。詳細なターゲティングが可能。
- 動画広告:YouTubeなどの動画プラットフォームに表示される広告。視覚的に訴求できる。
- ディスプレイ広告:Webサイトやアプリに表示されるバナー広告。認知拡大に有効。
広告は、予算をかければすぐに流入を増やせますが、広告を止めれば流入も止まります。また、広告費が高騰している昨今、費用対効果を慎重に見極める必要があります。
4. アウトバウンドによる営業活動
自ら見込み客にアプローチする営業活動も、フロー施策の一つです。具体的には、以下のような方法があります。
- コールドコール(テレアポ):リストを作成し、電話でアプローチする
- フォーム問い合わせ:企業のWebサイトの問い合わせフォームから連絡する
- LinkedIn連絡:LinkedInで見込み客を検索し、メッセージを送る
- 過去名刺連絡:過去に交換した名刺の相手に連絡する
- Xアカウント連絡:XのDM機能を使って見込み客にアプローチする
アウトバウンド営業は、時間と労力がかかりますが、確実に見込み客とコンタクトを取れるメリットがあります。
5. リファラルによる営業活動
既存の関係性を活用して、紹介をもらう営業活動です。具体的には、以下のような方法があります。
- 知人・友人:個人的なネットワークから紹介をもらう
- 顧問:顧問契約を結んでいる人に紹介をもらう
- アライアンスパートナー:提携企業から紹介をもらう
- 既存顧客:満足している既存顧客から紹介をもらう
リファラル営業は、信頼関係が前提となるため、成約率が高い傾向にあります。ただし、紹介をもらうためには、日頃から良好な関係を築いておく必要があります。
フロー的流入施策は、即効性がある一方で、変動費や時間がかかります。そのため、受け皿が整っていない状態で実施すると、せっかくの見込み客を逃してしまい、コストが無駄になります。
なぜ順番が重要なのか
ここまで、4つのステップを解説してきました。改めて強調したいのは、この順番を守ることが非常に重要だということです。
フロー施策を先にやってはいけない理由
多くの企業が、受け皿の整備やストック施策を飛ばして、いきなりフロー施策(広告や営業活動)から始めてしまいます。なぜなら、フロー施策は即効性があり、すぐに成果が見えるからです。
しかし、受け皿が整っていない状態でフロー施策を実施すると、以下のような問題が発生します。
1. コンバージョン率(問い合わせ率)が低い
受け皿が整っていないと、せっかくWebサイトに訪れた見込み客が、十分な情報を得られず、不安を感じて離脱してしまいます。
例えば、Web広告で100人をサイトに誘導しても、受け皿が整っていなければ、問い合わせに至るのは1〜2人程度です。一方、受け皿がしっかり整っていれば、5〜10人が問い合わせしてくれるかもしれません。
コンバージョン率が低いということは、広告費の無駄が多いということです。同じ予算をかけても、受け皿の有無で成果が5倍以上変わることもあります。
2. 変動費と時間が無駄になる
フロー施策には、変動費(広告費など)や時間(営業活動の時間)がかかります。受け皿が整っていない状態で実施すると、これらのコストが無駄になってしまいます。
例えば、月50万円の広告費をかけても、受け皿が整っていなければ、ほとんど成果が出ず、予算を使い果たしてしまいます。その結果、「広告は効果がない」と判断し、マーケティング活動自体を諦めてしまうケースもあります。
3. 改善のためのデータが溜まらない
受け皿が整っていない状態で広告を出しても、「なぜ問い合わせに至らなかったのか」を分析することが難しいです。Webサイトの問題なのか、広告のターゲティングの問題なのか、サービス自体の問題なのか、切り分けができません。
一方、受け皿がしっかり整っていれば、広告のクリック率、サイトの滞在時間、問い合わせ率などのデータを元に、どこに問題があるかを特定し、改善していくことができます。
正しい順番で進めるメリット
逆に、正しい順番で進めると、以下のようなメリットがあります。
1. コンバージョン率が高まり、効率的に顧客を獲得できる
受け皿が整っている状態でフロー施策を実施すれば、訪れた見込み客がしっかり情報を得て、安心して問い合わせできます。その結果、少ない予算や時間で、多くの顧客を獲得できます。
2. ストック資産が積み上がり、中長期的に集客が安定する
ストック施策を先に実施しておくことで、フロー施策を実施している間にも、オーガニック流入が徐々に増えていきます。その結果、広告費をかけなくても、一定数の見込み客が集まる状態を作ることができます。
3. 改善サイクルが回り、成果が向上し続ける
受け皿が整い、データが溜まることで、「どのターゲットの反応が良いか」「どのページで離脱が多いか」などを分析し、改善していくことができます。PDCAサイクルを回すことで、成果が向上し続けます。
焦る気持ちはわかりますが、順番を守ることで、結果的に最短距離で成果を出すことができます。急がば回れ、です。
ストック施策とフロー施策のバランス
ストック施策とフロー施策、どちらが重要かという議論がありますが、答えは「両方重要」です。ただし、そのバランスとタイミングが重要です。
フロー施策の課題
フロー施策は即効性がある一方で、以下のような課題があります。
変動費や時間をかけるのをやめると、問い合わせが止まる
広告を出している間は問い合わせが来ますが、広告を止めた途端に問い合わせがゼロになります。営業活動も同様で、アプローチを止めれば、新規の商談は生まれません。
つまり、フロー施策だけに依存していると、常に変動費や時間をかけ続けなければならず、事業が疲弊してしまいます。
競合が増えると、広告費が高騰する
Web広告は入札制のため、競合が増えれば広告費が高騰します。数年前は1クリック100円だったものが、今では500円になっているというケースも珍しくありません。
広告費が高騰すると、費用対効果が合わなくなり、広告を出せなくなってしまいます。
ストック施策の重要性
一方、ストック施策は効果が出るまで時間がかかりますが、以下のような強みがあります。
中長期的に効果が持続する
一度作ったコンテンツや、獲得したフォロワーは、その後も継続的に効果を発揮します。広告のように「止めたら終わり」ではなく、積み上げたものが資産として残ります。
オーガニック流入の最大化により、変動費を削減できる
ストック施策を積み上げることで、検索エンジンやSNSからのオーガニック流入が増えます。オーガニック流入は無料(または低コスト)で獲得できるため、変動費を大幅に削減できます。
例えば、SEO対策をしっかり行い、検索結果で上位表示されるようになれば、広告を出さなくても、毎月安定的に見込み客が訪れるようになります。
理想的なアプローチ
重要なのは、ストック施策を先に積み上げてから、フロー施策に移行するという順番です。
まず、ストック施策に集中する サービス開始当初は、受け皿の整備とストック施策に注力します。コンテンツ作成、SEO対策、被リンク獲得、SNSでの発信など、資産となる施策を積み上げます。この段階では、フロー施策は最小限に留め、既存ネットワークへのアプローチや小規模な広告テストにとどめます。
次に、フロー施策を拡大する ストック資産がある程度積み上がり、オーガニック流入が増えてきたら、フロー施策を本格的に拡大します。効果が出ている広告の予算を増やし、営業体制を強化します。ただし、ストック施策も継続し、資産を積み上げ続けることが重要です。
安定してもストック施策は継続する 事業が安定してきても、ストック施策をゼロにしてはいけません。フロー施策だけに依存すると、何かの理由(広告費の高騰、規約変更など)でフロー施策が使えなくなったときに、集客が止まってしまいます。常にストック資産を積み上げ続けることが、長期的な安定につながります。
マーケティング費用の配分戦略
最後に、マーケティング費用の配分について考えてみましょう。
初期投資の考え方
新サービス開始時は、まず受け皿の整備とストック施策に投資を行うことが望ましいです。
具体的には、以下のような費用配分が考えられます。
初期の費用配分例
- Webサイト制作・改修:50万円〜100万円
- コンテンツ作成(記事、動画など):月10万円〜30万円
- PR TIMES等のプレスリリース配信:月3万円〜5万円
- 広告費(テスト運用):月10万円〜30万円
この段階では、受け皿を作り、ストック資産を積み上げることに予算の大半を使います。広告は、テスト運用として小規模に実施し、どのターゲットや訴求が効果的かを見極めます。
成長段階の費用配分
ストック資産が積み上がり、オーガニック流入が増えてきたら、徐々にフロー施策(特に広告)の予算を増やしていきます。
成長段階の費用配分例
- コンテンツ作成(継続):月10万円〜20万円
- 広告費(拡大運用):月50万円〜200万円
- 営業人件費(体制強化):月50万円〜100万円
この段階では、効果が実証された施策に予算を集中投下します。ただし、ストック施策も継続し、資産を積み上げ続けることが重要です。
注意すべきポイント
マーケティング費用の配分で注意すべきポイントは、以下の通りです。
1. 初期から広告に大きな予算をかけない
受け皿が整っていない段階で、大きな広告予算をかけても、無駄になる可能性が高いです。まずは少額でテストし、受け皿を改善しながら、徐々に予算を増やしていくのが賢明です。
2. ストック施策をゼロにしない
事業が成長してきても、ストック施策をゼロにしてはいけません。フロー施策だけに依存すると、何かの理由(広告費の高騰、規約変更など)でフロー施策が使えなくなったときに、集客が止まってしまいます。
常に一定の予算をストック施策に割き、資産を積み上げ続けることが、長期的な安定につながります。
3. 効果測定を徹底する
どの施策にどれだけ費用をかけ、どれだけの成果が出たかを、しっかり測定します。効果が出ていない施策は見直し、効果が出ている施策に予算を集中させることで、投資対効果を最大化できます。
まとめ:焦らず、順番を守る
新サービスを開始するとき、「早く成果を出したい」という焦りから、いきなり広告を出したり、営業活動を始めたりしがちです。しかし、それでは効率が悪く、コストばかりがかさんでしまいます。
本記事で解説した4つのステップを、正しい順番で進めることが重要です。
ステップ1:サービスの設計 自社の強みが生かせる独自性のあるサービスを設計し、重点ターゲットを明確にします。
ステップ2:受け皿の整備 顧客がサービスを理解し、安心して問い合わせできる環境を整えます。情報量を充実させ、専門性・信頼感・納得度を高めます。
ステップ3:ストック的流入施策 中長期的に効果が持続する施策を実施します。被リンクの獲得、コンテンツの積み上げ、フォロワーの獲得など、資産を積み上げます。
ステップ4:フロー的流入施策 変動費や時間をかけて、短期的に集客を加速させます。広告、営業活動、リファラルなど、即効性のある施策を実施します。
この順番を守ることで、以下のメリットがあります。
- コンバージョン率が高まり、効率的に顧客を獲得できる
- ストック資産が積み上がり、中長期的に集客が安定する
- 改善サイクルが回り、成果が向上し続ける
特に重要なのは、フロー的流入施策を実施する前に、受け皿の整備とストック施策をしっかり行うことです。変動費や時間をかけるのは、受け皿が整い、顧客が納得し安心感をもって問い合わせができる状態を作ってからです。
また、フロー施策だけに依存せず、ストック施策を粘り強く継続することで、オーガニック流入の最大化を目指しましょう。広告を止めても顧客が集まる状態を作ることが、持続的な成長の鍵となります。
マーケティング費用の配分では、初期に受け皿の整備やストック施策に投資を行い、徐々にフロー施策の変動費に予算配分をかけていくことが望ましいです。
焦らず、順番を守り、着実に積み上げていくことで、新サービスを成功に導くことができます。地方企業の皆さんも、ぜひこのステップを参考に、新サービスの立ち上げを進めてみてください。
「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)
つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director
リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。